授業のたとえ
2023年4月17日
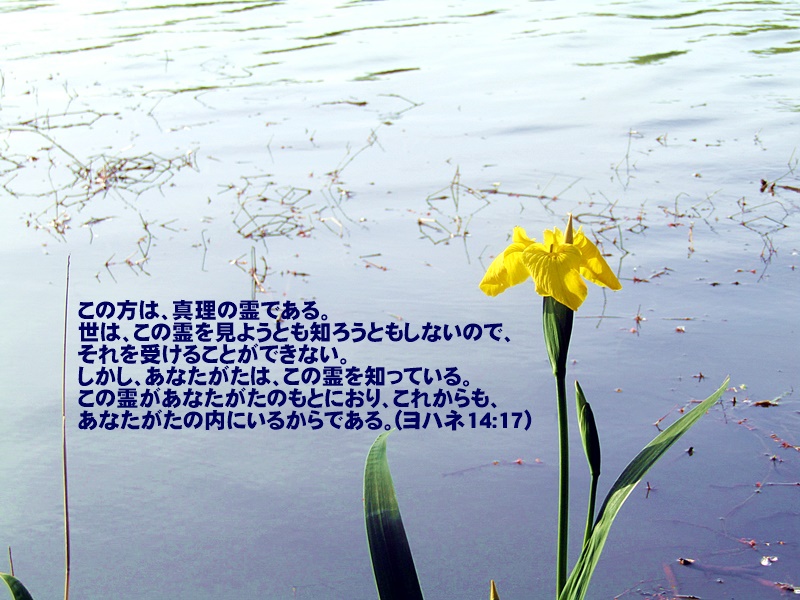
これは学習塾の話である。教師の立場の話である。子どもたちに、受けてよかった、と思われることを語りたいと思っている。言うまでもないが「ウケて」ではない。
テキストを解説するのは当然。書いてあることが分かる。もちろん。それを基にして、問われてきた問題に解答することができるようになる。そうありたい。その連続が、入試合格へと導くことになる。それが目的だ。
だが、それで終わりなのか。それが目的かもしれない。でもその次に何かつながるものをそこに含ませていなければならない、と私は思っている。生徒にとっては、受験合格が目標で、それに役立てればいい、というところしか考えられていないかもしれないし、そのためのサービスをもちろん表向きのウリとすることは当然だ。それでも、その向こうに何があるか、それを見据えて語るのでなければならない、と私は自戒しているのである。
そんな私はどうであれ、とりあえず授業の形を作ればよい、そんなことを考える塾教師はいない。授業らしいものを語っておけば、仕事は完了だとは考えない。そこから先は生徒一人ひとりが頑張るべきだ、教師の責任は授業でひととおり話すだけであり、あとは生徒の自己責任だ、そんな態度をとる教師は、もしかすると公立学校の教諭の中には一人くらいいるかもしれないけれども、塾には一人もいないだろう。
教師としては、授業のためにちょっとだけ予習をしましたよ。ほら、こんな難しい本を私は読んでいるんだ。すごいでしょ。実はあんまりよく内容は分からなかったんだけど、だから内容や脈絡というものは理解できいていないことになるんだけど、授業の中で引用しておけば、カッコいいでしょ。形になるじゃん。偉そうに見えるじゃん。
まさか、こんなふうな考えをもったり、こういうことをやったりするような教師は、いるはずがない。自分で強く納得したようなことは何もないのに、教科書にはこのように書いてあります、それはこんな意味です、私たちもこのように生活していきましょう、希望をもちましょう、などと言って授業をいつも終えるような教師がいるとは思えない。
たとえばその「希望」なら、それは聴く者の心の中に生まれ沸き起こるものであって、作文の棒読みのようなつまらない授業の中で「希望をもちましょう」と繰り返しても、ちっとも起こるものではないだろう。
自分もそう思うよ。生きていくときに役立ったんだよ。確かに教科書に書かれてあることは嘘ではないけれど、それはこんなふうに理解できるし、実際にこんなふうに役立つんだよ。あるいは、さらにこんなふうな点に気がつくと、この知識が本当に活きてはたらくんだね。これを覚えておくと、本当に楽しくなるよ。
私なら、こちらのほうがいい。生徒も、それを覚えるモチベーションができるのではないか。すると、教科書に書かれていることが、命輝くために働き始めるような気がするのだ。教師自身が、教える内容について実感のないところでは、生徒がわくわくするような授業が成立しているとは思えない。要するにこれは、語る者の内部で、十分咀嚼されたものがあるかないか、ということでもあるだろう。受け売りであるか、自身でよく噛みしめたものであるかどうかは、聴く側には、普通伝わるものである。もちろん、騙されるという場合が世の中に多々あることは認めるけれども。
つまり、もしかするとカルチャーセンターであれば、生徒のほうでも、そこに集まることや、友だちと会えることが目的であるから、授業内容などはどうでもよい、というケースがあるかもしれない、ということだ。名の通った偉い先生の授業に出席していた、という事実にこそ意味があるのであって、難しい内容になど最初から何の魅力もないのかもしれない。しかもそこには金を払って来ており、一定のステイタスを得ているという自負もあり、万事うまく回転しているのだ。もはや授業内容など、大して関心がない、という場合もないとは言えない。
でも、それでよいのだろうか。アレゴリーであれ、比喩であれ、伝わる人には伝わるであろうが、伝わらない鈍感な人には全く何も伝わらないというものが、世の中にはある。聖書の話にしても、それを伝えるものが、時に「聖霊」と呼ばれている神の働きであるようにも思えるのだ。
たとえば、聖書協会共同訳における特徴の一つに、ギリシア語の「ピスティス」について、一部訳し方を大きく変えたところがある。かつて「を信じる信仰」と訳されていたものを「の真実」としたのである。これは属格の解釈に伴うものであるが、当然それにより主体が替わるために、意味合いも異なってくる。
これを礼拝説教で説明するのは悪いことではない。参考書と別の訳の記述をただ並べて、違いを示すのも悪くない。ただ、その違いがどのように生じているか、を、聴く者は知りたがっているはずである。どうしてか。どのようにか。これの説明のためには、先に挙げた、語る者自らの心の奥底に一度知識を通して、消化して、あるいは反芻して、自分の言葉でそれが説き明かされていくというのが通常の経路であろう。
だが、それができない人が話すとすると、いろいろ不都合なことが起こり得る。たとえば、信仰と真実の意味がある、とだけぷつんと言ったなら、それをしたと言えるのかどうか。現代語ならよいのだが、古代のギリシア語の説明で「真実」という訳語が表に出ることはない。「信実」とした人もいるし、この語自体は、他の通例の場面では「信頼」のように訳されているところも多い。
しかしさらに、人とつながるときには信仰と訳す、神さまとつながるときには真実と訳す、というような説明をもししてしまったら、そういう言い回しでは、説明を聞く側からすると、まず理解不能である。そもそも、人と神とがつながるところに信仰も真実も存在するのではないのだろうか。こうした説明では、まるで人と神とのつながりの接点が、全くないかのようであり、私には理解できない。
これは、人から神へ、神から人へ、という応答の方向性を提示しなければ、区別がつきにくいところである。なぜこういう説明ができないことがあるのか。あるとすればそれは、その人が、自分と神との応答というもの、すなわち自分と神のつながりというものを経験したことがないからであろう。自分の知らないことは、適切に説明できないものである。救いにおける神との出会いと対話、それが生じる場というものを経験していたら、「信仰」と「真実」の使い分けは明白にできるはずである。
この説明を加えた上で、その新しい聖書協会共同訳に教会が変えない理由を、この人物が、新約聖書においては、これまでの新共同訳と殆ど変わっていないからだ、と強調したとする。しかも複数回、強く主張した、と。しかもこのとき、こんな言い方をするかもしれない。殆ど変わっていないこの新しい訳で、一番大きく変えられたのが……のように「ピスティス」のことを説明する。すると、日本語として理解できなくなる。この句の間には、日本語を知る者ならば当然、このような言葉を補うはずである。「いろいろ訳が変えられたけれども」のような言葉があってこそ「一番」という語を使うことができる。しかし、その人物が、しきりに、殆ど変わっていない、と連呼していたとなると、何故か、と考えたくなる。
思うに、教会が新しい聖書を使わないのはどうしてか、という疑問に対する答えが、頭に大きくあったのだろう。だから「殆ど変わっていません」と強く言い切った。だが、いまから「ピスティス」について自分が勉強したことを発表したいために、奇妙なつながりができてしまった。それに気づく日本語能力もなかった、ということではないか。
誤解のないように申し添えておくが、新約聖書も新しい訳は大きく変化している。日本聖書協会が、そのための説明のブックレットを何冊も発行している。新しい訳について少しでも「勉強」する気があったら、「殆ど同じです」などということを繰り返して主張するようなことは、できないはずである。一部の批評家が言った言葉をただ鵜呑みにしたのであろうと推測される。
神との応答。キリスト教会での「礼拝」というものは、すべてその中にある。礼拝のプログラムは、「神から」の項目と、「人から」の項目とが、なるべく交互になるようにつくられている。キリスト者は、一人ひとりが、この神とのやりとりのようなものを深く経験している。それを「祈り」と呼んでもよいかと思う。また、「救い」にしろ「義」にしろ、内実は同じものであるが、方向性により見え方が変わる、ということは、聖書にはいろいろあるだろうと思う。どれも、自分と神との関係性の中で捉えられることである。
教師と生徒との関係が、神と人になぞらえられる、などと言うつもりはない。聖書を語る者と聴く者との関係のほうが、それに近いだろうと思われる。語る者が神を知り、神を見上げながら、そして自分が神から受けたものを、ひとの命のために語るようであってほしい。だから、語る資格は、誰にでもあるのではない。神学校に行くか行かないか、そんなことは聖書には一言も書かれていない。神に活かされ、神との交わりの中で神の命を身に受けて、それを語らねば、伝えねば、という霊に動かされるのであれば、学歴など何の意味もない。つまりは、神との関係をもっていない人物は、福音を語ることはできないし、聖書を解説してもせいぜい一般論に留まる。しかしそこには神から命を受ける通路が欠けている。ぼけた景色しか描けない。そのような人物は、礼拝で語ることはできないのである。
まだいまなら間に合うのだが……目が覚めて、冷静に考えたら、これではいけない、危機へと突き進むだけだ、ということに気づくと思うのだが……。

