名前
2023年3月22日
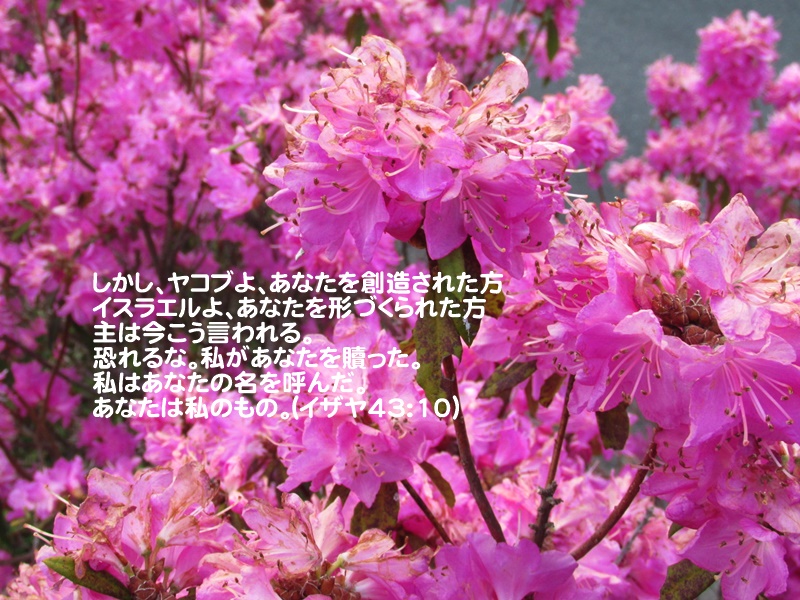
私は、花の名前を知らないほうだった。いまの子どもたちが知らないことに驚く前に、自分の小さなときのことを思い起こせばよかった。しかし、父が苦労して建てた一戸建ての家には、クチナシの木があり、カラーも咲いた。ホウセンカやキンセンカ、サルビアも咲いていたと思う。しかしなんといっても、金網の塀に絡みつくバラが、いちばん印象的だった。
田舎なので、小学校への通学路には野の草花がたくさんあった。ナズナやアブラナも普通にあったし、足元にはオオイヌノフグリやタンポポ、ハハコグサやカラスノエンドウもたくさんあった。田圃にはレンゲソウが彩りを与えており、時折ぽつんと咲く白レンゲを、見つけると摘みに走ったものだった。キツネのボタンやホトケノザも、スズメノテッポウもいくらでもあった。だから、これやカラスノエンドウ、ナズナなどは、音を出して遊ぶのに恰好の素材だった。ヤエムグラやオナモミをくっつけ合って遊ぶこともよくやっていたし、ササの葉を飛ばす競争も楽しかった。四つ葉のクローバーを探すのは得意で、ある場所には八つ葉も九つ葉もあった。
人の親になってから、子どもを写すためにカメラを始めた。理論を知りたいといろいろ学んだら、そのうち花の写真に惹かれるようになった。被写体が基本的に動かない。写し方をじっくり考えて取り組むことができる。裏花の美しさはひとしおだし、虫がとまっていたならうれしいフォトジェニックだ。
なにも名の通った花でなくてもよい。道ばたの草花も、写し方次第では魅力的な写真ができる。そしてこれは何の花だろう、などと図鑑で調べて記録していたのだが、あるとき、自然に詳しい方がそれを見て、これは違う、とずいぶん訂正してくださった。やはり図鑑だけでは、素人には見分けがつかないものだ。
そうでなくても、大人になってから出合う植物は、名前を覚えるのがやはり難しいものだ。言葉になどしなくても、美しいものは美しいし、愛おしいものは愛おしい。言葉なんていらないさ、と中高生時代に尖っていたままにつくって歌っていた詞も多かった。理屈なんかいらない、感性だ、ありのままの君でいい、みたいな気持ちの入った詞だ。殆ど負け惜しみみたいにいまでは思う。
名を呼ぶ、ということは、それを他のものから区別する、ということでもある。哲学の世界ではそういうのをよく「分節する」と言う。言葉で名づけるということは、それをなにか自分との関係の中に置くということでもあり、一種の責任が生まれる場面となることもある。創世記で、ひとが存在者に名前をつけるようにさせたというのは、たんにひとが自然を支配するものだとしたのではない響きがそこにある。神の設定は自然破壊だ、という非難を防ぐために、管理者になったのだという理解もあるが、それもやや読み込みすぎに感じる。一定の関係を築くというところから、押さえていく必要があるのではないか、というのが私の感覚だ。
飼っている熱帯魚に一匹一匹名前をつけている人がいると聞く。そうでなくても、ペットには名前をつけるのは、ある意味で当然であろう。地域猫にも、一人ひとり名前がある。名前を呼べば姿を現すし、近づいてくる。餌のボランティアさんが毎日名前を呼ぶので、それが自分のことなのだろうと、なんらかの形で認識しているのだろうと思われる。
君に名前をつけて呼ぶ。それは、君が自分にとり特別な存在だからだ。こういう背景が、多分にあるに違いない。『星の王子さま』には、特別な花があった。王子さまは、その花に名前をつけはしなかった。けれども、「あの花」と呼んで「ぼく」に話してくれた。それはやはり、特別な花だった。それは、世界のどこにもない花だった。しかし、王子さまは、五千ほどの赤いバラの花の咲きそろっている庭に来たとき、さびしさを覚えた。たくさんの、名もなく区別もつかないような花の群衆がそこにあったのだ。
神は、名もなき者を愛することができないようなお方ではないだろう。だが、一人ひとりの名を呼んできたことを、旧約聖書は証拠立てる。アブラハムやヤコブに、その名を呼んで臨んだ。ハガルのような奴隷娘にも現れたし、実に様々な場面で、人間にその名を呼んで話しかけている。時に、その名を新しく変えて、命名するようなこともした。
神は、私の名をも呼んだ。私は神の目に映ったのだ。

