教会に必要な「きよさ」
2022年10月21日
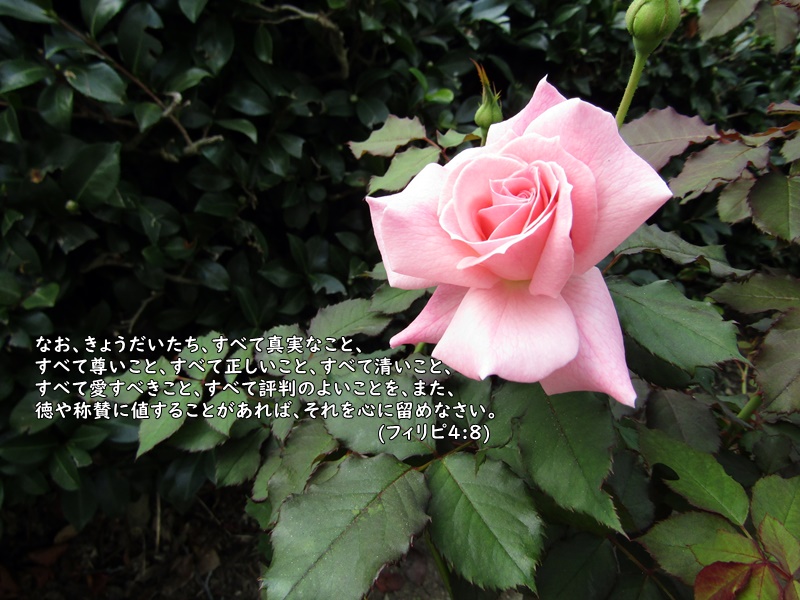
プロとして彼女は、白魚のような指で、ピアノを弾き続けた。
違和感がおありの方は、ピアノを弾く方であろうか。ピアノの弾ける友人がよく言っていた。そんなのは嘘だよ、ピアノを弾くには筋肉が必要なんだから、と。
どうにも勝手なイメージというものが先行することが、世間ではよくある。「クリスチャン」に付く枕詞は「敬虔な」であるように思われているようである。一体いつからそうなったのか知らないが、これに対して教会の説教でも、抵抗する場合がある。信じたから聖い生活ができるものでもないし、立派な人間になるというわけでもない、自分はだめだ、と思うその心から、イエス・キリストを見上げましょう……というような話がありがちである。もちろん、それは間違ってはいない。肩に力の入りすぎるクリスチャンに対して、もっと自然体でいたほうがよい、というメッセージにもなるであろう。
だが、そこからまた、クリスチャンは決して敬虔ではない、というように走るというのも、少し考えものである。それどころか、近年は、「ありのままのあなたでいい」というメッセージが、どうやら幅を利かせている模様。打たれ弱い世代には、「罪がある」という指摘をすると、もう教会には二度と来てもらえなくなる、と思っているかのようである。それとも、語る者自身が、「罪」ということを意識したことがない、という恐ろしいことも、ありうるような気がする。
「ありのままでいい」というメッセージが、すべて間違いだというわけではない。ただ、その意味の内容や受け取り方による、とは言えるだろう。つまり、その言葉には別々の意味が含まれているために、語ったほうの意図とは違う受け方をされていると、よくない誤解が重なっていく、ということである。
罪に敏感であると、自分の言動のすべてが罪であるように思えて仕方がなくなることがある。そのときに、自分で罪を処分することはできないから、イエス・キリストが十字架によってその罪を無効としたのだ、と信じることにより、罪の意識に苛まれているその「あなたのままで」「ありのままで」神の前に出ればよい、というメッセージを送ることは、可能であろう。
だから、敬虔などというレッテルを貼ってほしくない、敬虔の看板に合わせなければ、信仰生活ができない、というような重荷を背負う必要はない。そう考えるのは、決して否定されるべきものではあるまい。
しかし、自然体でよいのだ、というような思い込みが、次々と人間的な論理と感情によって、ずるずると、なんでもありの情況に導いていき、あまつさえそれを正当化してしまうようであれば、それは決定的に拙いことになる。そうしたことは、パウロも、その手紙の中で時折語っていた。すでに聖書は、このような罠に先手を打っていることになる。
どこかにけじめがなければならない。するとその境界をどこに置くか、が難しい。教会はいま、そんなところで思い悩んでいるのかもしれない。だが、教会の外にいる人々のことに目を向けよう。そこには、思いのほか、「きよさ」に期待する人は多いのではないだろうか。教会には、一種の「きよさ」を求めて訪れる人は多いと思う。そこでもしも、この世と同じように風景しか見えないのであれば、わざわざ教会に求めてくる必要はないと判断するだろう。あるいは、その教会はだめだ、と評価するだろう。
まさか、現代人が「きよさ」など求めているものか、などと教会の側が思うようであったら、まさしくもうだめである。子どもたちは、その「きよさ」を理想とする中で生きている。教育はひとつにはそれを与えているし、実際に子どもたちと接していると、子どもたちはたいてい潔癖であるし、ものの道理を弁えていることが分かる。
そして、世の中が「きよさ」を求めているからこそ、「世界の平和」とか「家庭の尊さ」とかいう看板を掲げた政治団体に、一般の人々も「それはよいことだ」と近づいていき、全財産以上のものを献げようとまでするようになるのだし、政治家たちはその「きよさ」を好都合なものと考えて協力を惜しまなくなっていたのではないだろうか。その政治団体が、宗教を利用していればなおさら、その動きに拍車をかけることができていた、というわけである。
平和や家庭の幸福というものを、むしろキリスト教会のほうが、蔑ろにしていなかったか、胸に手を当ててみるべきである。教会の派やグループ毎に意見が違うとして争いを続け、クリスチャンでない家族との間に不穏なものを常に懐いたり、反目していたり、あるいはいま話題になっているように押しつけたりするようなことがなかったか、よくよく省みる必要があると思うのである。
キリスト教会の中に「きよさ」がなかったために、「世界の平和」とか「家庭の尊さ」とかを謳う団体が力を伸ばし得たのだ、と考えるのは、おかしいだろうか。その団体とは関係がありません、という程度の対処しかしていなかったことで、被害者が増え続けていたのだ、という痛みを感じるのは、おかしいだろうか。
よく見よう。新約聖書の手紙の類いを見ると、「きよさ」がたいへん強調されているはずだ。当時、キリストを信じる者たちがマイノリティであり、迫害を受けていた社会状況の中で書かれた文書である。それが現代にそのまま適用できない場合が多々あることは、当然考慮しなければならない。しかし、いま正座でもして改めて読み返すことが求められて然るべきだと感じる。教会は、自分たちが自画自賛のように勝手に思い描くイメージで、自分たちがどう見られているかにすら、気づこうとしなかったとは思えないだろうか。
ピアノを叩き、その名から消えたものの「フォルテ」をも演奏するためには、たおやかな指ではなく、力強く鍛えられた指が必要であるという。聖書の言葉で鍛えられていくことを、あまりにも教会は蔑ろにしてこなかったか、蔑ろにしていないか、とくと自問しようではないか。そのためには、語られる説教の言葉が、幼児向けの教会学校程度の内容でないかどうか、確かな学びの上に、神との対話を経て組み立てられたものであるかどうか、間違った言葉遣いが居並ぶようなものとなっていないか、教会員が霊的に確かな目と耳をもって、吟味しなければならないであろう。そうしたものしか語れない説教者は、神学校に行っていようが、親が有名な牧師であろうが、礼拝で語る資格はない。教会の一員であることや、執事を務めることについては何も否む必要はないが、教会と、教会員に命を注ぐ説教を担うようなことをさせていたら、じきに教会は、死を迎えることになるだろう。教会には、そのための「きよさ」が必要なのである。神の言葉の「きよさ」である。

