【メッセージ】新しく生きることができる
2022年4月17日 【復活節】
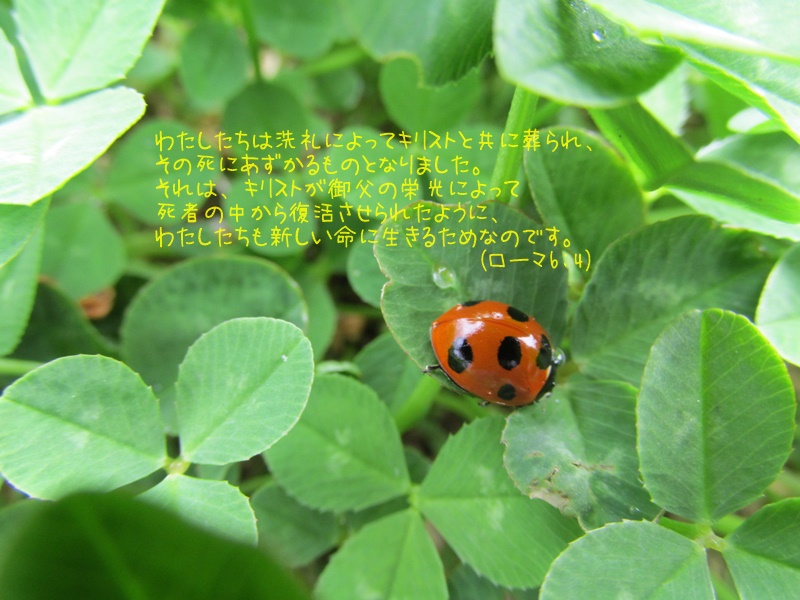
(ローマ6:4)
わたしたちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死にあずかるものとなりました。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、わたしたちも新しい命に生きるためなのです。(ローマ6:4)
◆魅力のないキリスト教
復活祭の日に、のっけからこれでは引かれるかもしれませんが、『遺体』という本を読みました。東日本大震災で、遺体を収容する担当となった方々の証言を並べて、小説のような形にした本です。プロではない、ただの市民が、遺体と遺族との対面の現場で世話をする。普通の歯科医が、身元の照合を行う。そんなことが綴られていくのは、読むだけでも息苦しくなってきます。でも、そうした現場のことは、報道では伝わってきません。被災された方々が、どんな痛みを負っているかを、想像の中ではありますが、私たちはもっと知ろうとしてよいと思います。
お寺の僧侶も登場します。人々が、いかに僧侶を慕っているか、頼っているかが伝わります。仏教会の人に著者が取材をしているので、取り上げられるのは当然かもしれませんが、それにしても、キリスト教会のことが少しもその本には出てきません。教会関係も現場で働いていたことは確実なのですが、ついにこの本では触れられませんでした。
熊本地震のときにも、キリスト教会が現地で、力仕事やメンタルな援助など、活動をしました。ささやかながら、何度か私も足を運びました。それは、宗教的なことを伝えるという目的は封印したものでした。それでよかったとは思いますが、心の中で願っていた、福音の種蒔きということは、果たして少しはできたのかどうか、それさえ怪しいだろうとは思います。ですから東北でも、伝道目的で教会関係者が何かをしていたのではないだろうと推測します。一部、そういうのがあって批判を受けたことはあるかもしれませんが。
僧侶は登場するが、牧師は登場しない、この『遺体』という本から、想像ではありますが、考えてみます。被災者の心の支えになったのは、仏教的な弔いであり、読経でした。目も当てづらいような死の連続の光景の中に、キリスト教や聖書の教えが、少しでも人の心を支えるようなことは、ありえなかったのです。かの地に教会が少なかった云々の背景があるかもしれませんが、聖書は傷ついた人々の心を助けることがなかったと言ってよい状態でした。
でも、新約聖書の中には、はっきりと「復活」があります。教会が十字架を掲げ、キリストの十字架を中心に置いたとしても、教会は同時にその十字架からのキリストの復活を、信仰の中心に置いているはずです。死と復活は、キリスト教の根幹ではなかったのでしょうか。
それとも、いまの時代、教会は「天国」を語ってはいないのでしょうか。「十字架の死に与る」とか、使徒信条にもあるような「からだのよみがえり」とかいうものは、もう教会は伝えようとしていないのでしょうか。あるいはそもそも、キリスト教会と名のるものが、復活ということを、信じてなどいないのでしょうか。
◆復活ということ
そうじゃない。今日はこの場で、「復活を信じる」ということを中心に、しばらく皆さまと共に過ごしていきたいと考えています。おや、その時点でもう耳と心をふさいで、この場から去ろうとしている方がいるのでしょうか。すみませんが、もう少しだけお付き合い願えないでしょうか。
「復活を信じる」といま申しましたが、その「信じる」という言葉について、日本人がもつイメージは、聖書のいうものと実は全く違うというケースがあるような気がします。
私にも身に覚えがありますが、子ども時代から、「神を信じる?」という質問の答えは、「いると思う」「いないと思う」のどちらかでした。神は存在するか・しないのか、それを訊くための質問が、神を信じますか、というものでした。もちろん、その意味の疑問文があってもよいのですが、古来そうした意味での質問は、なかったのではないでしょうか。つまり神の存在・非存在という観点は、近代的な関心から起こった思考であって、たとえば聖書を記した人にとっては、神が存在するのは、言うまでもなく当たり前すぎることだったはずです。「神の存在証明」そのものは古代からありますが、けちをつける者がいたときの対処のようでもあります。古代ギリシアの哲学者ソクラテスがどんなに「神々」というものに基づいて哲学をしていたかは、プラトンの著作を開くと一目瞭然です。
へたをすると、現代のクリスチャンたちの中にも、神を信じるかということについて、存在するんだよ、というところで論じ終わったような気になっている人がいそうです。そして自分の中でも、神は存在するんだ、で自分には信仰がある、と納得している可能性が、なきにしもあらずではないでしょうか。
「信じる」とは何でしょうか。ギリシア語でもそうですが、日本語の「信」もまた、「信頼する」ということです。「あなたを信じるよ」という言葉が、「あなたは存在すると思っているよ」という意味で使われるシチュエーションは、まず考えられません。ひとの運転する車に同乗するときには、そのドライバーを信頼しているわけです。ドアを開けて一歩踏み出すのは、ドアの向こうが崖になっていないと信じているわけです。今日も会社に行くのは、会社が間もなく給料をくれると信じているわけです。私たちは、日々刻々と、何かを信頼して生活しています。信頼しないことには、片時も生活ができないはずです。
今日は、復活祭です。「あなたは復活を信じますか」という問いかけが、ここに関わってきます。それは、「復活が存在するのか」というレベルでしばしば語られます。けれども、今日ここでは、それは致しません。存在することを議論して、もし仮に証明したとしても、「だからどうした」という結末になる場合があることが明らかだからです。では、私たちは今日、どのように「復活」ということについて、受け止めていこうとしているのでしょうか。
◆復活を信じる
まず、聖書にある復活の記事に心を向けることにします。ところが、復活を信じられないという人が世の中にはいます。これは、復活の存在を認めることができない、という意味です。無理もありません。科学的な知見がいまとは違うタイプの当時の人々も、信じられないという人が多かったのですから、科学的知識に基づく考え方に支配されている現代の人間にとり、復活を信じるというのは、ハードルの高いことに違いありません。
そればかりか、現代において聖書を研究する人々の中にも、復活を認めることはできない、というようなことを言う人がいます。聖書というものを、信仰の書としてではなく、文献として読むことが学問的だと言われるようになったこの100年の歴史の中で、そうした傾向はさらに強まったようにも見受けられます。
確かに、聖書が人間的に書かれたというところから理解することで、復活の記事にはいろいろと種明かしはこうだ、というような説明がなされることは可能でしょう。けれども、それこそが真実だ、ということを決めるかどうかが、その人の受け取り方次第であるという構造は、昔も今も変わりません。理性では信じられないが、建前としては信じる、というような態度で自分の中に折り合いをつけている「クリスチャン」が、いるかもしれません。
復活ということは、「永遠の命」という新約聖書が特によく掲げるものとつながっていきます。ラザロの復活は、そのものが永遠の命と等しいとは言い難いものでした。ではキリストの復活はどうでしょう。永遠の命と呼ぶに相応しいものなのかもしれません。そうなると、キリストの出来事を信頼し、キリストに従う私たちキリスト者の復活はどうなるのでしょうか。
死者が復活するはずがない。だから、いま信じることで永遠性が心に満ちることがあれば、それを永遠の命と言うのだ。こんな説明を持ち出す人もいます。人が死んでも、神はその人のことを覚えているから、永遠なる神の中であなたは永遠の命を得ていることになるのだ。そんな説明も、あるかもしれません。そもそも「永遠の」命というその言葉は、時間的に無限であることを意味する言葉ではないのだから、不老不死のようなイメージをもつことは誤りなのだ、という、なかなか説得力のある説明もあるでしょうか。
その人がどのように捉えようと、それを間違っていると突きつけることは難しいかと思います。しかし、そうした人の自由な捉え方こそが正しい、と弱気になる必要はありません。新約聖書から私たちは聞いてみたいのです。パウロや福音書が、いまのような説明をしているなどということはありません。聖書が福音、つまり良い知らせを伝えているということを、そのまま受け容れることができないならば、先ほどのような理屈による説明を、唯一の説明であるかのように信頼してしまうかもしれません。そうでなくとも、何かしら自分の考えた筋道のほうを信頼し、自分が納得できる形で聖書が説明できたのだと満足する場合もあるでしょう。
また、「復活」という思想は、旧約聖書には直接見出されないものである、ということも、新約聖書の「復活」に疑問をぶつける人々の論拠となることがあります。イスラエル民族の復興を象徴的に表している、エゼキエル書の枯れた骨のよみがえりは、ここで求めている「復活」に重ねるのは苦しい気がします。旧約聖書続編という、カトリックが取り入れている聖典、つまり聖書の中に、たとえば次のような箇所があります。
12:43 次いで、各人から金を集め、その額、銀二千ドラクメを贖罪の献げ物のためにエルサレムへ送った。それは死者の復活に思いを巡らす彼の、実に立派で高尚な行いであった。
12:44 もし彼が、戦死者の復活することを期待していなかったなら、死者のために祈るということは、余計なことであり、愚かしい行為であったろう。
マカバイ書二は、旧約聖書と新約聖書の中間期のことを描いた文書です。しかし、やはり聖書全体からすれば、例外的なものにも見えます。ユダの人々は、ローマの支配の中で、復活への希望が、次第に広がっていったというようにいま見ることも可能でしょう。
◆復活したイエスを信頼する
そこへ、イエスが現れて,復活への道が整えられました。でもそれは、きっと弟子たちにとっても、そんなに大きな目標と見られていたようには考えられません。あるとき、弟子の筆頭のペトロが、イエスに「だめですよ、そんなことを言っちゃ」と抗議する場面があります。
それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっている、と弟子たちに教え始められた。しかも、そのことをはっきりとお話しになった。すると、ペトロはイエスをわきへお連れして、いさめ始めた。(マルコ8:31-32)
「殺される」の言葉は聞こえても、「復活する」という言葉は、ペトロには聞こえていなかったのです。イエスの復活という筋書きは、このように意外なもの、思いも寄らないものであったのでしょう。この世にメシアの統率する王国が来るという、幻想めいたものはかなり本気に夢見ていたのだとしても、死んで復活するという事態は、想定外だったのではないでしょうか。
イエスは、この新たな救いの道を、それも旧約聖書がちゃんと言及していた、メシアたる救い主の姿と共に、もたらした。そのように捉えることもできようかと思います。
この道を、私たちは受け継いでいます。キリストに従う者たち、そしてその人々が共同体を築いて伝えてきたものを、いまもこうして同じように受け止め、同じように信じています。その教会の発端は、貧しい人々でした。生活も貧しかったけれども、漁師など、当時決して知的階級ではなかった人たちだったのです。福音書のギリシア語も、必ずしも流暢ではなく、たどたどしいようだ、と言う研究者がいます。おまけに、イエスが言った言葉が収めてある福音書のその言葉は、謎めいているばかりで、分かりにくいことだらけです。どう読んでも、なんだかよく分からないということがあります。どうしたらその意味が分かるのでしょうか。そのためには、聖書の記事を、自分の問題として受け止めることが必要であること、自分が聖書に描かれている事柄の当事者であるものとして読むこと、それが必要である、と私は常に強調しています。
だから、ここでいう「復活」を証明しろなどと言われても困ります。また、仮に証明できたとしたら、それはもはや命あるつながりではなくなるような気がします。それだと、いわば決められたプログラムに従って動く、ただの機械です。あなたの操縦する通りにロボットが動いたとしたとき、そこに命ある関係が存在するでしょうか。1+1が2ですよということを、私たちが生きる中でずっと見つめ続けて、何が楽しいでしょうか。
復活といったら、復活しかありません。ラザロが生き返る場面でイエスが、「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる」(ヨハネ11:25)と言った、その言葉で十分です。このイエスが、宣言通りに、復活したのだと聖書が証言しています。それでまずは良いではありませんか。復活したイエスをもとに、スタートしましょう。
やっと始められます。これからスタートすべきだったのです。私たちは、そのようなイエスを信頼しているでしょうか。イエスが弟子たちに語ったとして伝えられている言葉、それを信用しているでしょうか。どうか、福音書をこれからもまた読み直して戴きたいのです。そして、その一つひとつの記事とイエスの言葉を、自分が信用しているかどうか、もう一度確かめて戴きたいのです。
そもそも復活があるのかないのか、存在するのか。そうした問題ではないのです。復活は信じられるか、あなたは信じるか、そこなのです。復活のイエスに、自分の希望を、人生を預ける勇気があるでしょうか。決断できるでしょうか。それがイエスを信頼するということなのです。その信頼しますという告白によってこそ、私たちは本当に「復活を祝う」ということが可能になるのです。復活を祝うというそれは、信頼しますと告白できた自分を祝うことでもあるのです。
ああ、聞いていられなくなった方もいますね。立ち去る前に、どうかもう少し猶予をください。昔、そのユダヤの地で、最高の頭脳の持ち主でありエリートであった一人の人間が、命を懸けてこのイエスの復活を叫び続けていたということを取り上げます。ほんの少し、手紙の中のたった一節だけを取り上げますから、辛抱してくださいませんでしょうか。
◆死と復活との対比
6:4 わたしたちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死にあずかるものとなりました。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、わたしたちも新しい命に生きるためなのです。
これだけです。これだけを窓口にして、希望の光が射し込む道を、陽の当たる道を、ご紹介しようと願っています。但し、もし光が少し見えましたなら、この箇所の前後にまで、目を通してみることをお薦めします。すると、さらに光が増すと思っていますから。
ここには、「死」と「復活」が幾度も対比されています。対比が非常に明確ですので、いっそのこと「表」形式に整理したら、比較がしやすいだろうと思います。が、お話しするのはどうしても時間順でお知らせしなければなりませんから、方法を考えましょう。学問的な叙述ではありませんから、ここから私たちが受け止めたいことを手早くまとめてみようかと思います。そのためには、この後に続くパウロの言葉をやはり引用したほうが、眺めやすいので、少し長くなりますがお読み致します。
6:5 もし、わたしたちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。
6:6 わたしたちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。
6:7 死んだ者は、罪から解放されています。
6:8 わたしたちは、キリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。
6:9 そして、死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがない、と知っています。死は、もはやキリストを支配しません。
6:10 キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは、神に対して生きておられるのです。
6:11 このように、あなたがたも自分は罪に対して死んでいるが、キリスト・イエスに結ばれて、神に対して生きているのだと考えなさい。
私たちが洗礼を受けるということは、キリストと共に死ぬということである。それは、キリストの復活と共に生きることをも意味するものである。なぜなら、罪の支配を受けたものが死に、もはや罪に支配されないようになるからである。――これが前半です。
後半のためには、少し注意しておく必要があります。10節と11節に、「罪に対して」「紙に対して」がきれいに対比されています。この「対して」は原語にはない言葉です。格変化をしているだけですから、意味をぼかした表現として、おおまかにいうと「罪に」「神に」と表現しているわけです。日本語の「に」が一番近いと思います。「に対して」の意味もありますし、「によって」や「のために」や「と共に」あるいは「に関して」のような受け取り方も可能な形だということです。その意味の理解は、読む一人ひとりが考えればよいのではないかと思います。
キリストは一度きりだが罪に死んだ。私たちも罪に死んでいる。しかしキリストは神に生きている。だから私たちも神に生きている。
この「においては」は、新共同訳では、カトリックの味の濃い独特の「に結ばれて」となっていますから注意が必要です。英語で言えば「in」ですので、「キリストの中で」「キリストにあって」「キリストの内に」という、ややぼかした意味合いで、これも読んでおくべきだろうと思います。
キリストの復活は、しばしば「起こされた」のような言葉で表現されます。聖書で受動態の多くは、隠れたる神によってなされたことを意味していますから、父なる神がキリストを復活させた、という図式がここに成り立ちます。キリストが死に、神が復活させたように、私たちもまた、罪に死ねば、神が復活させてくださるのだ、とパウロは叫んでいることになります。
◆間をつなぐもの
死と復活をつなぐ主体は、父なる神であることが分かりました。でも、キリストをそのようにした神のことは聞いていますが、私たちの場合はどこまで確証のあることだと言えるでしょうか。私たちは、がむしゃらに信じなければならないのでしょうか。まるで私たちの信じ方次第でどうにかなるかのように。
思えば哲学の世界でも、このような2つの間をつなぐ関係というものが、常々議論に上がってきました。物事を2つの原理で区別することは、人間にとり難しいことではありません。善と悪、神と人、支配と抑圧、対比させること自体は、理解しやすくさせるために必要であり、分かりやすいと思うのですが、それらをつなぐものは何かという点について、意見が分かれるのです。
心身二元論のように、近代哲学は明確な二元論を以て、世界を説明しようとしました。デカルトは、精神と身体をつなぐものは脳の中の松果腺という場所だと断言しましたが、苦し紛れのようでもありました。カントは感性と悟性をつなぐために、理性の能力としてはまた話を複雑にすることになってもなお、構想力というものを持ち出さなければなりませんでした。認識と理念との間には、自由の概念が道徳律という形で現れることでつながる橋が架けられました。
ここでも死と復活、死と命との連続性を保証するものは、先ほど注意を促した「キリストにあって」のほかには、どうやら考えられないようです。罪に死ぬためには、罪を罪として認識させる基準がなければならないでしょう。人間が自ら法を勝手につくるようになったら、自分を守るために法を自由につくりかえて、自分を罪から逃がすようになります。イスラエルの社会では、「律法」という形での基準が、どうしても必要でした。しかし、それは違反者に死をもたらすためです。それを復活の命へ連れて行くために、神はイエス・キリストをこの世に与えたのだ、というのがキリスト教のエッセンスなのです。
それは、体験した者には分かります。死を恐れ行き詰まっていた私が、こんなに胸を張って空を見上げて歩いているのです。これは、私の中では奇蹟も奇蹟、天地がひっくり返るほどのすごい出来事なのです。
他方、あらゆる悲観主義の理論をも、私は一読して分かります。私もかつてそのように考えていたからです。反出生主義も、胸が痛むほど切実に感じます。しかしその絶望の壁は、イエス・キリストに出会ったときに、壊すことができたのです。
◆命を阻害する罠
聖書の記事は曖昧でもあるし、どうしても矛盾にしか見えないような箇所も確かにあると思います。それを、なんやかんやと理屈をこねて、正しい論理にもってこようとする涙ぐましい努力もありますが、私はそのようにもしないつもりです。むしろ、聖書を冷徹に研究する方々のことをたいへん尊敬しています。聖書について気づくべきいろいろなことを教えてくれるからです。だから、聖書の復活の記事を学問的に批判することは、あってはならないとも言いません。ただ、聖書をまな板の上の鯉のように扱うことに夢中になるとき、自分は果たして何者なのかということが、しばしば忘れ去られてしまうことは、気をつけないといけないと考えています。
カントにしても、理性の謎を解き明かすのはよかったのですが、その自分はどこにいるのかということについて、真摯に考えた様子はないようです。あくまでも人間とはこうだ、と言い放つばかりで、理性を批判するその自身の理性そのものは、それとは別の世界にあるかのようでした。それでドイツ観念論は、なんとかその自身と世界との関係を、もっと生き生きと説明しようともがいたのですが、そう簡単に世界の構造説明はすべての人を説得するようには解決されることがありませんでした。
聖書を切り刻み、謎解きに夢中になるとき、その人はどこにいるのか。自分は神とどのような関係にあるのか。さらに言えば、自分にとり罪とは何か。赦しとは何か。そして自分と神との関係の中で、復活とは何か、そんなことがいつの間にか意識されなくなってしまいがちです。どこまでも自分の解決策こそが正しいという前提で、神をすら自分の支配下に置く「ずらし」に陥ってしまう危険性が多々あり、またそうなっても気づかないという罠が確かにあるように見受けられます。
いや、学者は学者として、聖書の研究に貢献しているから、まだ役に立っているのだとは言えましょうか。役に立たないのは、口八丁手八丁で尤もらしいことを言うことはできるのですが、自身神とのつながりや確信を全くもっていないで、説教ごっこをするような輩です。これでは命を語ることができません。命をもたないからです。その人が信徒として教会に集っていることについては何も問題とはしませんが、さも聖書を知っており、神と人とをつなぎますというような嘘を、体裁だけで並べることは、悪です。教会から命を奪うからです。
◆胸に懐きたいこと
そこで、証明するとか、論破するとか、そういうのではなしに、あなたはまず、あなたの心で聖書に向き合いましょう。聖書が復活を宣言しているのであれば、「アーメン、その通り」と応じればよいのです。理屈で説明してやろうなどと思う必要はありません。もし証明というものがあるのだったら、科学のお勉強をしているようなものです。
もし証明があるのだとしたら、いつか来る「主の日」に全貌が明らかにされることになるでしょう。イエス・キリストを仰ぎ続けた魂が、歓喜の声を挙げる日です。
復活は、やはり復活です。復活を信じたらいま元気が出ましたとか、この瞬間が永遠であるように思えましたとかいうことで終わるものではありません。もちろん、元気になるのはいいし、いまこの瞬間に永遠を感じるのは、すばらしいことです。実際、この復活の希望を抱きしめる人は、おどおどしないでしょう。くよくよしないでしょう。うつむいて沈まないでしょぅし、倒れても起き上がることができることでしょう。
だから幾度でも言いたい。復活は復活であり、それだけでよいのだ、と。うつむいて、へたっているキリスト者よ。神の言葉は、決してそのままで居続けることを許さないのだ、と。今日はキリストの復活を覚える礼拝です。古代の文書である聖書が、現代の、時も場所も異なり、文化も違う私たちの関心の気に入るように書かれているはずがありません。私たちには謎、隠されていることばかりでしょう。だから自分の甲羅に似せて穴を掘る蟹のようなことをしないで、私たちはこの良いニュースに浸ろうではありませんか。それだけでいい。心配もすべて委ねればいい。それが信じるということなのだと考えましょう。
新しい人生に生きる。命を生きる。生きていればよい。命、人生、生活などと訳すライフが、断然明るくなります。それは、どこかの教祖が思いつきで言ったようなことではなく、空想の救い手を考案したたとえ話のようなものに基づくのでもありません。二千年という検証フィルターを経て、しかも実際にこの地上を歩んだイエスという方に根拠をもつような形で、このニュースは私たちにこうして届けられているということ、それだけでもう摂理だという信頼を寄せて、よいではありませんか。
だから、理屈や人の意見を気にする必要はありません。あなたが今日、復活の希望のニュースを聞いたのです。だったら、そこに心を開いたらよいのです。その声を聞いたらよいし、力を受けたらよい。顔を上げることができ、立ち上がることができ、歩き始めることができたら、それでよいではありませんか。光を感じたなら、その光のほうに、一歩歩めたらよいではありませんか。
それが、本当の復活への小さな一歩となります。小さな一歩ですが、大きな一歩です。あなたは今日から、新しく生きることができるのです。

