工作ができない
2022年1月16日
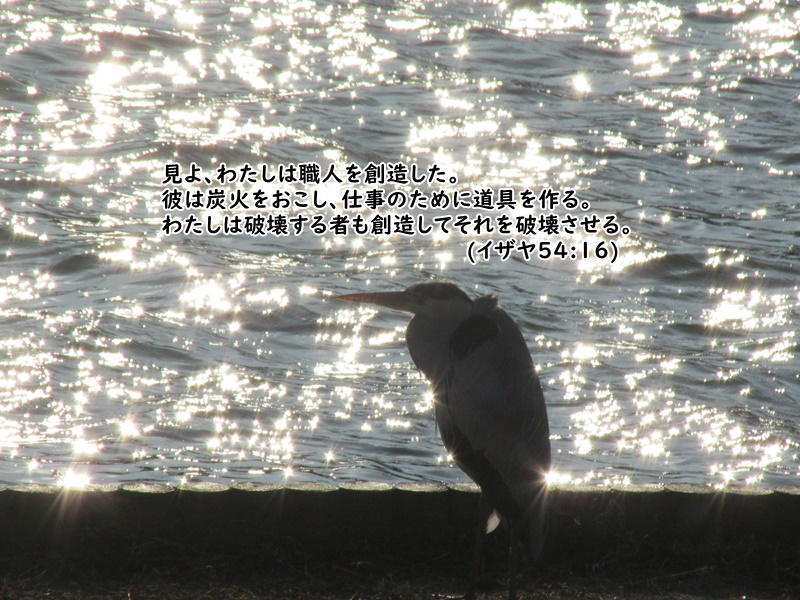
工作――するのだろうか、今時の小学生。
塾で、理科工作をすることがあるのだが、工作がてんでできない。成績上位の子も、どうしてよいか分からないといった事態がしばしばある。十人に一人かそこら、なかなかうまい子がいる。必ずしも学習成績との相関関係はないように見える。
昔と比較することは客観的にはできないが、恐らくこれほどではなかった。だからこそ、小学生にこれはできるだろうということで、教務がその工作を企画しているのである。
難しい操作を要するものができないと言っているのではない。まず台紙から、ミシン目に沿って切り取るところから、かなり危なっかしい。点線が折り目だという常識を知らないものだから、点線まではさみで切り落とそうとする。こちらも慣れたから、予め大声でそれは切らないのだと説明を繰り返すが、いざその場面になると、切ってよいかと質問が飛んでくる。
山折り谷折りが分からない。どちら側に折っておけば、組み立てるときに差し込めるか、全く考えられていない様子。作り方はもちろん目の前に図解してあるが、それと目の前の物体とがどうしても結びつかない。先にどちらを通しておけば、次に困らないかということを考えることができないので、後からまた全部外して組み立て直すこともよくある。
揚げ足を取るつもりはない。要するに、工作をしたことがないのである。
手を使い、折り曲げ、切り抜いて、貼り付けるという作業を日常的に経験していれば、恐らく自然と、こうすれば次にこうなり、目的のものを作るのにこちらが先になるのだ、ということは分かるものだ。ところが、手先の器用さにより、折り目が歪んだり、糊がはみ出たりするというのとは、レベルが違う。殆ど呆然と立ち尽くすようにしており、「どうするの」という質問しか出てこないのである。たまにそうした子がいるというふうではない。大多数が、そうなのである。
工作はいい。出来上がりを想定しつつ、その目的のために、いまの仕事がどういう過程となるのかを考えながら営む。仕上がりを見越して、それ故にこの部品はこちらに曲げるのだなどと考えて組み立てるだろう。
一から型紙を作れというのではない。すでに型紙もミシン目もついている。手順も十分分かりやすく図解されている。それでも、説明と自分の手で触れているものとの関係が形成されないのである。
遊びの中に、工作はおろか、手先を必要とするものがなくなってきているように見える。コンピュータゲームの指先の連打とそれはまた違う。あやとりやリリアンなどは、男の子もそれなりに喜んで参加していた時代があった。ゴム跳びをこしらえるというところから始まって遊んでいたし、草花で飾りや笛をつくったり角力をしたりということも日常的だった。
幼児期から、男の子向けの雑誌だったら、合体ロボや変身アイテムの工作を、テレビ雑誌などの付録で作っていた。あるいは親が作ってくれるのを横で見て、手伝っていた。女の子向けの雑誌だったら、着せ替え人形も、最初紙のものを、肩のところに小さな出っ張りがあるのを折り曲げていたし、お出かけポーチを組み立てるというあたりも、あったものだ。
それはずいぶんともう昔の話をしていることになるかもしれないが、そう遠くない時にもそうした景色はあった。
創意工夫という言葉も、全く別の次元で展開する場をもつようになった。料理ひとつとっても、出汁からつくるよりは、出来合いのものが中心になってきている。信じられないかもしれないが、私は料理の手伝いで、鰹節削り器でごりごりやっていたのだ。
妙に懐かしんでも仕方がない。ただ、自分の手で実感をもって組み立てるという営みは、物事の手順を考える上でも必要であるし、なにより五感を伴いながらモノに出会うという点でも、かけがえのないものだと私は考える。それは命あるものに対してもそうだった。虫や蛙に触れてこそ、命たるものを、理屈抜きで感覚していた。ずいぶんな生き物を殺したけれども、そのために、命について教えられたのは事実である。
虫も蛙も触れたことがなく、レンゲソウもツユクサも知らないままに、環境問題や生命倫理を議論する世代が、やがて現れることになる。
それではいけない、と、大人がまた自然体験教室を開くなどするかもしれないが、それがまた、商品とコースの押しつけに過ぎないのであり、本末転倒も甚だしいこととなる。
私もまた、そうした自然観としては、上の世代から見れば実に頼りない子どもたちのなれの果てである。だがその私が、目をつぶりたくなるような事態に遭遇しているのも事実である。もはやいまの親世代が、このルーチンに入っている。おセンチに淋しいなどと言っているのではない。論理能力の劣化や、自分本位の行動が起こす事件、命の軽視などが、偶々特別なケースである段階から、それが常識となってしまう世界になってしまうということさえ、単なる懸念ではなくなっているのかもしれない、そう感じているのである。

