【メッセージ】生きる
2021年8月29日
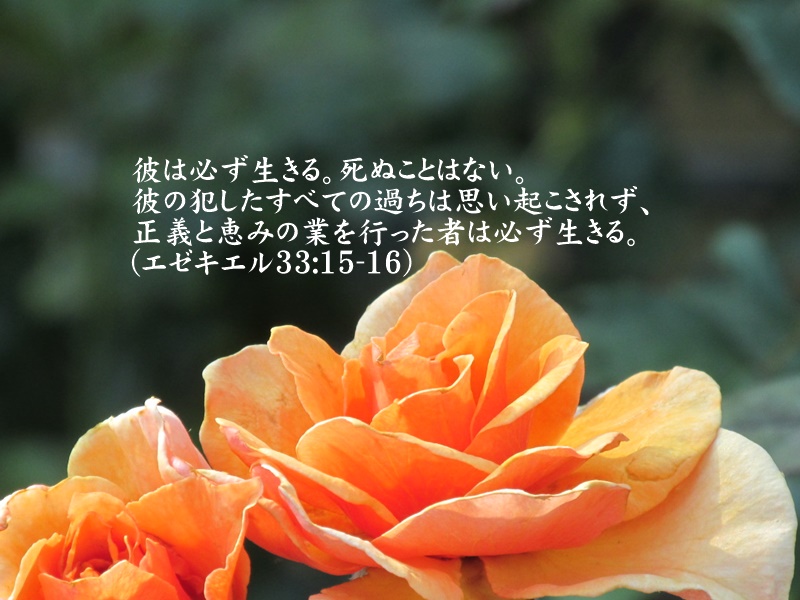
(エゼキエル33:10-20)
彼は必ず生きる。死ぬことはない。彼の犯したすべての過ちは思い起こされず、正義と恵みの業を行った者は必ず生きる。(エゼキエル33:15-16)
関わった方には、心に重くのしかかることに触れます。辛く思われた方はご退席くださって差し支えありません。それは「自死」のことです。
自ら命を絶つ。どんなにか苦しかっただろうと思います。生きていても希望がない、あるいは逃げ場のない情況に追い詰められている、そんな人が、いまこの瞬間にもたくさんいると思います。かつてそう思った人はもっといるでしょう。私も例外ではありません。
デュルケームの『自殺論』を読みましたが、19世紀末のヨーロッパでの様子を、社会学的なデータで取り扱った、この問題についての古典です。そこでは、個人的な原因に基づくというよりも、社会の中に原因を問うという、優れた観点が提示されていました。しかし、何かしらの原因でそうなったと軽々しく言葉にすることもできないだろうと思いますし、してはならないとも思います。
どんな自死も、当人はもちろん残された人にはたまらないことでしょうが、特にまた、若い人が命を絶つということには、親世代の私には痛みが大きく加わります。精神的な病と現在判断されるような中では、社会的な背景があるかもしれませんが、一定の個人的な問題によって、そうなることもあるわけです。そこで、これまで知られたその病、あるいは素人には診断がつかなくても、こうした兆候があるときには注意しなければならないとか、このような対応はよくないとか、ある程度の知識は共有しておくことが望ましいとも思えます。非常に分かりやすく書かれたものとして、『ねじ子が精神疾患に出会ったときに考えていることをまとめてみた』という本はお薦めします。イラスト主体で、森皆ねじ子という看護職現場に指導的な役割を果たしている漫画家が出しているもので、これもいわばプロ用の本です。しかし、素人として病気に対する判断は軽々しくしてはならないが、精神疾患に対する関心をもつ一般の人の目にも触れて然るべき内容になっていると思うのです。
さて、今回もエゼキエル書を開きましたが、ここでは「生きよ」としきりに呼びかけています。そこで、どうか生きてほしい、という思いを中心に、お話しできたらと願っています。そのために、ここまで辛いことに触れてきたこと、傷をもつ方々には特に、お詫びいたします。
実は開いたこの箇所は、その直前の部分が非常に有名でありまして、それについては全く触れる必要はないのであり、別の考えが述べられているのですが、あまりに有名なので、やはり概観だけはしておいて損はないと思い、簡単に触れることにします。
それは、警告をする者、おそらくは預言者としての自覚のようなものを教えているものだろうとは思うのですが、悪を知る者はそれに警告を与えなければならない、とするものでした。
その国に見張りがいる。敵がやってくるのを見た。見張りは、角笛を鳴らしてこのことを警告として知らせる。さあ、これを聞いた者がいた。しかし、もしこの者が警告を聞かず敵に殺されても、自己責任である。他方、見張りが敵がくるのを知っていたのに、角笛の警告を鳴らさなかったとしたらどうか。敵に殺された者が一人でもいたら、見張りの責任である。このように主は言ったというのです。そして主はエゼキエルに、あなたはその見張りだと諭します。だからこの警告を残らず民に知らせよ、というわけです。
私たちもまた神の言葉を預かる立場にある者として、この聖書の警告を、世に知らさなければなりません。しかしいまはこの背景があって、今日お開きした箇所で、エゼキエルはイスラエルの人々に語っているということを理解しておきたいと思います。これまで悪人とされていた人の中にも、エゼキエルを通して語られた警告を聞き入れて、正義を行うようになれば、その元悪人は生きることになるとするのです。でも、これまでいくら正しい人だと言われていたような人でも、このエゼキエルの警告に背くようなことをするならば、その人は救われないのだ、ともいいます。
神の言葉に逆らうならば生きられない。神の言葉を受け容れるならば生きる。ヨナの警告に悔い改めたニネベが救われたことを思い出します。また、後にファリサイ派や律法学者が、正しすぎるくらい正しいのに、イエスにより糾弾されたことをも思い出します。
それにしても、ここには今の私たちから見ると、どうしてもこのように考える可能性が強くなっていないでしょうか。救われるかどうかには、「自己責任」が伴うのだ、と。
「自己責任」。どうにも嫌な言葉です。社会問題において、時々この言葉が挙がってきます。事件の解釈や法的な理解において差し支えがあるかもしれませんので、具体的な事件をここで取り上げはしないことにしますが、危険な地域に立ち入った者が危険に陥ったのは自己責任であるなどとも言われたことがありましたし、その救出にかかった費用を支払えなどという圧力もよくあることです。欲がらみで投資を続けたが、詐欺まがいのために全財産を失っても、自己責任だなどとも言われました。家を失った人も、それは自己責任だから助ける必要がない、などとする考えもあります。
失敗したり、困窮に陥ったりしても、それは「自己責任」だというふうに片付けられるのが、世の常であったら、なんともこの世は世知辛いものです。新約聖書に描かれた教会では、そんなときに助け合ったのではないか、と期待したいような書き方がされていますが、本当のところ、どうだったのでしょうか。いまの教会を見ていても、教会員が個人で困窮しても、教会が助けの手を伸ばすということは、殆どないような気がしています。教会自体も予算がないし、奉仕に忙しくて、誰かを助けるような余裕がないことからしても、なんだか教会の内部にまで「自己責任」という原理が、居座っていないか、考えさせられます。この原理は、上位にある立場にあるほうが、下位にある立場の人の困難に手を貸さないことを正当化する原理であって、上の立場を信頼して助けを求めるのはお門違いだよ、という門前払いの理屈ではないか、と私は睨んでいますが、さて、どうでしょうか。
「自己責任」というのは、その人の失敗が、その人が自由に選んで行った場合に突きつけることができる言葉です。誰かの言いなりになって行動しただけのときに、その行動した人に責任を帰せるのは、殺人などよほどの時ではないでしょうか。行為自体蔑ろにできない場合でも、少なくとも、刑は軽くなるでしょう。
自由にその行為を選ぶ。私たち現代社会は、これを重要な原則として立てられてきています。人は基本的人権を守られ、思想や行動の自由を権利として与えられました。子は親の家業を継ぐのが当然だとされていた時代には、子には職業選択の自由はありませんでした。その代わり、思い悩まずに済むという事実もあったと思われます。職業選択の自由があれば、将来何の仕事をしようかと思い悩みます。そのとき、うまくそのようにできなかったとき、責任は本人にあるものと見なされます。自分が悪いのです。
近代において、自由は、人を解放したと考えられました。輝かしい自由の宣言がありましたし、実存主義あたりになると、自由を謳歌するのが当然というふうにもなりました。しかし、その自由の「不自由さ」も、近代においてすでに見抜かれていました。つまり、自由であることが、不安を引き起こし、人間にめまいを起こさせるというのです。
ああもう、こんなことで悩むのだったら、誰か決めてくれよ。こんなふうに叫んだことは、ありませんか。自分で決めるというのは、なんとも嫌なものだ、そのように感じたことはありませんか。責任を自分が負うということに対する恐れがあるからかもしれません。それ以前に、とにかく自由に選択するということが面倒だということがあるからかもしれません。自分で決めないほうが、楽なのです。
この姿勢は、私たちの社会で、「投票」のときに現れることがあります。誰に投票してよいか分からない、だから投票に行かない。自分で何かを決めることには、責任が伴うような気がして、一歩退いてしまうというのは、誰しも経験があることだろうと思います。
そしてこの「誰か決めてくれよ」の精神が、実は事を決めてしまう、という構造がこの社会にはあります。いまの例で言うと、投票していないのだから、自分は何の影響も与えていない、というような錯覚に陥りますが、それは間違っています。投票しないということで、一定の役割を果たしているのであって、傍観者で無関係というわけにはいかないのです。
同じ事は、戦時中、反対の声を挙げない、あるいは挙げられないからこそ、無言の者は戦争に加担していたことになったことへの反省として挙げられることがあります。しかし、当時その情況の中では、反対ができなかった、というのも確かです。「仕方がない」と振り返るしかないかもしれないし、そうする人を責めることはできませんけれども、その波の一部に自らなっていったことは、当人は自らも気づかないままであることがしばしばです。
しかし、気づくか気づかないかは別にして、今月半ばにNHKのドラマ「しかたなかったと言うてはいかんのです」が、ちょうどこれに関する問題を視聴者に投げかけていました。1945年5月から6月にかけておこなわれた「九大生体解剖事件」を描いたものでした。その題に関わる重要な場面で、重く語られた言葉が忘れられません。「何もしなかった罪というものもあるんじゃないだろうか」
同じ第二次世界大戦では、何百万人ものユダヤ人が、ナチスドイツの手で殺されました。ユダヤ人を強制収容所へ移送するために指導的役割を果たした、アドルフ・アイヒマンの裁判を傍聴して、ハンナ・アーレントが感じ取ったものは、あまりにも有名です。
逃走と潜伏を続けていたアイヒマンが、1960年、アルゼンチンにてついに拘束されました。翌年、アイヒマンはエルサレムで裁判の席に着きました。世界は、どんな悪人だろうと見守ります。しかしユダヤ人のアーレントは、その死刑執行までを見届けた末に著作の中で、この男の中に「無思想性」を見出し、「凡庸」に過ぎず、その故にこれを「陳腐」だと表現しました。世界はアーレントに怒ります。そんなはずはない。ユダヤ人を何百万人も殺したことに関わったものが、どこにでもいるありふれた人間だなどと、ふざけている。まっとうな反論も多かったのですが、アーレントは、この言及が目的ではなく、「全体主義」というもの本質を考察していたことのためのひとつの例証だったのです。
つまり、平凡な誰しもが、とてつもない悪を犯す可能性があるのだ、ということ。しかも当人は日常的なルーチンワークでもしているかのように、ただ職務を遂行するというだけの気持ちでしかないこともあるのだ、ということ。このようにして、人は大きな力に呑み込まれていき、その大きな力の一部としての役割を果たすようになってしまうこと。こうした指摘の流れは、オルテガの『大衆の反逆』(1929)もすでに言及していました。大衆という名の下に身を隠した人間たちが、実に野蛮な性質をもっていることを明らかにしていたのです。同じような流れで、ル・ボンの『群衆心理』(1895)もまた、人間が自分で考えることをなくして暴力を正義としていく危険性を、百年以上前に指摘していたことを、いまに活かさなければならないと考えます。
私はこの考察の方向を支持します。善良な顔をしている一般市民、そして本人も自分は善良であると信じて疑わない市民、それが実のところ暴力を振るっているのであり、社会や世界を悪へと推し進めるために力を加えているという観点を、忘れてはいけないものだと考えています。いまの社会でも、物言わぬ多数派がそうであるのかもしれませんが、事はもっと深いところにあると捉えています。
実際、キリスト教会は、歴史の中で何をしてきたでしょうか。新約聖書が書かれた当初は、少数派であり、迫害を受ける側であったかもしれません。しかしローマ帝国で公認され、国教とまでなりゆくと、その後は絶大な権力をもつようになりました。ヨーロッパの支配層となった教会組織は、人の生死をいとも簡単に左右するようになってゆきます。戦争も起こすし、魔女裁判を繰り返しては異端分子を排除もします。そして海外で幾多の文明を滅亡させることにも手を貸していくことになります。これらをすべて、神の思し召しとして、正義を実行するものとして、遂行していったのです。
敬虔なクリスチャンなどと言っている場合ではないわけです。キリスト教は、時の権力となって、あるいは権力を傘にして、実に暴力的で悪辣なことを、歴史上いくらでもしてきたのです。それは、性的マイノリティに対しても同様です。アメリカにおいても、半世紀前までは間違いなく、それは犯罪とされていたのです。その根拠は間違いなく聖書でした。また、彼らを嫌悪する者がアメリカ史上最悪の乱射事件を起こしたのが2016年、こういうことが、キリスト教を中心とする国や社会で現代においてもなされてきたことです。私は、日本の教会が、さも昔からずっと、性的マイノリティの人々の味方であったかのような顔をすることに、非常に嫌悪感を懐く者です。偽善者のすることだと思います。聖書を根拠に彼らを虐げてきたのは、まさにキリスト教会だったのですから。それで、教会がまずすることは、悔い改めて後、彼らに謝罪することであり、赦しを乞うことだと信じて止みません。その上で、支援をする、というのなら、分かるのです。そうでなければ、私たちがアイヒマンになるのです。
いえ、私は懸念します。キリスト教は敬虔だなどという決まり文句にいい気になって、実は残酷な、高慢な存在になっていないか、と恐れるのです。人を裁くような言葉や断定が、教会の中でも響いてきます。高圧的に、自分とは関係のない世界を一言でばっさりと決めつけます。しかし関係者は、その言葉を聞いている人の中にもいることがあります。聖書にも書いていないようなことで、それは悪だ、罪だ、人殺しだと、ひとの心に刃を突き刺すことが、現にあるのです。
かつてイエスが敵に回して非難を繰り返した、あのファリサイ派や律法学者を思い起こしてみます。彼らは、律法を守っていたはずです。正しい生き方をしていたはずです。旧約世界からすると、模範的な生活をしていたのだと思います。よく学び、神の言葉に従っていました。そして神の救いに与っていることを信じて、堂々とした人生を送っていたことだと思います。あるいは、少なくともそうした生活をしようと努めていたに違いありません。
気づかれましたか。これこそ、いま私たちが「クリスチャン」と読んでいる人々の姿ではないでしょうか。私は正しい生き方ができていないと思いますが、思い返せばこのような心持ちでいたことが、確かにあります。私はかつてまさにイエスの敵であったのですが、イエスの十字架を知ったその後にも、再びイエスの敵になろうとしていたのです。昔のキリスト教会が、人々の心と生命を支配し、世に君臨していったとき、その自身の暴走を止めることができなかったのも、悲しく思い返しますが、ありうべきことだったのだと認めざるをえません。私は、そのようなキリスト教を信じている者です。それでも信仰していると言って憚りません。神の言葉を新たに受けて、生かされているというところに縋っていきたいと願っています。
33:11 彼らに言いなさい。わたしは生きている、と主なる神は言われる。わたしは悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ、悪人がその道から立ち帰って生きることを喜ぶ。立ち帰れ、立ち帰れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。
神は私のような悪人であっても、「死ぬのを喜ばない」と言われました。この細い糸にしがみつきたいと願います。「生きることを喜ぶ」という神の言葉を心の支えにしたいと思います。
どんなふうであってもいい。ただ生きてさえいればいい。親は子どもに対して、時折そのように思うことがあります。もちろん、かなり切迫した情況でのことでしょう。日常的にそんな言葉を投げかけることはないだろうと思いますが、私などは、かなり頻繁にそのような思いを口にすることがあります。
細田守監督の映画のひとつに『おおかみこどもの雨と雪』というものがあります。ネタバレも起こしかねないのですが、最低限のストーリーを言いますと、女の子の「雪」と男の子の「雨」を、平凡な学生だった「花」は産む。父親は、人間の姿をした狼だった。懸命に2人を育てる花だったが、やがて子どもたちは成長して、そのまま人間として生きるか、狼としての生き方をとるか、選択する時期にさしかかっていた。「雨」は、山の自然を守ることを求め、狼として生きる道を選ぶ。台風の夜、突然山に向かった雨を追う花は、雨上がりに山に帰っていく雨に向けて、叫ぶ。「しっかり生きて!!!」
もうひとつ、最近読んだ本の中で、中島義道氏の『カイン』が心に残っています。タイトルが気になるかと思いますが、まさに創世記のあの最初の殺人者、カインです。人生に絶望し未来を見通せない大学生にひたすら手紙を宛てて書くという形式のものですが、著者の中島義道という名前をどこかで聞いた人はいらっしゃるだろうと思います。「戦う哲学者」として、世間の常識に吠え続けてきた人です。福岡県出身で、カント研究者でもあり、またその人生観においても私と共有できる部分があり、以前から愛読してきた哲学者でもあります。この本で著者自身の生い立ちとそこに含まれる復讐心などがふんだんに描かれていることも注目点ですが、良い子を止めてカインとして生きよ、というのが基本的なメッセージであろうかと思います。世間の善人たちは、自分の考えを押しつけようとし、それに疑念をもつ者を排斥し、迫害する。しかし私のアドバイスを読んできた君は、カインとして生き続けることができるはずだ。自分はいつだって「正しくない」ことを自覚しているならば、社会と手を結ぶ狡い生き方ではなく、ひとりで荒野をさまよい、「なぜだ」と問い続けながら生きるカインとして、本当の生き方ができるはずだ、と言うのです。
カインは、神のどこか理不尽な仕打ちに遭い、弟アベルを殺した人間です。このカインをモチーフに、有島武郎が『カインの末裔』を書いたことは有名です。人は生まれながらにして罪深い心を持っている。自分がそれだ、というところを思い知らされたのが、かのカインでした。しかし、カインは神により「呪われる者となった」と言われつつも、おまえは地上で生き続けると告げられます。しかも主なる神は、誰かに殺されることがないように、「カインにしるしを付けられた」のでした。
カインですら、生きるようにされたのです。エゼキエルもまた、悪人であったものが生きることがあると宣言します。
33:14 また、悪人に向かって、わたしが、『お前は必ず死ぬ』と言ったとしても、もし彼がその過ちから立ち帰って正義と恵みの業を行うなら、
33:15 すなわち、その悪人が質物を返し、奪ったものを償い、命の掟に従って歩き、不正を行わないなら、彼は必ず生きる。死ぬことはない。
33:16 彼の犯したすべての過ちは思い起こされず、正義と恵みの業を行った者は必ず生きる。
これはものすごいことです。神の言葉は、そのまま実現する、というのが聖書の基本的なスタンスです。その神が「お前は必ず死ぬ」と言っておきながら、その者が立ち帰るならば、「彼は必ず生きる。死ぬことはない」と言っています。およそ聖書に似合わないようなことです。神の言葉があってなお、それとは違った結果が生じるのですから、驚くべきことなのです。
そうした驚くべきことも、もしかすると、もっとすごいことが起こったことで、目立たなくなってしまいました。イエス・キリストの存在です。イエス・キリストが十字架において苦しみの極みを迎えたこと、しかしその残酷な死が復活という形で乗り越えられたこと、これはすごいことです。
私たちが自分の悪辣さに絶望し、自らを嫌悪しながらも、いやそれがあるからこそ、このキリストの奇蹟に出会って、神の常識すら塗り替えてしまいます。死ぬと宣告された者が生きるようになりました。この悪人たる私が、生きよとの言葉で、命が与えられたのです。その言葉は、同じ経験を、キリストを見上げる者、神の言葉で心の底を浚うように拭ってもらった者に、与えるに違いありません。神は「生きよ」と告げ、その言葉が真実となります。「必ず生きる」という神の約束が与えられます。これを信じるとき、私たちは、いまこのところから、別の新しい歩みが始められることになるのです。

