神罰 (カンディードとリスボン地震)
2020年9月19日
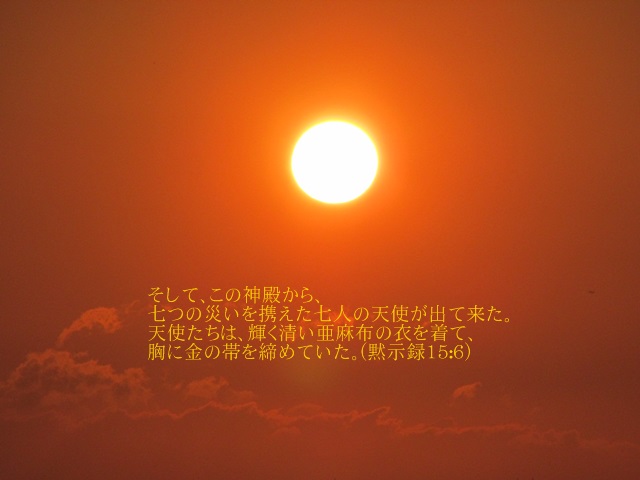
2020年は世界的に、とにかく新型コロナウイルスの年であったと言えそうな様相です。「コロナ禍」という言葉も使われるようになりましたが、「禍」という漢字が知られる契機にもなりました。「災禍」というように、この字も「わざわい」と読みます。普通、自然災害には「災」のほうを使いますが、どちらをも「災禍」と一括りにして呼ぶことにします。
大きな災禍があると、ひとはしばしば、これを「神罰」と評します。得体の知れない出来事に際して、何らかの説明をして不安から逃れたい、という心理のもたらすものだとも言われています。どうしてこんなことが起こったのか。それは、人の罪の故だ。人間が悪いからこういう罰が与えられるのだ。
これは近年とくに、キリスト教界では、避けるようになりました。一部、大震災を見て、これは神罰だ、と言ったようなグループもあったようですが、概してキリスト教界は、そうした見方や言い方を非難する傾向にあります。聖書の神は、人を愛する神であるから、罪の罰としてこの災禍をもたらしたわけではない、とするのです。
けれども、そもそも旧約聖書の書きぶりは、人の罪の故に災禍がもたらされた、という記述に満ちています。いったいこれを、私たちの神学はどのように説明するのでしょうか。
しかし、そもそもキリスト教は、災禍を神罰だ、と言い続けてきた文化であることを認めなければなりません。だから、いまも保守的な信仰態度を取るならば、神罰だと述べることは、いわば当然のことだ、とも言えるわけです。今の時代にそんなことを言うのは時代錯誤だ、とリベラル側が見下すようなことをするのは、適切ではないと考えます。それは現代人の立場で見ているのであって、聖書に立って見るならば、神罰と呼ぶことを否むことは難しいからです。
聖書を信仰するということは、これに限らず、矛盾のように思われることや、今の価値観からすると奇妙だと言わざるをえないことをも、歴史の底流から「引き受ける」ことではないかと私は考えています。先人たちと自分は違うんだ、のような態度を、私たちは取りたくなります。その心理は分かります。けれども、それは結局「自己義認」をしたいだけの精神を丸出しにしているのであって、今の世界で善いと認められている価値を称えることで、常に善人の側に自分がいるのだ、と構えてはいないか、常に自己吟味をする必要があると思うのです。そのほんの一例が、性同一性障害に対して少なからざる教会が支援の声を出していることですが、キリスト教界こそが、こうした人々を罪人と虐待してきた張本人であることを「引き受ける」ことがなくてよいとは思えないのです。
先ほど、大災禍を目の前にして、神罰だと考えるのは、説明により安心したいがためのひとつの「心理」だと申しましたが、もちろんそれは「信仰」でもありました。ヨーロッパの歴史だけを取り上げても、かつてペストなどの疫病により、教会どころか、国家や民族の危機に幾度も陥ったきた歴史がそこにあります。その度に、神罰と叫ぶことは、いわば当然の「信仰」でした。もし私たちが、そうした「神罰」ということを否定するようになっていたとしても、きっと自分たちでは気づかない中で、何かしらそれに相当するような、後になればおかしなことを言っていたな、と評価されざるをえないような、「信仰」の事柄を、さも唯一の正義であるかのように言い放っているのではないか。そのくらいの構えでいるべきではないか、と私は自分のことを思っています。
さて、『カンディード』という本を、先日やっと手にして読む機会が訪れました。ヴォルテールの、哲学的コントなのですが、これは、ライプニッツに代表される「最善説(オプティミスム)」への強烈な反論、あるいは嘲弄となる作品です。存在するものは、およそありうるもののうち最善のものである、という神学的な深い洞察から生まれた思想ですが、これを徹底的に揶揄し、笑いものにします。私が今回読んだのは、新しい訳で、この本には「リスボン大震災に寄せる詩」が本邦諸訳で掲載されていました。実はこの詩が読みたくて、こちらの訳を選んだことになります。
リスボン地震については、ここで説明するとさらに長くなりますから、ご存じなければお手数ですが検索ひとつで分かりますので、ご覧ください。世界史を大きく変えた巨大な災禍でした。世界トップの都市が一時に壊滅したのです。この『カンディード』には、丁寧な解説が渡名喜庸哲氏により施されていますが、そこでは、このリスボン地震について、災害の中でも特別な意味がある理由が挙げられているのですが、そのうち二つを引用します。
第二に、一一月一日という日付がさらに意味深い。この日はキリスト教の万聖節という祝日であって、多くの信徒がミサのために教会に集うことになっていたのだが、まさしくそこを大地震が、そしてそれに続いて津波と火災が襲ったのだ。このことはもう一つの帰結をもたらすことになった。栄華をきわめるカトリックの大都市を襲ったこの大災害は、人間の傲慢や奢侈をいさめるために神から与えられたものだ――このような「天罰」論が、とりわけ保守的な宗教界から出されたのである。聖書の「ノアの箱舟」の物語がそうであるように、理不尽に見える自然災害を、人々の不品行や悪業に対する神の懲罰、戒めとする考え方は、これまでのキリスト教世界ではきわめて強いものであった。……
けれども、――これを「リスボン地震」が特筆すべきものとなった理由の第三として挙げることができる――「神による戒め」、「天罰」というかたちで自然災害を宗教的に解釈する枠組みそれ自体を揺るがし、「災害」について多角的な(なかでも合理的、科学的な)議論を開くきっかけとなったこと、ここにこそ「リスボン地震」の最大の意義がある。【引用了】
こうしてこの解説は、震災復興のために合理的な都市計画がなされ、防災機能を備えた都市として、リスボンは復活を遂げた、と説明しています。但し、世界トップと言われる地位にあったポルトガルは、これ以後世界史の頂点に立つようなことはできなくなってしまいました。
教会の教えというものが、信頼されなくなっていくのです。啓蒙主義が展開し、産業革命が富をつくり資本の価値が世を支配し、やがて「神は死んだ」とまで言われる状況になる背後には、様々な理由があるのでしょうが、足を止めて考えてみる意味があるだろうと思います。もちろん、それはかつて幾度となく押し寄せてきたペストのような疫病のときにも、そうでした。教会は疫病を抑えることができない。この不信もあって、カトリックへの信頼が薄れ、ルネサンス文化が花開いたり、プロテスタントが支持されたりする歴史の流れができたりしたとすると、災禍はやはり世界史を大きく変えていく出来事として理解されるようになりうることが分かります。
最後にもう一度、『カンディード』の解説の一部を引用します。この世の悪の存在を含め、「摂理をめぐる論争」が当時も盛んに行われました。ヴォルテールとルソーとの間で論争がなされたほかに、カントもここに加わり、哲学の、あるいはまた恐らく神学の、必要不可欠なテーマとなっていくのです。
いずれにしても、こうした議論と思索のきっかけを作ることになったのが、本書に収められたヴォルテールの二つのテクストであることはまちがいない。確実なことは、それによって開かれた議論においては、これまでのような「天罰」か否かという議論は影を潜め、人間は災害にどれくらい関与しているのか、災害をどう認識すべきか、そこから何をなすべきか等々の議論が中心となってくるということだ。ヴォルテール以降、「災害」は「神」の領分を離れて「人間」の領分へと入ってゆくことになるのである。
(注)だが、十八世紀において「神」の領分から「人間」の領分へと場面が移ったのに対し、現代はどうかというと、現代は「人間」の領分から「システム」の領分へとさらに場面が移っているように思われる。【引用了】

