持続可能な社会
2020年1月27日
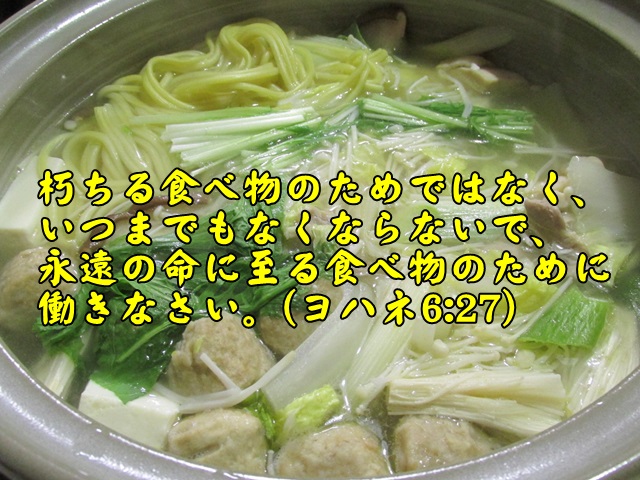
学校の教科書にも普通に載り、テストに出されるようになった言葉、「持続可能な社会」。もちろん報道でもよく聞く言葉ですが、さて、大人の皆さん、この言葉に通じていらっしゃるでしょうか。学校現場に関わっていないと、いま何が子どもたちに教えられているか、に疎くなります。それは、新しい時代の考えから離れてしまうということです。そうやって、昔の考えに固執するだけの頭の固い大人となり、若い世代から疎んじられるだけの存在へと突き進んでしまいがちです。そして昔はよかったという世界に閉じこもり、新しいのがよいというわけじゃないと嘯くようになる。あるいはまた、そんなことはないのだ、と新しい考えに好奇心をもつのはよいのですが、妙にズレた感覚で中途半端に新しい考えに接して使うので、逆にダサいと笑われるようなことになるのもありがちなことです。流行語がワイドショーで取り上げられると、それこそ時代の最先端だ、と喜んでやたら使いまくる大人がいますね。もうそんなの流行ってなんかねぇよ、と若者は哀れな目で見つめるわけですが、大人のほうは、自分は若者にとけこんでいる、と勘違いしているわけです。
さて、元に戻りましょう。「持続可能な社会」、これは何も流行り言葉というわけではありません。素人がくどくど知ったかぶりをするような真似はしたくないのですが、いわゆる地球環境問題、資源問題、食糧問題という大雑把な挙げ方をするだけでも、今後の世界の確立について危惧されることは明白でありましょう。少子化問題は、すべての国における問題ではないので、ここでは省くことにしますが、もちろん少子高齢化問題は、その国の存続について危機を招きます。但し、人口が増えることは先の環境や資源という問題については、その危機を助長するという捉え方が基本であるかもしれず、こうなると何が善いのか悪いのか、なんとも言えなくなってきます。
いったい、地球は存続するというのが善であるのかどうか。それさえ怪しくなってきます。
また、そもそも自分は生まれてこないほうがよかったのではないか、という問いすら起こります。おそらく何らかの誠実な人が、そのような論理に賛同するような気がします。私が誠実かどうかは知りませんが、その気持ちは分かります。あるいは、分かっていました。
『沈黙の春』でレイチェル・カーソンが叫んだとき、アメリカ人は小馬鹿にしました。いまも地球環境や資源に関わることで、アメリカの政策はそれを深刻に考えたり、責任を負おうとしたりする様子はないように見受けられます。それに対する若い世代を中心にした反対運動は一部にあるようにも思えるのですが、さて、今後どうなるのでしょう。
西欧文明が、教会支配の中世からギリシア・ローマ文化を見直し尊重するようになった近代への道は、科学の発展を促しました。それは、当初神を称える意図の中で探究されたものでしたが、自然を対象物として支配下に置くような「主体」が権威を有するように展開していきます。やがて技術と結びついて巨大な実際的力を有するようになっていきました。
道具として生まれたはずの科学技術でしたが、技術が主導権をとることになるのは歴史の必定でした。すると、無人格的な技術が支配しているかのように見えて、実は人間の欲望が歯止めを利かせることができなくなっていく運命へと人類が転がり込んでいくばかりでした。何かしら人間が気づかねばなりません。かつて近代理性が始まり論争に明け暮れていたときにカントが人間理性自身を批判することで、なにかしらブレーキがかかったことに比するものがあるとすれば、この転がり大きくなる時代の力をなんとか反省するものはないかということで、言葉というものに光が当てられました。理性が思考するという点を原理とするのがかつての近代理性であったとすると、その理性の判断自体を形成しているのが言葉であることに注目した、とも言えそうです。
こうしていまや「持続可能な社会」という言葉が生まれてきました。私たちはこれをどう扱っていきましょう。そもそもこの言葉をどう解するべきか、問われています。国連はSDGs(持続可能な開発目標)を掲げており、先日はダボス会議(スイス)にてテーンエイジャーたちがこの問題について発言するということで話題になっていました。去年のこの会議から、彼らに注目が集まることとなったとも言えます。
そんなスケールでものを考えつつも、隣人ひとり愛せないような自分に、何ができるのか、と言われればその通りです。自分が蚊帳の外にいるかのように、信仰や聖書という問題を扱うことはありえないはず。主観客観の対立という近代の規定された構図からちっとも抜け出してなんかいない。自分がそこにいる。それは自分のこと。自分のために言われている。環境問題は、環境をというものを相手にどうしようか、といった問題ではありません。自分が環境そのものであり、環境が私そのものであること、私自身が個人的に請け負わなければならない責任というものがあるという強い自覚がなければ、持続可能な社会というものを形成することは不可能なのです。誰かほかの人がやってくれ、ではどうにもなりません。客観の外に主観たる自分がいるわけではないのです。
世界には、無責任に世界の外に出ているつもりでいる自分を自覚することができずに、自分が被害者であるという正義漢を振り回す個人が増えてきています。先ず自分から、という意味で「先ず隗より始めよ」という知恵を弁えておきたいものです。他人が皆それをするなら自分もしてもいい、と考える人間は、必ずしも少なくないのですから。
持続可能な世界は、しょせん「可能」です。永遠に持続するという意味ではありません。その意味でも、呑気に万物は流転するだの、生まれ変わるだのといった楽観さは、保持しづらい考え方となるのではないでしょうか。かといって、やけになり今すぐ終わらせてしまえというような、究極の自己中心性を露呈する必要もありますまい。「可能」であるように協力することは、いまの時代を生きる者の義務であると思われます。しかし、だからこの世界は持続が終わらない、とする必要もないでしょう。終わりの日、と聖書は告げます。案外、私たちがイメージするその「終わり」とは、似ても似つかぬ「終わり」が来るのではないか、という気もしますが、持続を絶対的なものとして要求はせずとも、持続するかのように、その可能性に協力していく生き方というものが、求められているというあたりで、ひとつの結論としておきまょうか。

