【メッセージ】朝を待つ
2019年10月20日
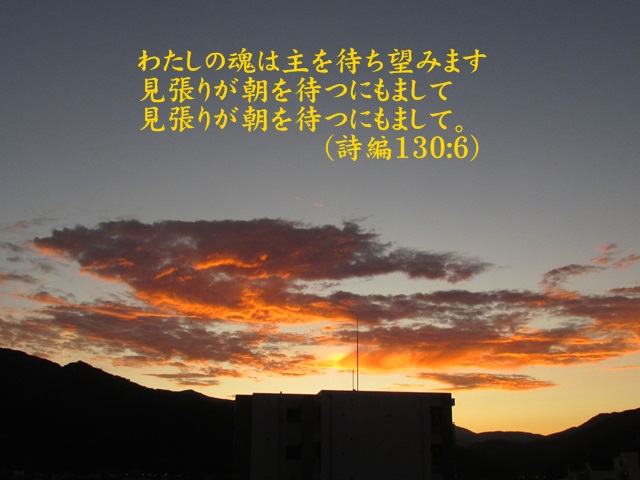
(詩編130:1-8)
わたしの魂は主を待ち望みます
見張りが朝を待つにもまして
見張りが朝を待つにもまして。(詩編130:6)
これも都に上る歌。詩人は自分と主との対峙の現場にいます。そして最後に、同胞イスラエル全体のことをも考慮しています。神殿に向かう思いからでしょう。最初には「深い淵の底から」と、穏やかでないフレーズがあります。そのため、詩編の中で七つあるという「悔改めの詩編」のうちのひとつに数えられていますが、全般を通して、悔い改めの色彩はさほど強くないように感じます。確かに、「主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら/主よ、誰が耐ええましょう」とあり、「赦しはあなたのもとに」あると告白していますがし、罪から贖うなどとありますが、私には、詩人の個人的な切迫さが窺えません。言い方が悪いかもしれませんが、他人事のように罪とか赦しとかを口にしているだけのように思います。ただ最初の「深い淵の底から」だけが、重い響きを伝えているというふうです。
しかし、自身の辛さをかみしめる人には、確かにこれは魂の深いところに響くスタートだと言えるでしょう。這い上がれないような絶望の谷底を思わせる言葉ですから、ここに共感する人にはたまらなく切ない、苦しい詩の始まりだということになります。まさにそうだと思います。
いじめは、子どもだけでなく大人社会にも蔓延しています。いじめている方はその意識がないのに、被害者のほうは死にたいほど辛いという状況に置かれている人の苦しみはいかばかりかと思います。そうした加害者がいるにしろ、いないにしろ、人は生活の中で、学びや仕事の場で、様々な困難を覚えていることでしょうから、この詩の「深い淵の底から」に、いきなり波長が合うということを、大切に扱いたいと思います。
130:1 深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。
130:2 主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈るわたしの声に耳を傾けてください。
詩人は、主を呼びます。主に聞いてほしいと願います。私は嘆いているのです。それを主に知ってほしいのです。悲しみや辛さの訴えが、ただのぼやきや愚痴でなく、「嘆き祈る」というとこにひとつのエポックがあります。私は主に向けてこれを訴えているのです。どちらを向いているか。主の方を、です。主に向けて嘆いています。
私たちはしばしばそれを忘れます。辛い、苦しい、ああどうしよう。目を周囲に向けてはオロオロし、解決できない事態を覚え、未来に不安を懐き、あるいは絶望します。しかしイスラエルの詩人は、呼びかける相手として「あなた」なる主を知っています。これは強みです。「どうしてこんな辛いことが起こるのか」との悲しみや嘆き、あるいは疑問にしても、その前に「神さま」という言葉が付くだけで、全く違う問いになること、ここをまず押さえておきたいと思います。私たちは、不条理なことを、神に向けて疑問として呈してもよいのです。まずは神を見上げること、神のほうを向くこと。
130:3 主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら/主よ、誰が耐ええましょう。
130:4 しかし、赦しはあなたのもとにあり/人はあなたを畏れ敬うのです。
どこか抽象的ながら、罪と赦しが対応して現れます。人には罪があるもの。だから罪のまま主の前に出れば裁かれるでしょう。神は赦しを与えてもくれるのです。その赦しの故に、人は神を慕い愛するようになるのです。何かしら悔い改めの要素があることは確かです。けれども私には、切実な罪の意識や切迫感をここに見ることはできません。嘆き祈っても、罪とか赦しとか口にしようが、どこか一般的な言及に留まっているように思われてならないのです。
確かに「わたしの声に耳を傾けてください」と2節で触れていました。が、詩はこの中央に至って、ということはつまり、この詩のハイライトに至って、ひたすら「わたし」が主役に躍り出ます。さあ、ここで私たちも、この「わたし」になりましょう。詩人の「わたし」はこの私であり、そして、あなたです。この「わたし」を傍観せず、いまからその「わたし」になりましょう。
130:5 わたしは主に望みをおき/わたしの魂は望みをおき/御言葉を待ち望みます。
130:6 わたしの魂は主を待ち望みます/見張りが朝を待つにもまして/見張りが朝を待つにもまして。
いま私に必要なのは何でしょう。生活の中で問題を抱える私たち、人間関係において嫌な思いを懐いている私たち、この私にとり、今日出会ったこの聖書の言葉は、つまり神は、何を残してくれるでしょう。私をどのように揺り動かしてくれるでしょう。そう、「待ち望む」ことです。漢字では「望」が幾度も出て来ますから、「望む」ことが必要だというのもひとつの大切な観点ですが、今日私が強く覚えたのは、「待つ」ことでした。「見張りが朝を待つにもまして」と繰り返していることで、詩人がそこを重く捉えたのだと理解したのです。夜番の見張りが、早くこの物騒な夜が明けて仕事から無事に解放されてほしいと、夜明けを今かいまかと待つ気持ちに自分の心を重ねているのではないかと感じたのです。
待つというのは、ある時が来て、事が解決するのをゴールに設定している思いで支えられる行為です。待つからには、何かある事態を目標としています。そしてその時が現実になったら、その待つという行為は終わります。私の心の中では、ある事柄の実現を想定し、それまで待つのです。待つからには、自分で事を解決しようという気持ちはありません。自分で何かをするのではないのです。自分が何かをやってそれを実現するというのではなく、誰かほかの人やほかの存在が変化することによって、自分が思い描く事態が実現する、ということを目標としているのです。目的であるならば、自分が行為して、努力して、それを目指すことでしょう。自分が動かなければ、目的達成は望めないでしょう。しかし待つとなれば、自分で何をすることもできません。自分が動いてもその待つ目的に対して、貢献することができないと知っています。私は待つ目的に対しては、無力なのです。ほかの何かに、結果を委ねていることになります。ほかの何かを信じるしかないのです。
太宰治の『走れメロス』で、メロスの帰るのを待っていたセリヌンティウスは、メロスを信じるしかありませんでした。それを後に、一度だけ疑ったと打ち明けましたが、それほどに、自分の命がかかっている現場となると、待つことは難しいものがあります。私たちは、詩人が口に出したような「待つ」ときに、自分の命がかかっているということを、あまり意識しません。でも今日は、どなたでも、自分の命がかかっていると思ってこの詩に触れて戴きたいのです。主の言葉を、命をもたらすものとして待つことを。それがこの世に、そしてこの自分の身において実現するようになることを待つのだ、と。
実は、待つ名人がいます。それは、子どもです。「ここで待っていなさい」と親に言われた子どもは、ただそこで待つしかありません。なかなか親が戻って来ないと、不安を覚えますが、かといって自分で動いて何かができるという知恵も勇気もありません。ひたすらそこで待ちます。これが大人にはなかなかできないことです。何かあったのだろうか、自分はどうすればよいだろうか、と動き始めます。こうして大人の待ち合わせは、しばしばすれ違ってしまうようになります。今どきにはスマホで連絡すればよいので、そうしたすれ違いのドラマは起こりにくくなりました。昔の「君の名は」もそうですし、私などは待ち合わせ場所を勘違いしてなかなか会えなかった「めぞん一刻」のすれ違いなどが、切なくドキドキさせるものだと記憶しています。何時間でも待ち続けた五代くんの気持ちが、痛いほどよく分かる頃がありました。
子どもは待ちます。子どものように自分は無力だという前提があることで、待つことは苦痛でなくなる、あるいは待つしかないということになります。しかし、待っている間にはなかなか泣かず、親がついに現れたときに、ほっとして泣く、そんなものです。私たちも、待つときにはただ待つというあり方で、いざ相手が現れたとき、事が実現したとき、うれし涙を流すということを理解できないわけではありません。その時がくれば、すばらしいことが起きます。助けられます。世界が変わります。聖書で「待つ」ことが言われているときにも、そうした私たちの身近な体験を、推測のために少しばかり重ねてもよいのではないかと私は思います。さらに、自分が無力だからただ待つしかない、という子どものようなあり方、そうした子どものようでなければ神の国に入ることができない、とイエスが言ったことも、少し関係があるのではないかという気がします。
自分が事を決めるのではありません。誰かほかの人や存在に、主導権を渡すのです。詩人はそれを「主」に任せるという態度です。これは、詩人が個人的にそう思うだけというわけではありません。これがイスラエルです。聖書を紡いできた民族の、底流にある信頼であり、希望であったのです。
130:7 イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに/豊かな贖いも主のもとに。
130:8 主は、イスラエルを/すべての罪から贖ってくださる。
購いというのは、イスラエルの文化です。買い戻されるというややこしい法的な概念が伴いますが、とにかくなんとなく水に流すというあり方で実のところ被害者に負担をかけるというのではなく、加害者が本来許されざる行為について、痛みある支払いをすることでなんとかその悪、あるいは罪というものを、白紙に戻してもらうという約束に基づいた行為です。主なる神が、そうやって私たちの悪あるいは罪を白紙に戻してくださる、という信頼を、詩人は詩の最後で繰り返します。同胞よ、こうなのだよ、私はこのことを知っているから、皆もそうであれよ、と呼びかけています。歌は、このように呼びかけて連帯することを以て、結ばれます。単なる個人的な思い込みでなく、共同体皆の共通の理解の中で、互いに励まし合うような状況を明らかにしています。私たちも、教会生活というこの仲間の中にいる限り、これと似た感覚を味わうことができます。私が待つ、それは皆も待つことだ。共に待とうではないか。自分たちが何かをしてしまうことではないという自覚を以て、つながっていようではないか。イスラエルという言葉を、いまは「クリスチャン」とか「教会」とかいう名で置き換えて考えることが許されることでしょう。都へ上る途上の歩みを、日々の生活として着実に進めている私たちは、主がすべてを解決してくださること、明るい光に包まれる朝という救いの完成の時を待ちつつ、望みつつ、今日もいまも、主を見上げてその名を呼ぶのです。たとえここが暗闇であり淵の中のような、苦難の中であったとしても。

