口伝について
2019年8月14日
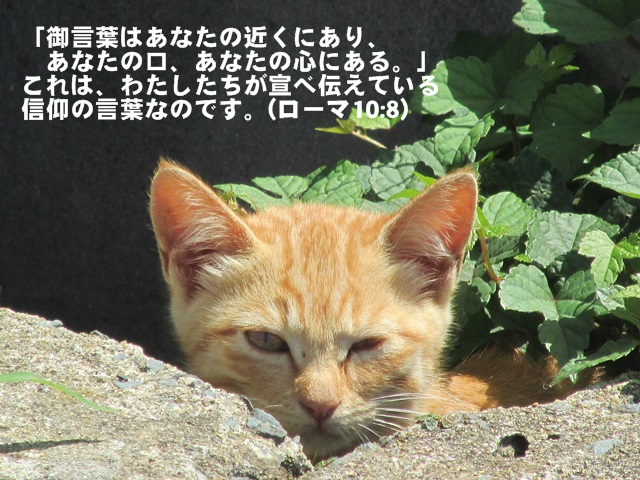
8月14日という事実上の終戦の時を迎え、広島にしろ長崎にしろ、そしてもちろん沖縄戦にしろ、同じ年数を刻む思い起こしがひとつの頂上を見る思いがしますが、これが戦後十年を数えるあたりから、意図的に15日が終わりだというように変えられてきたことの影響を、その後の社会はあまりにも大きく受けすぎているように見受けられます。その意味では、文書よりも、口で語り継がれることの力は軽視できないことがよく分かります。
大昔は文字がなかったから、すべて口伝であった、というふうに一般には言われています。本当にそうだろうか、と私は疑います。調った万人に理解可能な文字文化が成立していなかったかもしれないけれど、果たして口伝えのみで本当に伝わるものなのだろうか、と不思議に思うのです。
日本にも、漢字がもたらされる間では文字がなく、従って漢字を見たとき、それに日本語の発音をうまく乗せて、いわば記号として漢字を利用して口で言う言葉を記録するようになった、とよく言われています。
太安万侶が史書の編纂に携わったとされていますが、このとき、稗田阿礼が記憶する歴史を文字にした、というような伝説が信じられています。しかし稗田阿礼についてはあまりにも謎が多く、その実在性さえ疑われているのが実情です。なおのこと、記憶力のよさから歴史をそらんじる云々となると、具体的に何をどうしたか全く分からないとしか言いようがありません。歴史は勝者の記録を遺すために記すという点で、こうして書かれた歴史書も、以前の歴史を消して支配者の正当性を訴えるために作られたのではないか、と眉に唾を付けて考えてしまいます。
この辺りのことを、手塚治虫は『火の鳥』の「ヤマト編」では、次のように記しています。「ヤマト王朝の古事記とか日本書紀なんかにはそういうわけでクマソを未開人あつかいしたり悪人みたいに書いてある。もしクマソのだれかが当時のクマソの記録を書き残したとしたら古代日本の歴史はかなり変わっていたかもしれない。だが残念ながらそれは残っていない。……(中略)……つまり……歴史とはあらゆる角度からあらゆる人間の側から調べなければほんとのことはわからないものなのである。」
同じヤマト編の冒頭で、ヤマトの王がその国の記録を遺すために、「カセットテープ」と呼ばれる者たちが監禁され、一人ひとりが「ヤマト王朝の正しい歴史をつくるように命令」され、一定の文句を記憶して、口に貼られたテープを外されるとそれを再生して語るという「録音」の様子を手塚治虫は描いています。もちろん「語部」と一般に呼ばれている、文字のない時代の歴史の記録のことで、たいへんな皮肉をこめたギャグです。
後の琵琶法師は、盲目でありつつ平家物語を全部暗誦し琵琶を奏でながら謳ったそうですが、これ自体はありうることだと思います。ただ、それも晴眼者がそれを文字にして遺しているからこそ私たちにその文学が伝えられているのであって、純粋に口伝によって後世に伝えられたというものではありません。個人的に暗誦能力のある人物はいたでしょうが、何も文字のような手段をとらずに口伝えだけで重要な記録を遺そうとするのか、そんなリスクを冒すだろうかと、私は疑念をもつのです。
何を言いたいのかというと、聖書はどうだろうか、ということです。聖書は神の言葉あるいはイスラエルの記録であるわけですが、それを指すときに新約聖書は「書かれたもの」という言葉を用いています。口伝ではないわけです。また、すでに文字があった以上、口伝にする必要はなかったことになります。旧約時代の文献にしてそうなのですから、新約の時代になって、なお口伝だけで記録が遺り、それを数十年後に初めて文字にした、というようなことが、ありうるでしょうか。私はそんなはずはないだろう、と思います。
ところが、新約聖書の各書が書かれた年代が研究されるにつれ、どういうわけかそのような伝説が、既成の事実のように飛び交っているのが実情です。それどころか、律法自体も口伝律法として口伝えであったかのような言い方がなされます。いえ、それは置いておきましょう。新約聖書の成立において、文書資料があることは仮説として認められていますが、それと共に口伝資料とが、たとえば福音書記者によって編集されたのだ、というふうに言われています。そのときの口伝というのが私は意味が分からないわけです。すでにイエスが弟子たちと活動したころから半世紀を経ているような頃です。記録性と報道性のまるで異なる現代と単純比較はできないのですが、沖縄がまだアメリカの統治下にあった頃、大阪万博の頃のことを、文書記録なしに言い伝えだけで、信頼を置くべき決定的な重要文書の編纂に使うかどうか、ということです。もちろん、戦争体験などはそのようにして聞き取りをしなければならない、いま重要な時期にきていますが、果たしてあの福音書の記事が「口伝」によって書かれた側面があるという意味は、どのようなことでありましょうか。
口伝という行為を、一種のメタファーとして受け止めるのならば、反対はしません。何らか体験者が思い起こしたことも参考にする、という程度であればよいのですが、いくら文字を書けるということが特権的な才覚であったとしても、口伝えに遺された記録というようなイメージで、私たちの前に置かれたら、私たちはずいぶんと実情と違うものを想像してしまうのではないでしょうか。
口伝に頼ると、誰かの意思、意図が大きく歴史を変化させます。口伝の要素を大きく考えると、編集者が自由に事実を変えて書き記すということになってしまいます。多くの偉人の伝記が、脚色に満ちたものになってしまっているのと同様です。果たして福音書は、そのようなものに過ぎないのでしょうか。そうだという人もいます。しかしそれなら、私たちはその中からどのように、神を感じ、神から声を聞き、神と出会うことになるのでしょうか。あまりにも聖書を、神との生きた交わりから排斥するような言い方をして、多くの信仰者の生の事実を否定し去るようなイメージをもたらす言い方をすることには、賛同できません。
ただ、文字によらないものを伝えることが無理だなどというつもりは全くなく、むしろ文字にならないものが大切なことを伝えていくことは大いに必要だ、とも私は考えます。親が子に伝えるものは、口から出る言葉だけではありません。子は親の背中を見て育つ、とも言います。自分の生き方すべてが、子どもに伝わっていくものであるし、ちょっとした瞬時の仕草や動きが、子どもに大きな影響を与えることもあります。もちろん、子どもに対してだけでなく、身近な人、初めて会う人、通りすがりの人もまた、同様です。私たちは、つねに何かを伝えていくことができる、それが人と人との関わりということに違いありません。

