宗教改革501年
2018年10月31日
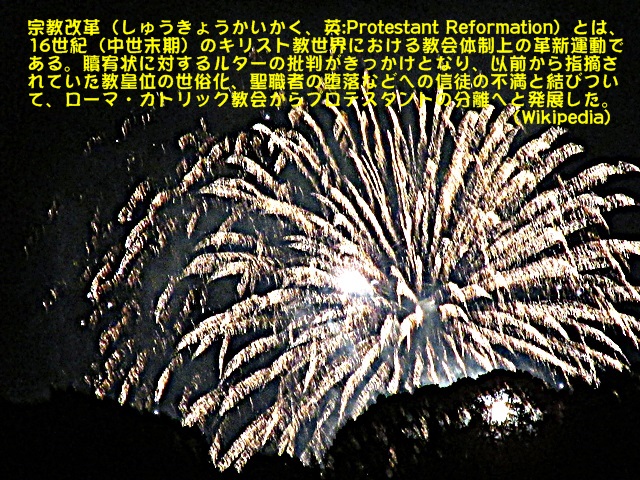
歴史上の名場面は、しばしば脚色めいたものとされています。ルターの宗教改革についても、人々が祭で集まる場に、どどんと貼り付けた、みたいなマンガがイメージされますが、近年はそんなはずはないだろうという研究が進んでいます。
しかしその時期に導火線に火が点いたのは間違いないようで、プロテスタントの誕生の時として、昨年2017年は宗教改革500年を記念する行事が各地で行われました。
他方、それに関心を寄せないプロテスタント教会もたくさんありました。ルター派は、プロテスタントのグループの中でも、決して多数派ではなく、また思想的に相容れないと考えるグループが多々あるので、ある意味でどこか冷めた目で、ルター派とカトリックとの握手を眺めているような雰囲気すらありました。
もちろん、500年というのは単なる数字のことであって、そこに深い意味があるわけではありませんが、互いに近づき手を結ぶ努力をしようという出来事、一種の和解の行為を蔑ろにするというのは、もったいないことのように思えます。
距離を置くグループとしては、そこに怪しいものを見出しているのでしょうか。もしそこに何か策略があって、この和解を手段として別の意図をもっているというように利用しているだけなのなら、この和解も空しいものでしょうが、さて、そんなものなのでしょうか。
数字は数字に過ぎませんが、数字はまた、気持ちを新たにする契機にもなります。高校野球でさえ、100回記念ということで、盛り上げもできたのですし、気概を育むものともなりえたことでしょう。何かしらの、新たなスタートとして意識を高めることが可能かもしれません。
プロテスタント教会は、幸い、聖書という、戻るべき家があります。カトリック教会は教会の伝統にも大きな価値を置きます。しかしプロテスタントとて、教会に意味がないと考えている極論を良しとはしないでしょうし、カトリックも聖書を無視して恣意的な運びを望むものではないでしょう。どちらも神の名を掲げ、どちらも人の集まりです。完全なるものを背景にもちながらも、不完全な人間が営みます。人の立場として、教会が互いに信頼をしないままに歩んでいくところに、何の希望があるのでしょうか。
これは小さな教会においても、組織となった瞬間、何か違う原理が大きな顔をして、大切な土台をすり替えてしまうのではないかという懸念が私にはあります。組織化した教会が、信徒の信仰生活をいつの間にかねじ曲げていき、聖書ならぬものを第一とさせるような事態は、多々あるように思われてなりません。
宮田光雄集の「聖書の信仰」シリーズ全七巻をすべて古書で手に入れ、読ませて戴きました。『国家と宗教』を先日読み終えたのですが、このように時折教会は「国家」というものを論じます。国家が教会を圧していくことが正当化されてよいのか、また日本の近代においてこの構図はどうだったのか、真摯に問うべきだろうと思いますし、多くの心ある方が問うています。しかし、この構図がそのまま、教会と信徒個人との間に成立していないか、振り返ることを、どれほどのキリスト者が意識しているでしょうか。人間は国家として振る舞う立場になると、教会を従えるように働くことを危険視するキリスト者は多いのですが、その傾向性は、人間が教会として振る舞う立場になるときにも、ありうるのだということを、意識しているだろうか、ということです。
宗教改革501年を経て、教会が教会自身をどう意識するのか、難しい問題を提供してみたい。結局自己肯定ばかりするのであれば、国家が暴走して個人を圧していくのと、同じことを教会すらしてしまうのだ、という人間的な性質を弁えているかどうか、問いたいと思うのです。
この思い、伝わる方がいらっしゃるでしょうか。

