【メッセージ】回り道を導くもの
2020年9月6日
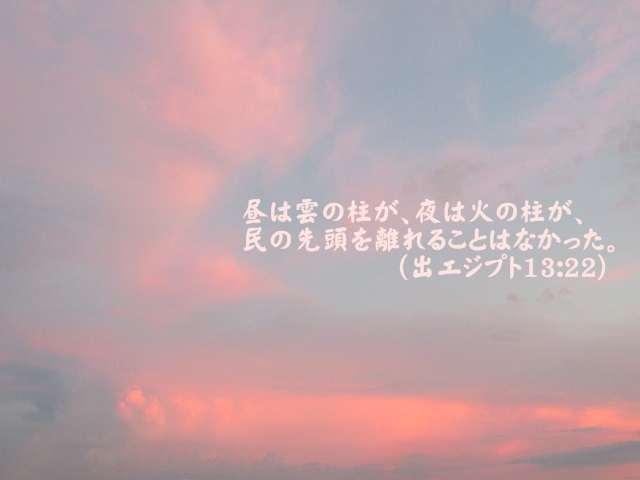
(出エジプト13:17-22)
昼は雲の柱が、夜は火の柱が、民の先頭を離れることはなかった。(出エジプト13:22)
イスラエルの民は、ついにエジプト脱出を果たすことになります。……などと簡単にはいかないのですが、今日はその旅立ちの希望溢れる雰囲気のままに終わりたいと願っています。
ところで、進学塾で子どもたちを預かっていると、親の気持ちというものがひしひしと押し寄せてきます。中学生の場合は、親も我が子の力がだいたい分かっているし、本人がどう選ぶかという点が一番なので、あまり親の意志や意見をぶつけてはこない傾向があります。このままではどうなるか、見定めたいところです。公立高校に行ってほしいという、経済的な心理があるとすれば、私立高校になるかどうかの判断こそが、重要になるわけです。
ところが小学生の場合、つまり中学受験というのは、本人よりも、実は親の受験である、と言われるほどで、親のほうがなんとか合格させたいとかなり熱心になります。そして、あとこれくらいやらせてくださいと頼むと、その通りすれば大丈夫なんですね、とばかり子どもに無理にでもそれをさせようと動いてくれます。子どもも、親の言うとおりにしか動かないような時期ですから、ストレス云々などと言っている場合ではありません。受験の意志さえ具わっていれば、たいていの子は、自分の限界に挑むべく、どんなことでもするようになるものです。
そんな親の熱心さが揶揄されるように、ドラマで描かれることがありますが、我が子をなんとしてでも合格させようと無理難題をもちかける親は、基本的にいません。どうにかして最短距離で合格させようとする近視眼的な見方をする方は、普通いないものです。もちろん、合格が目標です。しかし、目の前のエサだけがすべてということではなく、その子にとって何が良いものか、長い目で見る眼差しも必要だということはよく分かってくださいます。たとえ無理して合格したとしても、そこから始まる学校生活というものを想定していないと、その学校での学びを続けられなくなってしまうのですから。
回りくどくなりましたが、そう、話もそうです。ストレートにストーリーに没頭していくばかりでなく、時には回り道をして、心の準備でもしながら、大切な話に入り込んでいくということもあってよいでしょう。
エジプトを出ることに成功したイスラエルの民。大人の男だけで六十万人いたなどとも別に書かれています。
12:37 イスラエルの人々はラメセスからスコトに向けて出発した。一行は、妻子を別にして、壮年男子だけでおよそ六十万人であった。
この民は、目的の地、当時はカナンとのみ呼ばれていた、後のイスラエルの地を目指して壮大な行列をつくって移動することになります。その時、負担を軽くするためにも、近道がよいように思われますが、神が選んで導いたのは、遠回りの道であった、このことが今日の最初に書かれてあります。
13:17 さて、ファラオが民を去らせたとき、神は彼らをペリシテ街道には導かれなかった。それは近道であったが、民が戦わねばならぬことを知って後悔し、エジプトに帰ろうとするかもしれない、と思われたからである。
13:18 神は民を、葦の海に通じる荒れ野の道に迂回させられた。イスラエルの人々は、隊伍を整えてエジプトの国から上った。
何か理由をこじつけているように、見えなくもありません。しかし、この対比は、明確に方向性が違うように描かれています。つまり民は、近道だと、戦いへの恐怖から後悔し、エジプトへと帰ろうとするであろうと書かれています。そこで神が導いたように、迂回路を行くならば、荒れ野ではあるものの、エジプトから離れていく方向へと進むことになります。
キリストを信じて、信仰生活を始めたとき、何かと危機が訪れると言われます。やっぱり元の生活に戻りたいという誘惑もありうるし、周りとの衝突が生じることもあります。教会生活が、こんなはずでは、と落胆することもあるし、たちまち様々な問題が襲いかかってくるというこもとしばしばです。これを、悪魔が狙って、キリストにつく者を躓かせようとするものなのだ、と説明することもあるほどです。
イスラエル民も、エジプトを出たところで、やはりあのエジプトへ戻りたいという気持ちが起こるようなことを、神は危険視したのです。いや、もう足も目も、そして心も、エジプトには背を向けていかなければなりません。そしてカナンの地へ上っていく、一本道だけがそこにあるべきだと見なすのです。
それは足場が悪く、食糧や水を得るのにも不都合な、荒れ野を行くコースでした。当時もいくつかの街道が整えられており、旅には便利な面があったと思われます。しかし、そこでは出会う相手も多く、ペリシテ街道というくらいですから、後にイスラエルの宿敵となるペリシテ人が多く住まう土地でもあったのでしょう。とにかく他の民族や国を通過する際に、様々な争いが起こるリスクが高くなります。迂回させるという神の配慮は、このような背景があったのでしょう。決して楽ではない旅の道、しかも遠回りであろうコース、これのほうが、間違いなくエジプトから離れていく道となります。洗礼を受けたビギナーのクリスチャンも、困難があるかもしれないし、損をすることになるかもしれないけれども、確実に、かつての世界から離れていき、神の国に向けて進む道へと導かれていくはずです。この出エジプトのイスラエルの民と共に、旅してみるというのは如何でしょう。いえ、もちろんベテランのクリスチャンもまた、ここから歩いてみるのも悪くありません。
さて、ここで、不思議な叙述に出会います。
13:19 モーセはヨセフの骨を携えていた。ヨセフが、「神は必ずあなたたちを顧みられる。そのとき、わたしの骨をここから一緒に携えて上るように」と言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。
ここだけに触れられる、ヨセフについての情報です。ヨセフは、カナンの地から兄弟に嫌われた末、数奇な運命の中でエジプトに来てそこで出世した人物です。やがて飢饉をきっかけに親兄弟をカナンの地からエジプトに呼び、そこで生まれ故郷を離れたままに生涯を全うしました。そのヨセフには遺言がありました。創世記に、いまわの際で、兄弟たちにこう言い残した記録があります。
50:24 ヨセフは兄弟たちに言った。「わたしは間もなく死にます。しかし、神は必ずあなたたちを顧みてくださり、この国からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き上ってくださいます。」
50:25 それから、ヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。「神は、必ずあなたたちを顧みてくださいます。そのときには、わたしの骨をここから携えて上ってください。」
このヨセフがエジプトの宰相だったことなど忘れ去られていたが故に、イスラエル人が不当な労役を強いられていたという背景だったのですが、モーセだか誰だか、このヨセフのことをちゃんと覚えて言い伝えていたということなのでしょうか。この辺り、つながりが不思議です。聖書に書かれていないことをあれこれと想像して牽強付会のように説明するよりは、なんだろうという思いで聖書に向き合うことも必要です。いつの間にか、説明する自分のほうが聖書より上に立つようなことを避けるためです。聖書から聞く、聖書から呼ばれる。ここではモーセがヨセフの骨を持っていたというのです。但し、モーセがそれを最初から預かって持ち歩いていたというふうに決める必要はありません。いまイスラエル民族を導く指導者となったモーセの手に、ヨセフの骨を守り伝えていた誰かが託したのかもしれません。
ヨセフの遺言を大切にするということは、この民族の言い伝えを守っているということです。アブラハム・イサク・ヤコブという系列の、次に属するヨセフを尊重するということです。民族のアイデンティティがそこにあった、と見ることもできます。ヨセフの信仰と共に、これからイスラエル民族は、本来の土地を目指して進んでいくのです。そしてここで移動する民族は、ただここにいるだけのメンバーが移動するのではなくて、歴史をつくった父祖をも含めて歩むのです。私たちの人生が、自分という個人だけで歩んでいくべきものではなくて、つながった歴史の中で、多くの人々と共に歩むはずのものであることを、噛みしめてみたいと思います。
13:20 一行はスコトから旅立って、荒れ野の端のエタムに宿営した。
スコトは明らかに、まだエジプトの国内そのものという場所です。ヨセフの兄弟たちが住むように宛われていたゴシェンの地と言ってよいようなところです。イスラエルの民は基本的にそこに住んでいたようなことも窺えます(出エジプト9:26)。エタムはよく分かりませんが、そこからいよいよ荒れ野の道を行くというところであったと思われます。遠回りの迂回路がここからスタートすることになるのでしょう。
13:21 主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱をもって導き、夜は火の柱をもって彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。
13:22 昼は雲の柱が、夜は火の柱が、民の先頭を離れることはなかった。
なんと言ってもこの光景が、お見事です。もしこの先に、あの海が分かれる大スペクタクルがなかったならば、出エジプトを象徴する最大の見せ場として描かれることになったのではないかと思います。とてつもなく不思議な光景です。
ここでイスラエルの民は、昼は雲の柱を頼りに、夜は火の柱を頼りに、前進することができたと書かれています。もちろんこの時代の人々が「柱」と表現したものが、いま私たちが想像する「柱」と同じものを指しているかどうかは分かりません。電柱が動いているような絵を描けば、ほぼマンガになります。では竜巻あるいは旋風のようなものなのでしょうか。
アブラムが主を信じた(創世記15:6)とき、「日が沈み、暗闇に覆われたころ、突然、煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた」(創世記15:17)という不思議な幻がありましたが、火の柱というのはこのような松明のようなものだったのでしょうか。
考えれば考えるほど、分からなくなります。だとすれば、この情景は、比喩に過ぎないのでしょうか。確かに、考えてみれば、「昼も夜も行進することができた」というのは、文字通りに受け取ることは難しい言葉です。だとするといつ休むのでしょう。無理な話です。私たちが「昼も夜も」という表現を使うときには、昼も夜も休まずすべて、という意味では言わないでしょう。「昼にしようと思えば昼にも、また時に夜にしようと思えば夜にもできた」という意味のときに使うものと思われます。ここでイスラエルの民が「昼も夜も行進することができた」のは、必要とあれば夜にだって動くことはできたのだ、という意味であるにほかなりません。
これは信仰生活にも戒められることでしょう。日曜日だけクリスチャンの顔をして教会に集まるが、他の日は、甚だしくは礼拝から帰るその道ですら、聖書とは無関係な生活、考え方をしている暮らしをしているわけにはゆかないということです。私たちはクリスチャンとして「昼も夜も行進することができた」と言えるようでありたいものです。そう考えると、この「柱」が昼夜を分かたず導いたというのは、なんとも示唆的だと言えます。
さらに気になるのは、やはり「柱」。これは後に、幕屋ばかりか神殿の柱をも意味する語です。その建築を成り立たせる支えです。一方で建築物には土台が大切ですが、棟を築くためには、柱がどうしても必要です。そして神殿が帝国により破壊される様は、柱を持ち去られるということの内に描写されています。
カルデア人は主の神殿の青銅の柱、台車、主の神殿にあった青銅の「海」を砕いて、その青銅をことごとくバビロンへ運び去り、壺、十能、芯切り鋏、鉢、柄杓など、祭儀用の青銅の器をことごとく奪い取った。(エレミヤ52:17-18)
イスラエルの神殿の中核を形成していたものが「柱」であったと理解してよいでしょう。主は雲の柱、また火の柱として、間違いなくイスラエルの民の中心にそびえており、共同体を覆うことを可能にしていたということです。主は民を導き、民を覆います。民を守り、民にそこから呼びかけます。これは、新約聖書において、「柱」というシンボルがどのように扱われているかを見ることによっても、知ることができます。
また、彼らはわたしに与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目されるおもだった人たちは、わたしとバルナバに一致のしるしとして右手を差し出しました。それで、わたしたちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。(ガラテヤ2:9)
これは教会の中心人物を示す表現です。これは私たちも普通に使うような、ごくあたりまえの言い方であるとも理解されます。しかし、教会の中心人物でなく、神の国を構成する教会そのものにこの「柱」という見方を重ねる箇所もありました。
行くのが遅れる場合、神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいのです。神の家とは、真理の柱であり土台である生ける神の教会です。(テモテ一3:15)
私たちは個人的にも教会の柱となりうるかもしれませんが、この教会は神の国の大切な柱としてここにあるのだ、というわけです。これは地上における働きだけを指していると見られるかもしれませんが、永遠の都なる神の国においても、教会なり信徒なりが、神殿の柱となりうることを、黙示録が告げていました。
勝利を得る者を、わたしの神の神殿の柱にしよう。彼はもう決して外へ出ることはない。わたしはその者の上に、わたしの神の名と、わたしの神の都、すなわち、神のもとから出て天から下って来る新しいエルサレムの名、そして、わたしの新しい名を書き記そう。(黙示録3:12)
私たちは慰められます。人として、教会として、神の国にはべらせて戴くというばかりでなく、そのなくてはならない「柱」として用いようというのです。
主が「柱」となって私たちを導くこと、またこの私たちも「柱」となりうる慰めを得ました。ところがここで、思い返したいことがあります。あの「ヨセフの骨」です。いくらイスラエルのアイデンティティに関わるとはいえ、誰がどのように保存していたのか、どう覚えられていたのかいまひとつ不思議でしかなかった、ヨセフの骨についての言及を、いま私たちはどのように受け止めればよいのか、ひとつの視点を与えられたと考えたいのです。
13:19 モーセはヨセフの骨を携えていた。ヨセフが、「神は必ずあなたたちを顧みられる。そのとき、わたしの骨をここから一緒に携えて上るように」と言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。
私たちもまた、ヨセフの骨を携えているかどうか、問われているように感じました。ヨセフは民族の父祖でした。歴史的な重みを含みつつ、言い遺された言葉を受け継いで、その骨への願いを叶えるべく、歴史のつながりの中に入っていくだけの意義をもつことを考えることも必要です。しかし私たちはそのようなつながりを保証するような「骨」をもつわけではありません。
いえ、もつ必要がありません。歴史の重みを抱えるとはいえ、それはあくまでも人の骨。ヨセフは人に過ぎません。また、骨という形になってしまったならば、それは所詮人のものでしょう。私たちには、生きているイエスがいるはずです。生きているイエスの霊が共にいて、私たちを外から助け、また私たちの内から支えています。「わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」(マタイ28:20)と宣言したイエスの言葉のままに、「わたしたちはいつまでも主と共にいることになります」(テサロニケ一4:17)とパウロも認め、世の終わりにおいても「小羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた、勝利を収める」(黙示録17:14)というように、つねに神が共にいることを以て歩んで行くことが許されているのです。
イエス・キリストの救いを与えられた私たちは、ヨセフの骨ならぬ、イエスの霊を携えて、柱を導きとし、柱とされて、昼でも夜でも歩み続けることができるようにされています。その歩みには、迂回もあるでしょう。思いもよらぬ回り道を強いられるかもしれません。けれども、主が先立って行きます。私たちはこの主を見上げていればよいのです。
「主は雲の柱のうちに幕屋に現れられた。雲の柱は幕屋の入り口にとどまった」(申命記31:15)というように、雲の柱は、モーセが死ぬときにも現れています。主は私たちが生きている限り、忠実に私たちと共にいてくださり、言葉を投げかけてくださいます。私たちはその呼びかける言葉を聞き、従っていくことだけが求められています。イエス・キリストの救いを携えて、いまここから歩んでいくのです。

