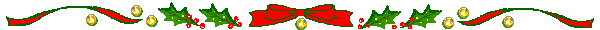|
たかぱんは、 どうして聖書を信じるようになったのでしょう? |
|---|

|
たかぱんは、 どうして聖書を信じるようになったのでしょう? |
|---|
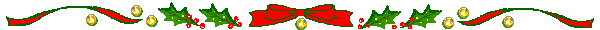
中島義道さんの『生きにくい……』という本を、2001年秋に読みました。
中島さんは、知る人ぞ知る、風変わりな(だけ余計だとご本人から叱責を受けそうですが)哲学者です。小さなころから、「死ぬのはいやだ」と叫び続け、その問題を考え続けて、哲学者として生きているのだそうです。
誰でも、そうした叫びはもつことがあると思います。けれども、その感覚あるいは感じ方というものに、やけに共感できるところがあるのは、たかぱんもまた、哲学を志したことがあった点で、中島さんと近い道筋にいたのではないか、という気がするのです。

数学が面白いと思っていました。答えが明確に出るところが、好きだったのかもしれません。真と偽がはっきりしている。それが好ましいだけで、自分は数学を目指すべきだ、と思いこんでいました。
大学入試に失敗して、高等数学の才能がないことを思い知ったとき、哲学という世界があることを知りました。高校で学んだ倫理が、実は自分の一番関心のある事柄だ、と分かったのです。
浪人している間、狂ったように本を読みました。
哲学といえば京都。そういうことを知って、京都へ行きたいと願いました。
大学は、どこでもよかったのです。京都という土地で、そして哲学の伝統を有している大学ならば。
親も無理をして、わがままを聞いてくれました。こうして京都での一人暮らしが始まりました。最初は電話を敷くお金もなく、一月に一万少しの食費でやりくりする日々が続きました。家庭教師の口もみつかり、生活は助かりましたし、一方でかなりまじめに哲学の「お勉強」を続けました。

口先の理屈ばかりを身につけるために、哲学をしたというわけではありません。もともとは、たしかに切実な動機があったのです。
でも、一方で、人を平気で傷つけていられる自分というものにさえ、気づいていませんでした(今がそうでないという意味ではありませんが)。
人を傷つけたことを、やがて痛感したとき、死にたいとさえ思いました。あれほど、死にたくないという思いから、ここまできたのに……。

ある秋の日のことでした。ある偶然なことから、友だちが、勧めてくれた本がありました。三浦綾子さんの『帰りこぬ風』という文庫でした。看護婦である主人公の日記形式で、つらいことに遭いながら、聖書の言葉から一つの真実を悟るというものでした。三浦さんは、クリスチャンとして、聖書に従う人の生き方を中心に執筆していらっしゃった作家です。その三浦さんにしては、聖書をそう全面に出さない、控えめな作品だと思いますが、それでさえ、キラリと光る聖書の言葉は、渇いた心にはしみこみます。
聖書を読もう。
そうです。西洋哲学は、考えてみれば、聖書を下敷きにして展開していた歴史があったはず。なのに、聖書など、短い新約聖書でさえ、一度たりとも全部を読んだことはありませんでした。
せめて、教養としてでも、読む価値はある。
不純な動機も混じりました。でも、とにかく手に取ったことが、始まりでした。それは、高校のときに、国際ギデオン協会(ホテルや学校などに、無料で聖書を配布している団体)からもらった、新約聖書でした。

初めは、よい教えというふうで、心が洗われるような気持ちで読んでいました。まだ気楽でした。お酒片手に読むような態度でした。
ところが、ぱらぱらと見ていたある日のことでした。(引用はギデオン協会の聖書から)
愛は寛容であり、愛は情け深い。 また、ねたむことをしない。 愛は高ぶらない、誇らない。 不作法をしない、自分の利益を求めない、 いらだたない、恨みをいだかない。 不義を喜ばないで真理を喜ぶ。 そして、すべてを忍び、すべてを信じ、 すべてを望み、すべてを耐える。 愛はいつまでも絶えることがない。 コリント人への第一の手紙13:4-8
頭をハンマーで殴られたような気持ち、というのは、このようなことをいうのでしょう。
だって、これらの文の主語である「愛」を、自分の名前に置き換えてみてください……。
自分はそれまで、人を愛し続けていたつもりでした。ところが、とんでもない。ここに自分の名前を入れると、恥ずかしくて読み進めることができません。自分は、愛とは正反対のものであると、突きつけられたのです。
愛がない。自分には、まるで愛というものがない。
だから、せめて、誰か一人でも、愛することができますように。
初めて、祈った日でした。

旧約聖書のついた、日本聖書協会の、いわゆる口語訳聖書を購入し、最初から読むことにしました。
天地創造の話が終わったところで、またも頭を殴られます。(引用は口語訳聖書)
あなたはどこにいるのか。 創世記3:9
哲学を使って考え抜いて、最近注目し始めた視点への考察が、この一言に盛り込まれていました。と同時に、いったいそのおまえ自身は、どこにいて、何をしているのか、と他者(神)から問いつめられたとき、もう、逃げ場はありませんでした。
神の前に、一人みじめな姿でたたずむ、ちっぽけな存在に過ぎない自分を、痛烈に自覚させられました。
たかぱんは、教会に足を向けていました。クリスマスの準備が始まった頃でした。

たかぱんが命を吹き込まれた言葉やエピソードは、まだほかにもあります。ここでは、ほかの人にご迷惑をかけにくい部分を、紹介させていただきました。
聖書には、神は愛であると書いてあり、キリストを信じた者には永遠の命を与えると書いてありました。たかぱんには、それが深く心に刻まれました。
わたしは道であり、真理であり、命である。 ヨハネによる福音書14:6
イエス・キリストの言葉です。