美談に潜む二つの問題
チア・シード
詩編51:1-19
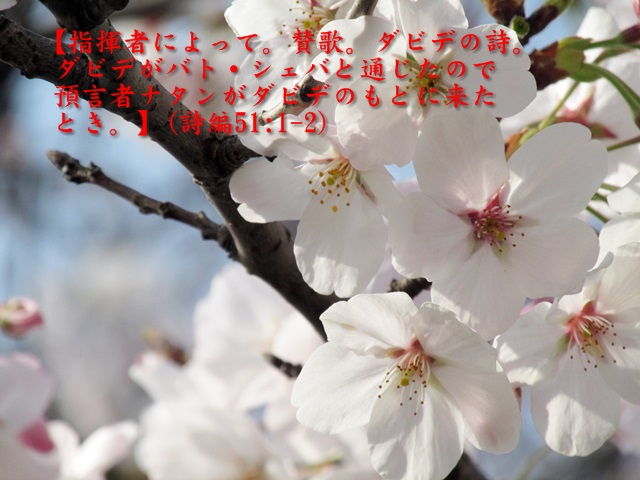
末尾の2節を採択しなかったのは、ここが後の付加部分だと思われるからです。ダビデの思いは19節までで一度完結しているので、そこに集中して捉えてみようというわけです。するとこれは感動的な悔改めの詩であり、どうしようもないダビデの姿が描かれると共に、それを美しいと感じてしまう感傷的な心が起こりがちでもありましょう。
しかしここには、二重の意味で問題を覚えるのです。ダビデのこの詩のストーリーは、イスラエル人にとり周知のものであったことは間違いありません。ダビデが如何に人気のある王であり、その王家の血筋が守られたとはいえ、基本的な十戒のうち大きな二つを破っていることについて、これくらいの悔改めで、それを許してよいのでしょうか。
きれいごとを並べた並べたからといって、あのダビデだもの、仕方がないよね、で済ませてよいのでしょうか。もちろん、これを神は結局赦しています。ダビデはやはり神のお気に入りなのです。神の選びに文句をつけるのではありません。けれどもこの詩は「ただあなたに私は罪を犯しました」からその罪を取り払ってください、と願っているに過ぎません。
いったいこれが罪というものなのでしょうか。ここには、私たちが思いも及ばぬ罪の概念が潜んでいるようです。つまり、罪とは神との関係のことをいう、ということです。人や事柄に対する行為の内容云々のことではなく、ダビデの場合でも、ウリヤに対するものは罪とは呼ばない、別の事柄であると考えざるをえないのです。神との関係というものは、それほど私たちの甘い倫理からは遠いものなのです。
もう一つの問題は、これがダビデの事件の詩である、と表題に掲げられ、あの事件のことだと明示されている点です。確かにそれはあの事件にまつわる思いでしょう。痛ましい事件でした。そして犯したダビデ自身、胸がちぎれるような心になり、それに私たちも同情したくもなるものです。あるいは、ダビデを断罪したくなるかもしれません。
しかし、これらはいずれも、この詩をダビデの出来事だと定義し、自分とは無関係な出来事として突き放して距離を置いて見てしまうことを意味します。読者、後の時代のこれを目撃する者にとり、この事件はしょせん他人事であるということになってしまうわけです。私たちはどこか醒めた目で、この詩を見渡すのではないでしょうか。
これはダビデのこと。自分のことではない。そういう意識をもつ私たちは、自分と神との間の関係に逃げ道を用意してしまいかねません。確かに私たちは聖書の物語を、自分のことのように読むでしょう。しかし「ように」が付いた時点で、それは自分のことではないことを前提することになります。そうではなく、これは自分のことである、と根底に置きたいのです。


