逃れの町の現代的意義
チア・シード
民数記35:9-15
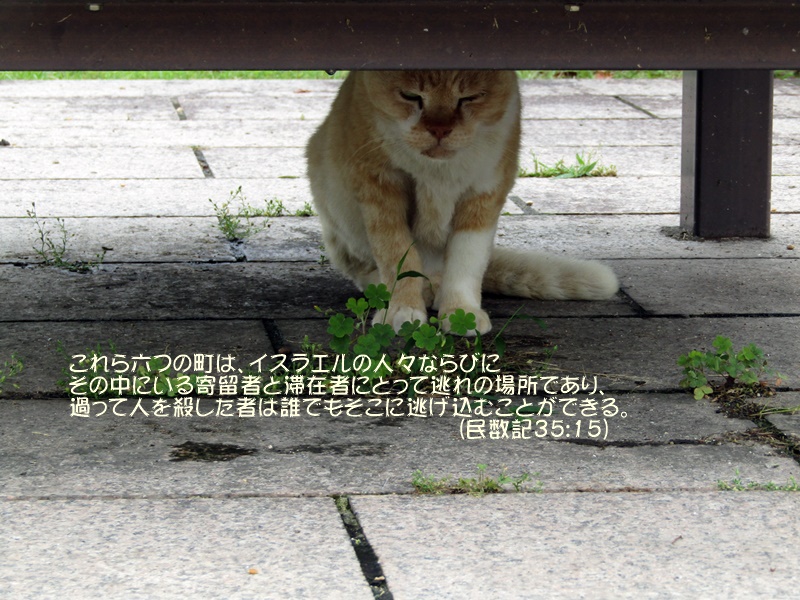
逃れの町については、これまでも幾度か見てきました。過失致死犯を、復讐から保護し、正しい裁判を行うための措置です。民数記ですから、出エジプトの旅の中でモーセに与えられた律法ということになっていますが、内容はカナンの地に入ってからのものです。それでも、実際にそうした町の規定は後にあったものだとして受け止めておきます。
過失であるのに、被害者の親族などから、天誅とばかりに復讐の手がなされるならば、神の正義が冒される可能性があります。目には目を、という規定を、復讐は超えて実行する危険性があるからです。中東で一般的だった同害刑法も、このイスラエルでは、必要以上の復讐をすることへの歯止めとなっていたかもしれません。
この逃れの町もまた、人間の感情の暴走への手立てとして設定されたとすれば、なかなかの知恵です。但し、それが即座に無罪とすることではなく、裁判は受けなければなりません。判決が出るまでの間、超法規的な仇討ちから守るというだけのことでしょう。ただ、ここで注目すべきは、その規定の対象です。イスラエルの人々だけではないのです。
見ると、寄留者と滞在者も、この保護の内に含まれていることが分かります。過失致死の場合、身を守られるという規定は、こうした外国人でも適用されるというのです。日本の場合、そうなっているでしょうか。出入国管理局の監視は、大切な仕事です。それにより元来の国民は守られており、厳格に働いているからこそ、国民は安心して生活できます。
身分証明のない外国人滞在者に対しては、厳重に対応してもらわないといけません。それは必要です。けれども、それが行き過ぎてしまう懸念もあり、実際の問題も起こりました。イスラエルの当時の管理は、もちろん現代のそれとは違うわけですが、旅人をもてなすのが当然という文化を考慮に入れても、やはりなかなか驚くべき規定だと思います。
現代の法にも通ずるような、こうした規定があったことを思うと、社会の運営に関しては、古代も現代も、そう特別に変わったことがないように思えてきます。聖書からも、法や政治について、まだまだ直接学ぶべきところが多いのではないでしょうか。まして、人の生き方に関しては、神は変わらぬ導きの手を伸ばしているに違いありません。


