驚くべき信仰に応えた
チア・シード
マタイ8:5-13
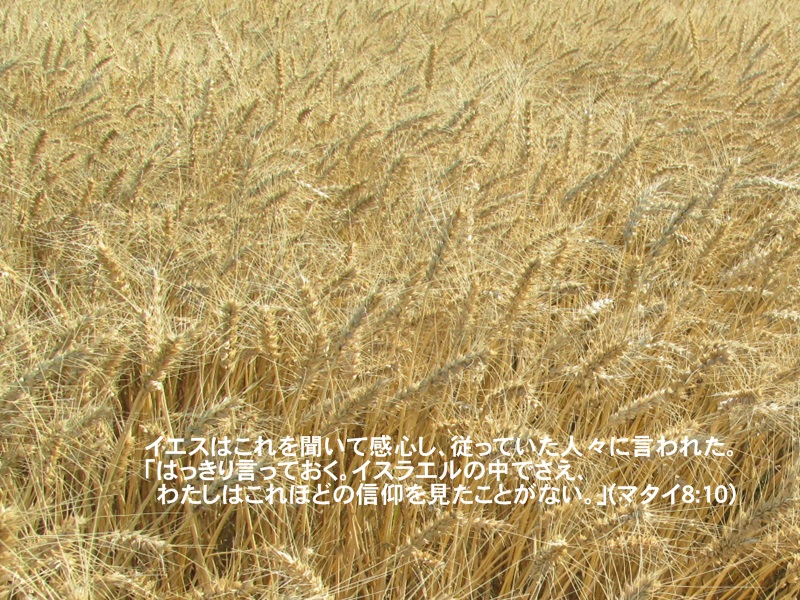
イエスが癒した実例をマタイは並べます。百人隊長が近づいてきたとき、ある種の緊張感が走ったのではないでしょうか。当局が目をつけてケチをつけにきたとも思われるからです。しかしその言葉は、懇願でした。英語を習ったとき、「懇願する」や「嘆願する」といった訳語の語を、辞書で幾度引いたことでしょう。神に対する構え方がたくさんあったのです。
赦しを願う機会というのが、生活の中でも多々あったことが偲ばれます。百人隊長はユダヤ人ではありません。異邦人が助けを願ったのです。これに対して、イエスは実にすんなりと受け容れます。では行こうではないか、と歩み始めようとするのです。ところがここでこの百人隊長は、意外な反応を示します。主をお迎えするような家をもってはおりませぬ、と。
それよりも、言葉を下さい、と百人隊長は求めました。言葉さえ戴けたら、我が子は生きるのです。これはきっぱりとした断言でした。勢いある発言です。まるでイエスの口から出てきてもおかしくないような信仰の言葉です。しかし普通の人間、まして異邦人の口から出てくるというのはどうでしょう。洗礼者ヨハネならあるかしら。弟子たちは無理でしょう。
弟子たちがこんなことを言えるようになるのは、使徒言行録に入ってからのことです。この百人隊長、権威の下にある自らの規律が、神の法の下にもパラレルに起こっているはずだ、という信頼を寄せました。そしてイエスが、それを呼び起こすことのできる方だと信用したのでした。イエスは驚いたといいます。なんということでしょう。イエスの驚きとは。
イスラエルの中に、これほどの信仰がかつてあっただろうか、と最高の賛辞を贈ります。そこから示すのは、ユダヤ人たちに分かりやすかろう終末のイメージ。いつか神の大宴会が開かれ、広い世界から大勢の人が来て、この宴会に加わるだろうと言ってのけます。けれども、イスラエルにただいただけのような者はそこから追い出されるだろう、とするのです。
厳しい仕打ちです。別のシチュエーションでは明らかに「裁き」として持ち出される内容です。イエスは、神の招きに応じないイスラエルのエリートたちの姿にも、別の意味で「驚いた」のかもしれません。百人隊長の子は、もちろん癒されました。彼の信仰の実現が、神の言葉によってなされたのですが、イエスの驚きは、いま祝福となったのだと思います。


