分断の先にある平和を思う
チア・シード
マタイ10:34-39
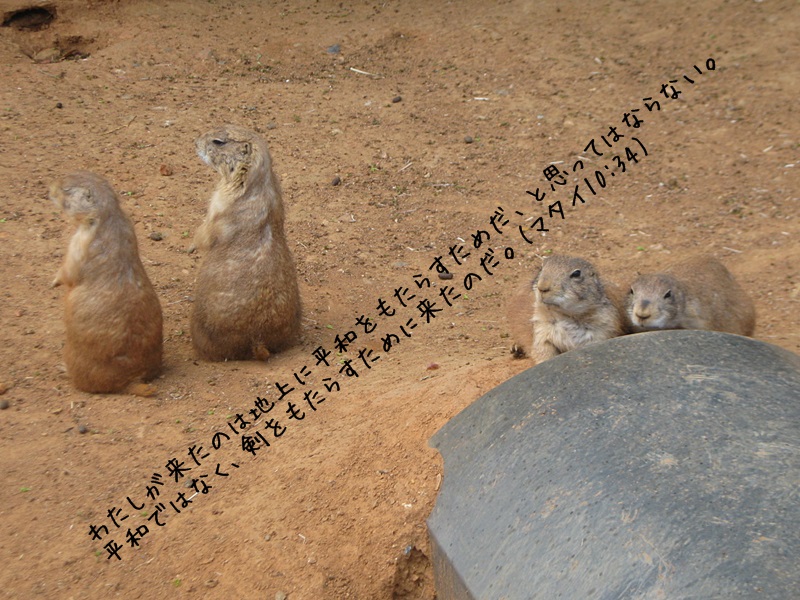
イエスは十二人を選びました。イスラエルの部族を救うという意図がそこにあるのかもしれません。派遣における心がけも教えました。これは、後の世代の伝道へのアドバイスにもなりえました。だとするとそこには迫害が想定されていたことになるでしょう。それでも、ただの人間は恐るるに足る存在ではないとするのでした。
マタイは、イエスの口を通してそのように伝えます。そもそもイエスは、この世でなあなあの妥協の平和を実現することを目的としてはいません。イエスのもたらす平和は厳しいものです。そして徹底したものです。シャロームという言葉を思い起こします。平和を意味しますが、何もない様子というよりは、戦い取った平和のイメージがあるといいます。
イスラエルの歴史は、戦い取る平和の積み重ねでした。現代でもきっとそうでしょう。厳しい自然と周辺民族との関係から、そのようになったのでしょうか。イスラエルはこれを神により正当化された戦いだといつも認識しています。イエスもまた、いま現れた背景には、人々を敵対させるためであったのだと漏らしました。
現代の、分断の世界を考えるに相応しいテーマではないでしょうか。政治的にもそうですが、感染症の時代には、物理的に距離をとり、人々の連隊を断ち切り、互いに非難を浴びせ合うような世界となり、それが一層はっきりしたとよく指摘されますが、元来この世界には、それがあったと捉えることはできないでしょうか。人は本来そうなのだ、と。
パウロが、コリントなどの教会に、どうしようもない分裂や不和を見ており、異端の混入に抵抗し、帝国の圧政と脅威に刃向かうような思想をもちえたとすれば、ただの観念的な信仰の出来事であるだけではないと思われます。パウロはもたなかったにせよ、家族というものすら、無条件に一体となっているべき存在であったのではないと思うのです。
この分断の本質を生きぬくためには、己れの十字架を背負う者です。イエスがその先頭を進みます。なあなあの表面的な平和は要りません。命を得るというのは、イエスに従い、そこに命を預ける者だというのです。さあ、平和とは何でしょうか。私たちにとり、それを受けるための戦いとは何でしょうか。私たちは誰と戦うべきなのでしょうか。


