禁ずるべきか許すべきか
チア・シード
マルコ3:1-6
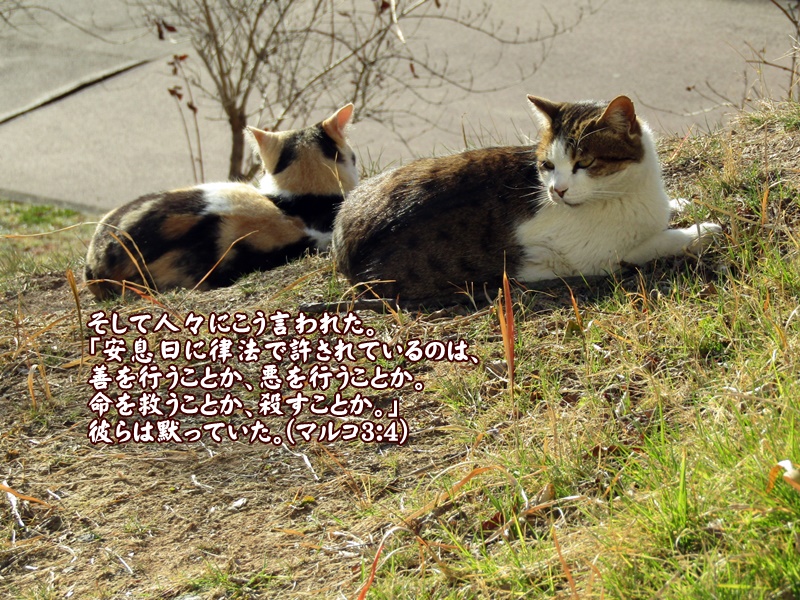
安息日に麦の穂を摘んだことが仕事をしたと見られ問題となったのですが、あの出エジプトの時に、七日目の安息日にマナを拾い集めたことへの非難が重なって考えられたのかもしれません。その後ここでは片手の萎えた人を癒やしたことが問題となります。ここにはさらに、人道的な配慮が関わってきているようにも思われます。
人を助けることについては、安息日か否かは区別できない、そうではないでしょうか。正にイエスが自ら言ったように、安息日に律法で許されているのは、善を行うことであるでしょうし、命を救うことであるはずです。人々の視線に応えたのかもしれません。安息日に禁じられていることだ、と思い込んでいた人々の白眼視に。
イエスは、もちろん許されているという方を貫きます。神の律法は、禁じることが主眼だったのではないのです。制限することで逆に許すことだったのです。私たちはこれを学びます。働いてはいけないという制限は、休むことを許すことになります。私たちの社会は、特定の人を休ませないように動いてはいないか、振り返ってみましょう。
一方、この状況は、イエスが会堂に入ったところから始まっています。安息日に会堂に入るのは当たり前のように見過ごしますが、そもそも話をするためだったのかどうか、考え直す必要があります。ラビが立ち上がって話をするという習慣があったとするなら、いわゆる説教をする心づもりであったのかもしれません。
好ましい人が比較的自由に語ることができたという話を聞いたことがあります。イエスがこの時語ろうとしたのかどうかは分かりません。今で言うなら、教会の礼拝に来たら、身体の不自由なところのある人がいます。その人に呼びかけ、皆に見えるような場所、つまり会堂の中心に連れてきます。周りの者たちの刺すような眼差しが分かります。
イエスはそうした場面で、安息日に許されていることは何か、という問いを発したのです。人々は答えられません。安息日の禁止事項しか頭にないわけです。でも、人道的に助けることそのものが悪だなどということはできないのだと気づきます。こういうとき、イエスを責められないし、仲間の視線もありますから、皆が沈黙することになります。
この沈黙が、イエスの怒りを呼ぶことになります。はじめからイエスを陥れる企みでしかなかったのです。でも、人間の良心というものをイエスはある意味で信じています。だからこそ良心とのジレンマを起こしたのです。けれども、人間はどこまでも醜い。自己反省は重んじず、イエスへの憎悪ばかりが膨れ上がっていくことになりました。


