敵を愛する教えの転倒
チア・シード
ルカ6:27-31
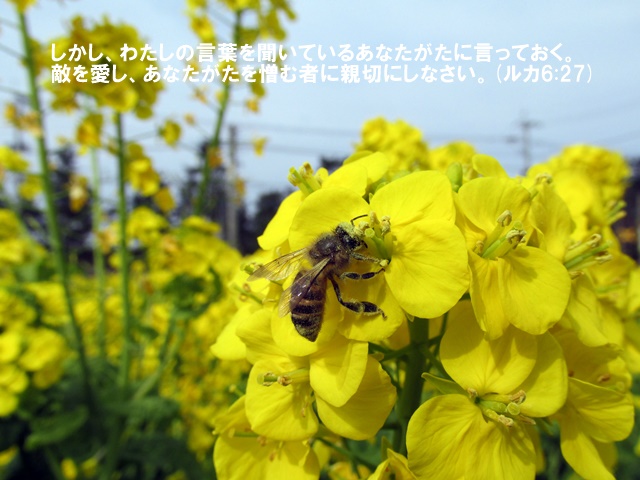
愛敵などと呼ぶことがあります。気軽に人は名を付けます。名を呼ぶことにより、その対象を支配することができるという考えが古来ありますが、名付けることでなんとなく愛敵ということが分かったような気がするのかもしれません。「わたしの言葉を聞いている」者にイエスは言いました。聞かない者には言っていないことを押さえておきましょう。
神の言葉を聞くところにこそ、愛敵の考えが告げられたのです。まず敵を愛せという命令から始めると、ルカは具体的に、憎しみを向けてくる者に親切にせよ・呪ってくる者を祝福せよ・侮辱してくる者のために祈れ、と畳み掛けます。これらは、目には目を、ように応報の原理を避けるという共通目的があるように感じられます。
どうして応報がいけないのでしょう。同じものを返さないのは何故か。それが悪だからです。悪には悪を以て返礼してよいのだ、と私たちは考えやすいのです。それを論理的にも正しいとみなしてしまう傾向性が私たちにはあるのです。イエスは、敵を愛するという概念の中で、この論理を徹底排除しているのです。
また、ここまではこちらが思いも寄らないものを相手がもたらす場合でした。しかし、ここからは違います。頬を打ってくる者に別の頬を向けよ・上着を奪おうとしてくる者には下着をも与えよ・持ち物を奪おうとしてくる者には何でも与えてしまえ、というのは、相手の望むようにしてやれ、という内容なのです。
他人のものを奪おうとすることは悪かもしれませんが、もし物を求めようとしているだけなら、必ずしも悪だとは言えません。ルカの視点はこの後、お返しできない者に与えていくようにシフトされていきます。ここまではともかく、相手からすれば予想外の反応がくることと、要求した物をまんまと手に入れることとが並べられていたことになります。
これらは多少見る角度が違っているように思えないでしょうか。しかしなお問います。ここまで、イエスの言葉を聞く者は、描くシチュエーションでは常に被害者の立場にありました。キリスト者は当時、迫害などにより、ずっと被害者の側にあったということは確かです。だから、このイエスの言葉を被害者側から見るのが自然であったと思われます。
しかし、歴史的状況は変わります。キリスト教はむしろ加害者となることが多くなりました。今や増えすぎて社会権力をもつようにさえなって、そしてまたこの私もまた、他人を憎み、呪い、侮辱しています。他人の頬をうち、その上着を奪い、持ち物を搾取しています。人がしてもらいたくないことを、平然としている者になっているではありませんか


