主の日は近い
チア・シード
ヨエル2:1-3
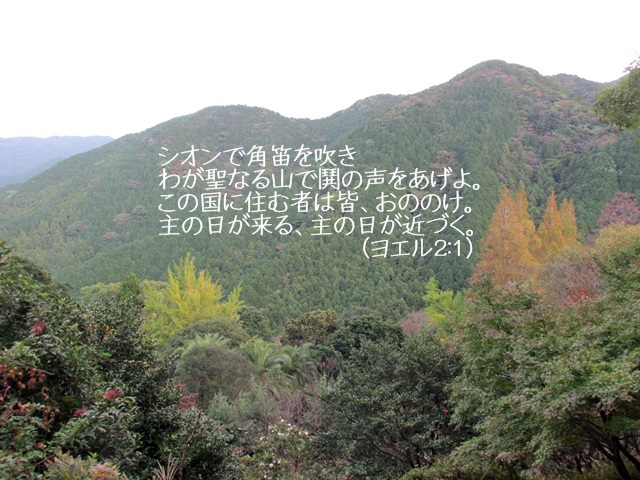
シオンを見つめる預言者の目に映るものは、すでに廃墟となった、かつての都の姿でした。エルサレムは誇らしげにその丘に佇んでいたのでしたが、ついにそれは崩壊してしまいました。なんだ、事後預言か、と見下す人がいるかもしれませんが、「主の日」がもう過去のことでしかない、と認めてしまうことは危険なのではないかと思います。
「主の日は近い」というのは、これから先のことなのではないか。預言者がこれを言った、あるいは筆記したとき、繁栄していたにも拘わらず主から離れてしまい、不穏なムードの中にあった時代に身を置いて、バビロン捕囚へとつながる一連の出来事を「主の日」と呼んだとしましょう。でも、その歴史を記したのだ、としたのでは片づかないはずです。
事態がここにあった、それだけのものでしかなかったのだとしたら、このようなことが古より起こったこともなくこれから後も起こることはないだろうなどと、預言者が言ったその暗黒の日は、過去のことでしかなく、私たちはもう破滅をこれから経験することはないのだ、ということになってしまわないでしょうか。
エデンの園ももはや再起不能な荒れ野となると告げています。唯一無二の出来事があると言って、それを「主の日」と呼んでいるのですから、私たちは今どこにいるのか、私たちが今これを目にしているのはどういうあり方の中においてなのだろうか、と考えることが求められているように思います。
つまり「主の日」がもう終わったことであるのなら、私たちにはもう信仰するものは何も残されていないことになります。私たちは抜け殻なのでしょうか。生きてここに立っているのではない、ということなのでしょうか。もう震え戦くことすらない、無為な時がただ流れる中で呆然と立ち尽くしているだけなのでしょうか。
「主の日」がもしまだこれからもある、否これからこそあるのだ、と構える捉え方をしてよいと思うし、そうあらねばならないとさえ思うのです。その笛を吹き鳴らし、聖なる山で鬨の声を上げるものが必要とされています。逃れうる者が一人もいないその日が、これからきっと起こります。それが、先の見えない人生の生き方ではないでしょうか。


