敵の存在理由
チア・シード
士師記2:16-23
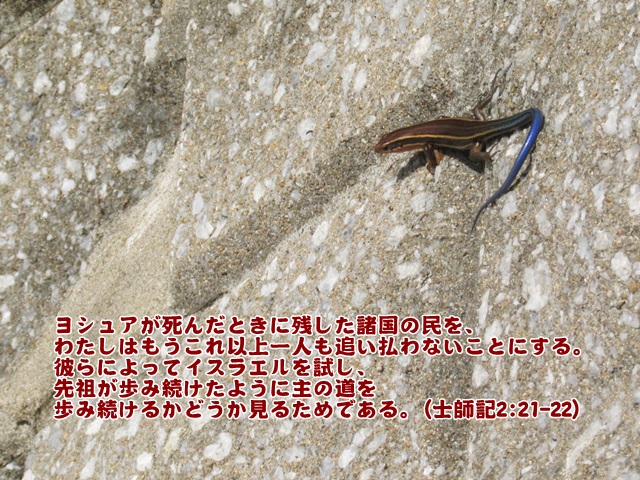
ヨシュアが死ぬ。モーセからヨシュアと絶大な力を見せつけていた英雄がいなくなり、イスラエルは飼い主のいない羊のようになりました。もはやかつてのまとまりを保つことができなくなったのです。そこで、士師記となりました。さばきづかさとも訳される士師により、イスラエルは揺れ動きながらもなんとか統率されていくのです。
この後オトニエルに始まり、エフド、さらにデボラなどの名をもちだしつつ、ギデオンへと続いていく士師の系譜は、その叙述に、定型的な繰り返しを必要としています。すなわち主の目に悪とされることを民が行ったため、主がイスラエルを苦しい目に遭わせます。民が主に救いを求めて叫ぶ主が士師を起こしてイスラエルを救うという歴史です。
しかしそれでイスラエルは安心してしまい、再び主を離れ、元のループに戻ります。具体的に幾人もの士師のエピソードがこの後語られていき、だからこそこれが士師記と呼ばれるのですが、このルーチンの繰り返しをイスラエルは幾度も経験することになります。それをまとめて予告するかのように、記者が予め提示しているのが、当該の聖書箇所なのでした。
士師が死ぬと、前よりも一層ひどい具合に主を捨てて他の神々に従うようになるイスラエル。主は怒りの炎を燃やします。契約に従わず、主の声に聞き従わなかったではないか、と責めます。カナンの先住民族もコントロールするのがこの神です。偶像の神々が周辺にある中で、イスラエルはどうするか、テストするためだというのです。
敵となる民族を、神は安易に駆逐してしまわない。目の上の瘤のように、人には快く思わない存在、苦手な相手、妨げとなる存在があるものです。どうして神はこんな妨害となるものを私の前に放置しておくのだろう、と忌々しく思うことがあるかもしれません。きっと何か理由があってのことだと、信仰の励ましのメッセージとなることがよくあります。
しかし本当にそうでしょうか。私こそ、誰かにとって妨げそのものではないでしょうか。主にとり私こそが、忌まわしいものとしてここにあり、しかも存在を消されずに赦されているとしたら。憐れみにより生かされているだけの者なのでは。そんな私が、イスラエルの民はなんて愚かなのだ、などと嗤うどころの話ではないのです。


