神の言葉の光を受けて
チア・シード
出エジプト34:29-35
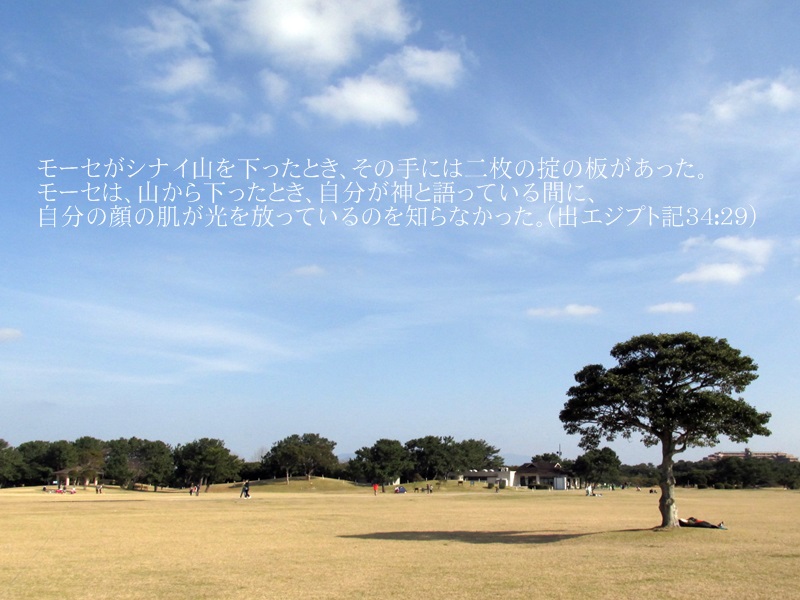
十戒を初めとした律法規定が、どこまで告げられた物語にリアリティがあるのかが問われるかもしれません。後にカナンの地に入ってからの規定が、荒野でこんなに飛び交うはずがないなどと言うと、ついには果たして山で神から石板をもらったなどというのは本当かと疑われ、その他の細かな規定はずっと後の時代のものなのだろう、などと。
しかし、イスラエル民族にこのようにして法が与えられたことの根拠が、こうした物語で与えられたのだ、という点を疑う必要は何もありません。モーセが単独シナイ山へ神から呼ばれ登ったのだ、という権威。いろいろあったけれども、律法のうちの十の言葉を刻んだ証しの板を手に持って、モーセは山を下りてきます。
古代の訳し間違いがここに指摘されます。モーセに角があったとラテン語訳で信じられ、そのためミケランジェロのモーセ像には立派な角が生えることとなりました。光という語を角と訳してしまったとされています。聖書協会共同訳では、この「角」を別訳として、ウルガタ訳がそうだと示していました。親切な解説ではあります。
しかし、そうなると他の語の別訳なるものもまた、間違いのことであるのか、単に原文が異なるだけなのか、私たちは判断に困ります。このモーセの顔の光であるが、私たちは世の光であるとイエスが知らせてくれたことを思い起こします。主の戒めをもつ私たちもまた、このモーセのように光を放っているのでしょうか。放っているはずです。
モーセ自身、その光に気づかなかったように、私たちも自分ではそれが分かりません。モーセのように私たちは主が自分に語ってくださったことを、悉くひとに語ることができているでしょうか。だからこそ実は光があるのだなと覚ることもできることがあるのかもしれません。モーセの顔の覆いにも、きっと何か意味が当時あったのでしょう。
パウロは第二コリントで、キリストに譲らねばならない旧い律法を象徴して、モーセは顔に覆いを掛けたのだなどとしているのは、およそ出エジプト記の描き方とは異なるものでありますが、ここでモーセは神と人とに語る時、つまり神の言葉に関わっているときには、覆いが外されていたらしいことに注目してみたいと思います。
私たちが神との間に、神との関係の内にある差し向かいの心を持ちたい気持ちが与えられるのが、その意味だと見ました。光の中を歩めと言われて、私はためらうことがあります。でも、今日も言葉を受けようと思います。その思いに迷いはありません。自分はとてつもなく頼りないあかんたれですが、光はきっとあるのだ、と神を信頼しようと思うのです。


