共にいる神の示す道
チア・シード
出エジプト33:12-16
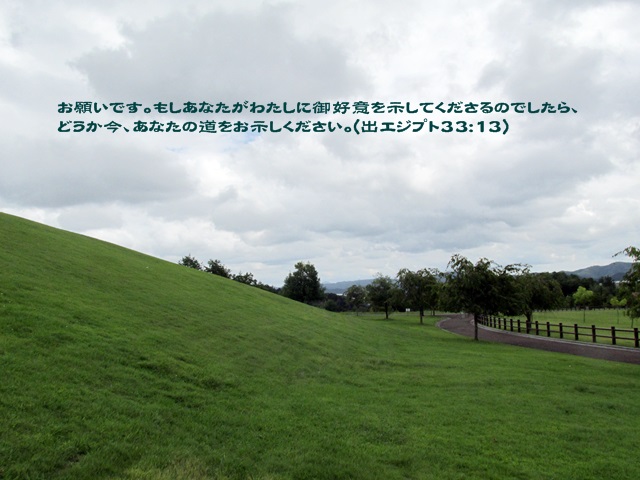
会見の幕屋は、モーセと主とが話をする処として用意されていました。モーセは、主が自分を選んだと聞いており、それを信頼したいと思っています。イスラエルの民をエジプトからカナンの地へ導くのはおまえだ、と指名されたことを信じたいのです。モーセの運命は主に変えられました。ただモーセは、共に遣わされる者がいてこその旅だと主に訴えています。
さらにモーセは続けて、主の道を示してくださるようにと願います。自分が率いる民が主の民であり、確かに自分は主に望まれて立てられているのだという確信を得るためには、主の道が明確に示されることが必要だというのです。旅には伴う同行者が必要だと考えていました。旅の道を知る者が助けてくれないことには、進めないと感じていたのです。
モーセは、「共に遣わされる者」ということで、この「主の道」とほぼ同義のように捉えていたのでしょう。旧約聖書続編のトビト書で、旅するトビアに同行する、実は天使ラファエルが必要とされたように、道を知る者がないと困るというふうに訴えるのです。そこに主の道があります。そして主の教えること、主の掟も、そこに含まれているものと思われます。
この道を知ることは主と出会うことであり、主の民として生きることでもあったはずです。そのような脈絡で理解したいと思います。「道」とは文字通りの道だけの意味では済まないでしょう。私たちは今「キリスト教」とか「信仰」とか言いますが、新約聖書の中ではこれを「道」と記者は記しています。生きる縁、進むべき指針をいま「道」としています。
主はモーセの願いに対して、「主自ら共に進む」ことを告げます。それがモーセの安息となるのだそうです。これはモーセにとり安らぎである、安心材料である、ということなのでしょう。モーセは主の同行なしには進めないと訴えます。それにより民が主の目に適うものであることが分かります。不自然なやりとりは、ある種の交渉をしている故なのでしょう。
主が道を示し、旅につねに共にいてくれること。モーセはこの約束を取り付けました。だったら自分が選ばれたということもよく理解できるのです。ここにはもちろん、インマヌエルの思想が芽生えています。それはモーセの記録を綴る中で後から適用しているというのかもしれませんが、主がイスラエルの民と共にいると信じることが、民の原動力となります。
主こそが主の道であり、イスラエルの進む道であることをはっきり示すことで、主と出会うこと、主と豊かな交わりを果たし、その関係の中に生きることがどういうことであるのかを、はっきり教えてくれることになります。私たちも、このモーセのように、神を語ることが許されています。主が、イエスが、共にいるからです。


