祝福はいまここで
チア・シード
申命記7:6-15
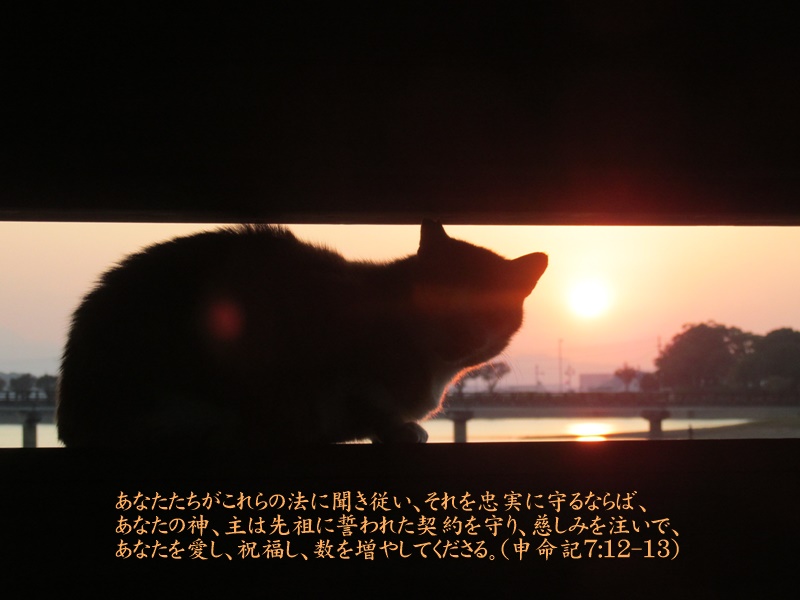
ついに約束の地を目前にして、モーセを通じて主の祝福を、これでもか、とぶつけてきます。至高の喜びを以て、これらの言葉をイスラエルの民は受け取ったことでしょう。と思いきや、この後、千年だか数百年だか後に、イスラエル民族は国家機能を失い、ばらばらになってしまいます。主の聖なる民という名誉ある称号も、空しいこと限りないもの。
小さな民族をこそ主は愛し導いたという希望の呼びかけは、私たちにも慰めとなりますが、歴史的には無力だったということなのでしょうか。この神を真実の神として崇め、従っていたら歴史は変わっていたと思ったかもしれません。祝福の道と呪いの道の分かれ密がそこにあったのは確かでしょう。主の法を守り行えば、その通りになったのでしょうか。
土地の産物や家畜までも、この祝福をふんだんに受けています。その神の言葉に嘘はなかったはずです。ではこれを狂わせたのは何だったのでしょうか。所詮営利に目と心を奪われたイスラエルの民の歴史の中に見出すしかなかったのでしょうか。申命記はしきりに「あなた」と呼びかけます。もちろんそれがイスラエルの民であるはずです。
しかし漠然と塊として、集団として呼びかける民族というものであるのではなく、その一人ひとりに対して呼びかけていると見るのは、いかにも近代的に過ぎるかもしれませんが、やはり問うてみたい点です。出エジプトを果たしたとき、モーセに従った群衆は、やがて一人ひとりの不満を軸に、個人として、また集団として、モーセに刃向かいました。
約束の地を目指す旅を続けてきた人々へ、いま改めてこのメッセージが届けられます。但し、もしこの文書がずっと後の時代になかった。って編集されたものだとしたら、つまり捕囚の中でこれを記したのだとしたら、そこには何が目されているのでしょうか。おまえはかつてこんなにも祝されていたのだと自覚させ、立ち上がらせようとしたのでしょうか。
他方、いま私たちへも投げかけられている問いかけなのだ、と後の読者たる私たちに向けられた問いなのでしょうか。さあ、覚れ、と。いずれにしても、聞く者はここから歩き始めるしかありません。いまここからどうするか。この言葉が命を与え、これからの生き方をどうつくるのか。私たちは常にこの問いかけの中にいることを忘れてはいけません。


