主の祭りを楽しもう
チア・シード
申命記16:13-17
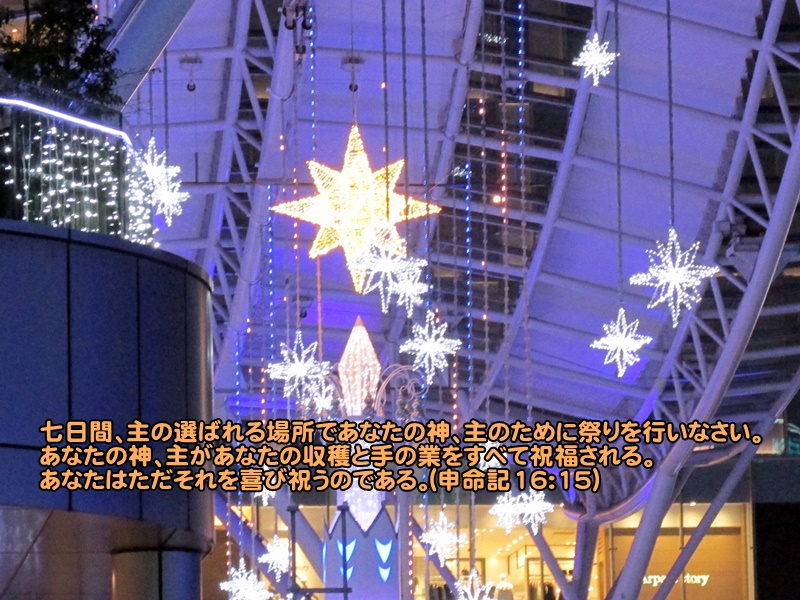
仮庵祭の規定です。荒野で天幕暮らしを強いられたイスラエル民族のスピリットを、決して忘れないための祭りです。当事者であったモーセがこれを決めたと理解するのは無理がありそうですが、それはいまは脇に置いておきます。収穫の時期にこれを行えと言います。この仮庵祭については、楽しみなさい、喜び祝え、と命じられています。
出エジプトの出来事を思い起こす祭りは、楽しみに包まれているべきだというのです。ここの直前の五旬節の祭りも同じでした。神は、かつての歴史が苦しかったことを知らない訳ではないのですが、今は楽しむものとしてそれを記念する祭りを与えていることになります。もちろん、単に思い出が時を経れば美しくなる、というものではありません。
しかも、寄留者や孤児、寡婦らと共に楽しめと言っています。弱い立場の人たちと共に楽しむ祭りであってこそ、人々が心から楽しめるものではないでしょうか。誰かを疎外して、はじき出して行う祭りは、どこか後ろめたくありませんか。そんな気持ちがあると、心から楽しむということは、なかなかできないものなのです。
弱小イスラエルが小さな者であるという自覚を基に、小さな者に心を向けるべきだということを、律法は忘れることがありません。人は、それを忘れてはなりません。それでこその交わりであり、世界でありたいものです。そうして、主がこの収穫をもたらしたこと、祝福して下さることを、心から共に喜ぶ者でありたいと思うのです。
果たして私たちは、心から喜ぶ祭りというものを、いま経験していると言えるでしょうか。クルシミマスなどというのが冗談でなく、クリスマスの時季になると慌ただしく忙しく準備に追われている、そんな教会生活を送ってはいないでしょうか。自分が楽しくても、誰かが楽しめないでいないか、気づくようでありたいと願います。
三つの祭りを申命記は並べ、それをまとめるにあたり、主の前に出なければならない、と告げます。私たちは襟を正されます。何も持たずに出てはならないというのです。祝福を受けたことを贈り物という形で、与える喜びとなっていけばよいですね。主はいつも私たちと共にいてくださいますが、私たちもまた主の前に出て喜びに包まれたいものです。


