どうすればよいのですか
チア・シード
使徒2:37-42
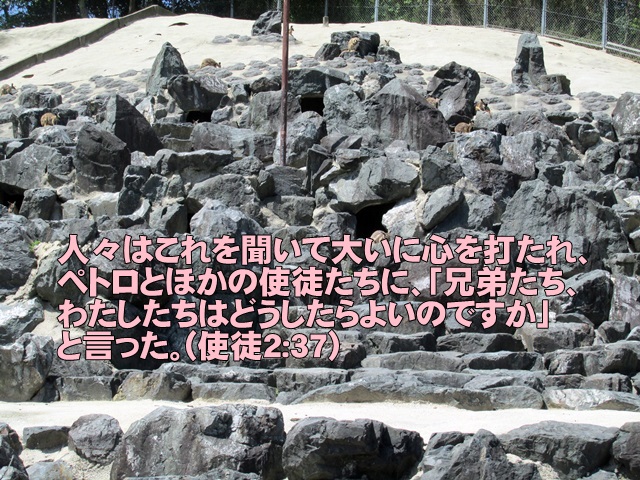
過越祭の7週後、ペンテコステの日の出来事が人々の目の前で繰り広げられる中、これはどうしたことかという疑問が出されました。それに対してペトロが11人と共に立って説教をした、ということになっています。ユダがいないはずなのに、この書き方は疑問が残りますが、さらに疑問は、これほど劇的に変わり、また知識が与えられるのか、というところでしょう。
マルコ伝を見ると、とことん師を理解できない弟子たちであったし、十字架を前にして逃げ出した男たちは、復活のイエスを見てもぼけっとしているような、その弟子たちが、この瞬間すべてを理解し、ペトロが大胆に完成度の高い福音を語った、とするのはいかにも不自然です。しかし、後の世に必要な信仰箇条がまとめられているという意味では、ここはまことに印象的で大切なスペースです。そもそも福音書などは、そのように書かれていると捉えるべきではありますまいか。
いま問題にするのは、これに対する人々に反応です。「人々」と言いましたが、そこにいたのはユダヤ人ばかりでなく、改宗者もいたはずです。単なる異邦人もいたのかもしれません。各地の出身者がいたからこそ、異言の確かさが証言されていますが、それはもちろん、福音が世界へ宣教されていくことを象徴していました。人々は、心を刺された、と記されています。このペトロの説教は、人々の心にグサリときました。いまの私たちの説教に、それがあるでしょうか。
教会のリーダーとしてペトロが重んじられていたこともここから窺えます。人々は「何をしたらよいのか」不安になりました。「する」という語は「作る」と同じ語です。自分のこれからの人生をどう形作っていくものか、問うています。世の人々はクリスチャンに、人生に作っていくべきものは何であるのか、尋ねているのです。
これに対する教会の答えは、悔い改めることでありました。洗礼・罪の赦しの結果、聖霊を受けることが約束されます。イエスの十字架で罪の赦しは、存在論的に成立しています。しか、当人の信の内ではまだ確立していません。判断能力がある人であれば、それぞれが神の前に出ることでこれを確立していくことになります。
与えられているのは、この約束。主は恐らくすべての人を招いています。福音書と使徒の記録とを知る人は、すべて招いています。招くということは、これを断る者もいるということです。神は、断ることのない人々を、もしかするとすべて救う憐れみを有しているかもしれませんが、こざかしい理屈をこねて断る人々は、審くことになるのでしょうか。
この時代から救われなさい、とペトロは人々に勧めました。これは、教会全般への勧めであると言えるでしょう。時代は曲がっているからです。それは今もなお響く指摘となります。このように見ていく私たちですが、罠があります。それは、この私もまた、その曲がった時代の中にいる、ということです。聖書の呼びかけや勧めは、私へ向けての神の声なのです。
救われるというのは、癒されると言い換えることもできましょうか。冒されている病があります。それが癒されることが必要です。また、神の言葉がそれを癒します。人々の内から、仲間に加わった者も少なくありませんでした。洗礼を受けて過去の自分に死に、仲間となってパン裂き・交わり・祈りに熱心な生活を始めました。これも、いまの私たちがクリアしているのかどうか、チェックボックスとして目の前に現れてくる項目なのです。


