人とは何者なのでしょう
チア・シード
詩編144:1-15
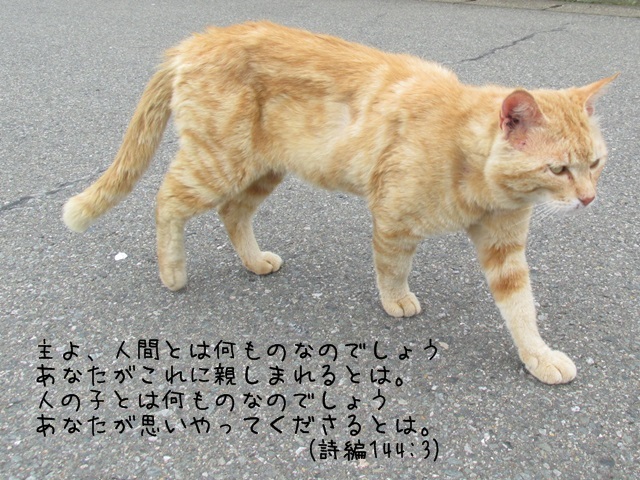
人とは何者なのか。ダビデとされる詩人は驚きます。このような驚きなしには、神に向かうことはできないでしょう。神の前に出るとき、一体自分は何であるのかと問われる思いを忘れてはいけません。まさか、それを一度も経験したこともなく、クリスチャンの顔をしているというようなことはありますまいが。
神は私の外から作用してきます。もちろん、内なる神という表現もあります。神が私の内にいるという意識が誤っているとは少しも思いません。しかし旧約聖書の中で果たしてそれがあったかというと、分かりません。人は神を畏れ、大いなる存在、創造主として崇めており、見上げていたことでしょう。
自分を客観視することも、旧約の時代にはどれほどできていたか分からないと思います。神と自分とがその図の中にいる、という図式を思い浮かべるようなことを、人がしていたかどうか、疑問です。しかしこの詩人は、どこか客観的に、神と自分と、そしてまた自然や世界を想定しながら、人とは何者であるのか、という問いかけをしました。
この見方には、ある種の新しさを感じます。ダビデとして、危機の中を主に救われたいと祈り願っていたことは想像に難くありません。大自然を想像し支配する神が、たとえ大水の底にあっても私を助けてくださるという確信は大したものです。ただ畏れ従うだけでない、神のなす業を思い描く、抜きん出た視点があるような気がします。
それから異邦人の具体像がここに出てきます。それが語ることは空しく、することは欺きであると繰り返します。ん、待てよ。日本人はここでいう異邦人の中にいることになりますね。いまもなおそういうことではありませんか。イスラエルのような主に導かれた民のメンバーではないのです。新約の光の中で神のイスラエルとして変えられたキリスト者であっても、しょせん異邦人は異邦人です。
だとすれば、詩編に描かれた「異邦人」のようなことを私たちがやっているのではないか、反省する価値はあると言えるでしょう。異邦人でない民は幸いだと詩人は祝福しています。イエスが、幸いだと告げる対象の中に、私たちは迎えられたと信仰していると思いますが、空しいことを語り行いを欺きの中に置いていないか、いま一度考えさせられます。
自分の信仰は正しい、自分の聖書の理解は正しい、といつの間にか自慢し、また豪語するようになっていないか、私たちは耐えず自らを吟味しないといけないのではないでしょうか。案外、そのようなずらしの中に陥っているものです。詩を味わいましょう。主を神とする民が幸いなのです。自分で自分を幸いと自認しているのではないのです。


