当事者と傍観者
チア・シード
マルコ3:20-30
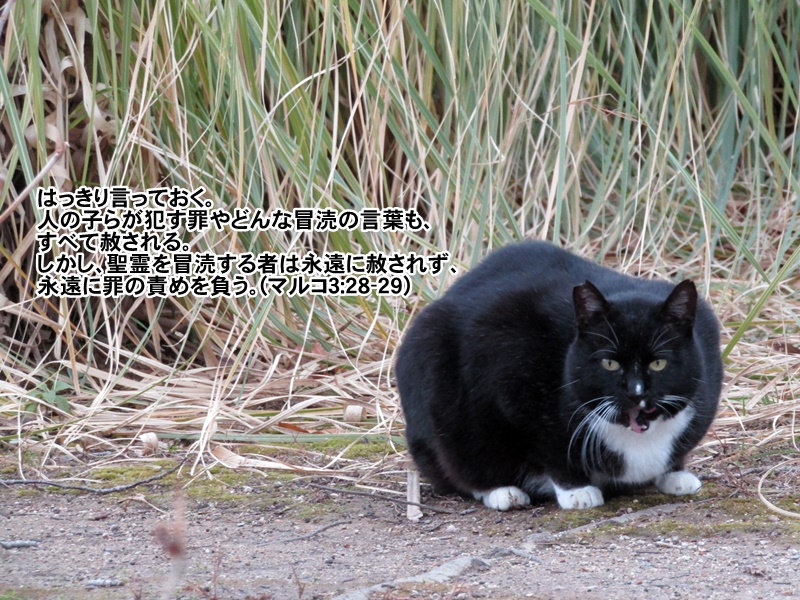
カファルナウムに、弟子たちと暮らす共同体の拠点があったと思われます。群衆は、イエスの評判を聞いて、そこへも集まってきます。「また集まって来て」というので、度々だと分かります。食事すらままならぬことまで書かれていますから、よほど対応に追われていたのでしょう。コロナ禍で混乱した病院関係や保健所も大変だったことでしょう。
イエスの身内が取り押さえに来たそうです。只ならぬ事態でした。イエスが奇妙なことになっていたのです。狂気の沙汰と思ったのは、訳により、世間の人々であったり、身内の者であったりします。私は、両方が思ったのではないかと考えます。マルコが、どちらをもうまく指せるように記述したのだとするのは、買いかぶっているでしょうか。
エルサレム当局の律法学者たちも、イエスを悪霊が支配していると言っていたというので、イエスと弟子たち、そしてそこに集まる群衆たちも、常識的な世の中から浮いていたのです。これを、当事者意識で想像することはできるでしょうか。癒す者・癒される者当人にとっては、切実な問題であり、真実な出来事ですが、傍観者からはそうは思えません。
傍観者の好奇の眼差しから見えるものは、狂っているという決めつけによる安心の結論です。イエスは彼らを呼び寄せて、サタンが内輪もめをするようなことを考えるべきではないと説明します。ただ言わせておかずに弁明をしたのです。この「彼ら」は、やはり律法学者でしょうか。イエスの身内の人たちはそれに含まれたのでしょうか。
身内の人たちはわざわざやってきたのです。だからこそそこに、きちんと説明した、とも考えられます。サタンの企みとその支配が立ちゆかないならば滅びよう、と言いました。敵を攪乱し、同士討ちをさせた、旧約のいくつかの戦いが思い起こされます。サタンは同士討ちはせず、最後まで神に対抗していた様子が黙示録から窺えます。
イエスには、こうしたサタンの支配というものが何らかの形で存在することを前提として話をしています。妙な擬人化さえしなければ、サタンなど実在しない、などとは言えないのです。さらにイエスはテーゼを絞ります。罪も冒涜の言葉も赦されるが、聖霊を冒涜する者は赦されない、という有名なフレーズです。それは永遠の罪なのだというのです。
神のなすことを、汚れた霊がしたのだと言いのけるようなことを禁じたように見えます。当事者というものは、そもそも命懸けです。それを、安全な場所に立ち、何の痛みも覚えない傍観者が、狂っているなどと無責任に痛めつけることを言ってはならないのです。自分はその問題に関わっていないのだ、などと思い違いをする人は、いつの世にもいます。


