ヤコブ書の抵抗
チア・シード
ヤコブ2:14-18
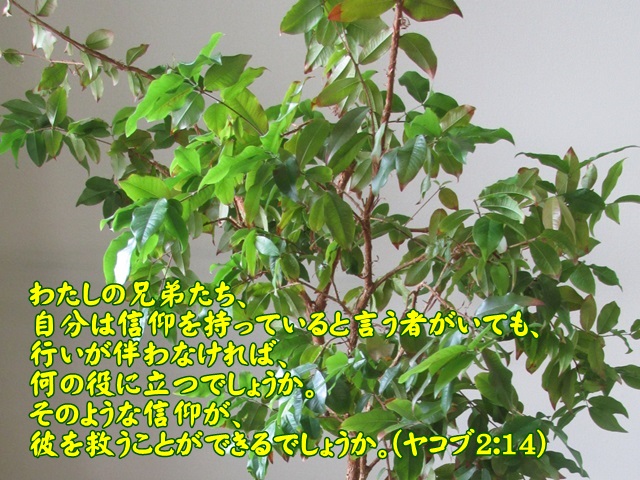
実のところ、私たち人間にはしっくりくる教えだと思います。いくら口先で綺麗事を言っていたとしても、実際何もせず手をこまぬいているばかりの人を、私たちは快く思わないし、立派な信仰者だなどと称しはしないものです。理屈というものを必ずしも無視する訳ではありませんが、汗して活動している人のことを私たちは尊敬すると思うのです。
ヤコブ書の文脈からすると、ここまで貧しい人を差別している教会の実情に苦言を呈し、憐れみをかける必要を説いていました。この流れで、現実の行動はどうかと問いかけるようにして、この「行い」の称賛へと目を移したように見えます。ヤコブ書のメッセージはこのことと、貧者の救済とに主眼があったのではないかと思われます。
信仰と行いの問題は、当該箇所から後へも続きます。パウロの教えとは対立するように見えますが、当時パウロの教えが極端で好ましくない方向に解され利用されていたとすれば、それに対するカウンター思想として、現れて然るべき内容であったとも言えます。そのパウロの思想がキリスト教の主流でありすべてだと考えられては困る、というわけです。
ひとは行いによってではなく、信仰によって救われる。これは後のプロテスタントの強調点でもありました。それはまた、カトリックの当時の歪みに対するカウンターであったのでしょうが、それは政治的な背景をも巻き込みながら、ヨーロッパを二分するかのように争いを起こし、人命を多数奪う醜い歴史を刻んでしまいました。
ヤコブ書の書かれた時代、キリスト教はそれほど社会の強者であったわけでなく、せいぜい内輪で対立する程度でしたが、パウロの強調点はどちらかというとエリート好みの思想へと傾いており、コリント教会のようなところを相手にパウロが悩んでいた文書が中心になると、貧民の助けというよりはセレブの心の平安を支えていた面が表に出るものでしょう。
パウロは確かにイエスと出会った。けれどもそれはいきなり復活のイエスでした。ヤコブ書の記者は、キリストの直接の弟子たちに身を置いて考えました。十字架と復活のキリストしか知らないパウロの思想でキリスト教が成り立つのなら、あのイエスの地上生涯は何の意味があったのでしょう。まるで死と復活がすべてのように扱ってよいのか。
パウロは、イエスの旅の生涯に接してはいないのです。キリストの人生を知らないのです。そのパウロはまた、貧しい漁師などではなく、生まれながらのローマ市民であり、ユダヤ幹部候補のエリート教育を受けました。優秀な出世街道真っ盛りの知識階級でした。確かに伝道で苦労はしましたが、根はええとこのぼんぼんでした。
そこからの思想だけがキリスト教ではないはずです。エリート層が近づかない地の民に入り込んだイエスの姿が捨象されてはいけない。パウロ主流の教会に対抗意識を覗かせていることは確かです。なにも、教義を戦わせているわけではありません。私たちも口先だけのエリート視点で、聖書を都合良く解釈して満足していないか、自省する必要があるのです。


