分岐点に立たされている
チア・シード
申命記30:15-20
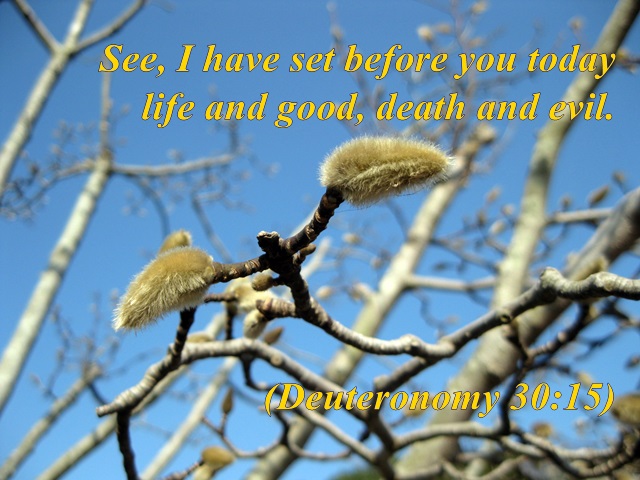
神は祝福を与える約束もしましたが、他方呪いについては、祝福の何倍もの言葉で警告をしています。これは、ホレブの十戒の契約とはまた違う契約なのだとほのめかす契約であることに注目しましょう。かつてのイスラエルの伝統を否定することはできません。しかし、申命記記者は、研究者が言うようにバビロン捕囚の経験の中で編集しているとすれば、かつての契約を継承しつつも、新たな形で結び直す改訂版をここに示したと言えるでしょう。
モーセが荒野の度を間もなく終えようとしています。イスラエル民族は、カナンの地に正統的に必然性をもって住むようになったのだと歴史を刻みます。この旅の振り帰りを全イスラエルに示しましょうその意味をはっきりさせておきましょう。ここにいま、分岐点があります。どちらの道を行くものかを全員に問います。右は祝福へと至る道、左は呪いへと落ち込む道。主は、他の日ではなく、今日、それを命じ、問います。
神の道を選び、そこを歩むには、掟を守る必要があると言います。それはいいにしても、守った後に待ち受けているのは、殆ど現世利益と呼んでもよいような幸福の羅列。まるで成功哲学のような按配に、神を信じるならばこの世で幸せになれるという単純なメッセージを裏打ちするかのように、神の言葉は安易に世の波に乗せられているのではないでしょうか。
申命記が記されたのがバビロン捕囚を知る中であったとすると、やはりその痛みはただごとではありませんでした。神殿は滅び、おもだった知恵者や技術者は連行され、国は再建の可能性を断たれた状態となりました。これはどう考えても、呪いの結末です。この悲惨なイスラエルの末路を、神の故ではなく、人間の責任であるとしたのが、預言者たちに与えられたビジョンでした。
カナンの地で安泰するには、ひとえにこの主のみを神として掲げ、主に従うことが必要となるのだ、と信仰復興を目指す申命記グループは告げます。土地を継ぎ、主をひたすら拝することで命を得るというところに、永遠の命と後に呼ぶものの萌芽がありました。与えられる土地で平和がある、捕囚期の理想は、何よりもそこにあったと思われます。捕囚期の描く契約では、現実の土地こそが理想であり祝福であったのです。捕囚期に、荒野の時代を描くという錯綜した時間軸の中で、イスラエル民族は自身の姿を、この分かれ道に断つ者として描いたのでした。
これが、さらにヘレニズム期を経てローマ帝国の支配を受けると、またイスラエルもしくはユダヤと呼ばれる人々の信仰観が変貌してきます。地上の生活に望みを置くことが空しく思われると、「長く生きる」という言葉の意義が変化してきます。永遠の命へとバージョンアップします。さらに新しいキリストによる契約は、すっかりその流れを受け継ぎました。
私たちクリスチャンもまた、この岐路に立たされています。心変わりや惑わしなどを挙げますが、これらは自分ではそれと気づかないからこそ恐ろしい問題なのです。自分を基準とすることができないというわけで、それ故に近代人が陥った罠であるとして、私たちは警戒しなければならないでしょう。今日ここにも、その分岐点があります。悪しき者は常に、その道を誤って選択するように、待ち受けています。私たちは、瞬間瞬間、分岐点の前で試されているのかもしれません。


