ナアマンの陰に信仰あり
チア・シード
列王記下5:8-14
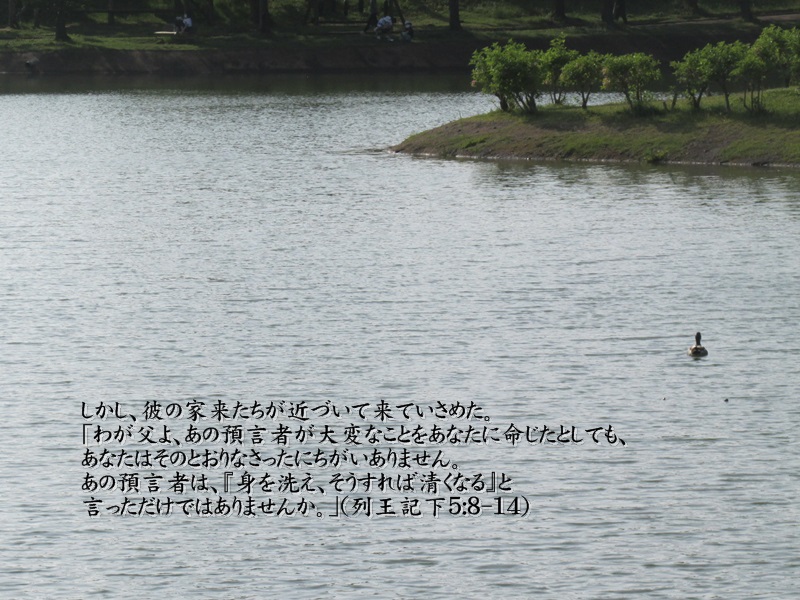
アラムの将軍ナアマンの物語は、この5章全体にわたります。今回の箇所は、イスラエル王へ届いた癒しの依頼に、王がキレたところから始まります。ナアマンが皮膚に症状が顕著に出る怖い病気にかかったのですが、イスラエルに預言者がいて治すという話を聞いて、イスラエル王に治療を頼むという知らせが届いたのです。政治的には無理難題です。
エリシャがこのことを聞き、怒るな、大丈夫だ、と王に伝えます。イスラエルの預言者のことをむしろ知らしめたまえ、と告げました。一体エリシャとは何者なのでしょう。まことに人間味のない、全能者であるかのような態度をとります。しかしそれだけ信頼され有名だったからこそ、アラムにまでその評判が伝わっていた、とも言えましょう。
王はアラムへ返答します。エリシャを信用したのです。ナアマンは軍人としての姿で駆けつけます。エリシャの家の戸口まで来たということは、従順な姿勢のように見えます。しかしエリシャは、直接ナアマンの前に現れることはしませんでした。イエスは直接その人に触れて癒すことが多かったのですが、ここでエリシャは言葉だけを渡します。
確かにイエスも、言葉だけで癒したこともありました。エリシャは多面的に、イエスの姿を映し出しているようにも見えます。ヨルダン川へ行け。そこで七度身を浸せ。告げた言葉はそれだけでした。そうすれば、体は元に戻るのだ。清くなるのだ。これは汚れた病だとされていました。アラムでも恐らくそのように捉えられていたのでしょう。
アラムやモアブなど、イスラエルの親族とも言えそうな民族の間にも、イスラエルの律法は浸透していたと言えるのかもしれません。文化としての共通項が何かあったことは間違いないでしょう。しかしこれを聞いてナアマンは怒ります。自分の懐いていた、癒しのイメージとはあまりに違っていたからです。なんだ、このペテン的な仕打ちは。
私たちも、己れの思い込んでいた結果や方法でない場合に、神を疑い、自分の考えのほうをこそ正しいと思うことがあります。神ならばこうするはずだ、と自分が神を制約している構造がそこにはあるのですが、なかなか気づきません。そんなときに、自分で気づかなくても、誰かが天使のように、助けて知らせてくれるという場合がありませんか。
ナアマンの家臣たちが、預言者の言葉に従いましょう、と進言しました。この家臣たちは、とりあえずの感想を漏らしただけかもしれませんが、これを一つの強い信仰だと見てもよいのではないかと私は考えます。筋が通ったことを言ってもいます。自らその構造や意味が分からなくとも、ありのままに受け容れるしなやかさを見る思いがします。


