共同体の結束を図る思い
チア・シード
ヨハネ一2:1-3
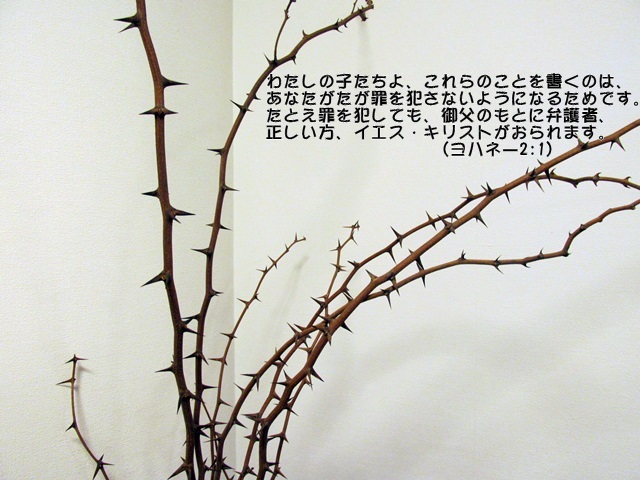
掟を守るなら、神を知っていたということを知る。グノーシス主義はこの「知る」という語を膨らませた思想を展開し、初期のキリスト教に大きく警戒されたと言われています。このヨハネの手紙の時期にも、それはすでに現れていたとされ、著者は逆にその「知る」という語を用いて対抗しているかのようにも見えます。
神を知る、それは神と出会う体験をしているということです。神と心の、あるいは霊の交流があったということです。深い人格的交わりがあることが、ユダヤ式の「知る」ということです。そして、人が神との関係の中にあるのだということを、傍らにいる私たちも体験するのだし、体験するべきだと考えられています。
クリスチャンとしての交わりがここに成立します。共同体、今でいう教会としてのあり方をここに提出しているようなものです。本書簡は、回覧して読まれることを意識していたはずですが、当時手紙という形式が権威あるものとされていたようなのに、もはや手紙という形式に縛られない新しい感覚で書かれてあるようにも窺えます。
ヨハネと名のる者は、異端的な思想を排除しようとしています。時にいやらしいほどの言い回しや議論をもちかけ、異分子をつまみ出そうと画策するのですが、確かに教会はこのとき一つの危機を迎えていたはずです。ヨハネの福音書とヨハネの手紙と、どちらが先に成立したのだろうとよく問われますが、私は、一度福音書が存在したが、そこに書き足りないようなことが手紙にされ、その手紙の思想が再び福音書に書き加えられたのではないかという気がしています。つまり、連動して成立していたのではないか、と。
ここでは罪を犯さなくなるという一つの理想的状態が語られますが、イエスが弁護をして傍らにいてくださるという安心感が強調されています。福音書のイエスとの強いつながりが感じられます。そしてヨハネ14-16章に4度しか登場しない「パラクレートス」という語がここにも使われ、連動しています。
見よ、神の小羊。バプテスマのヨハネに語らせた福音書の著者が、その小羊なるイエスをここにまとめ、私たちの、いやそればかりか全コスモスの罪のための、宥めの供え物となったのだと告げています。そこから急に掟となりますが、この掟とは、この後に紹介していく、愛し合うという掟です。共同体は内部的に一層の結束を図る必要がありました。それというのも、キリストに敵対する勢力に対抗するためでした。掟という文字面に囚われず、置かれた情況の中で、ヨハネの手紙を味わっていくようにしましょう。


