知恵があるという思いこみ
チア・シード
コリント一3:18-23
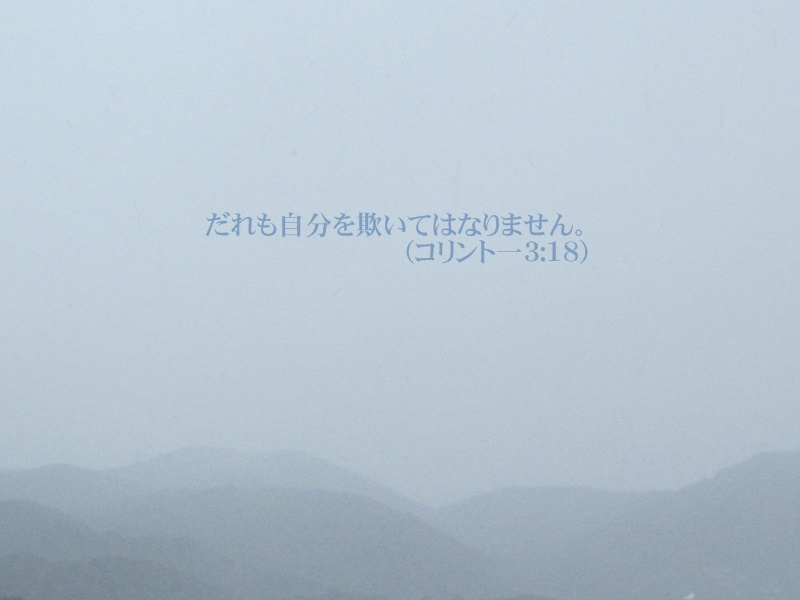
自分に知恵があるというふうに思わないことだ。パウロはこれを強調します。ここまでの議論をひとつまとめているかのような箇所かもしれませんが、これまで告げてきたような問題は、要するに今風に言えば「自己欺瞞」でした。人間の知恵なるものがどういうものであるかを追及するとき、それは自己欺瞞ではないかと言うのです。
人の知恵で、何もかも分かったような口を利くことが如何に愚かであることかを覚らせようとしているようです。パウロ自身、ユダヤ教については一流の学びを受けた、その道のエリート幹部でした。そうした自分の人生を振り返るとき、こうした反省が痛みを伴って迫ってくるのではなかっただろうかと想像します。
この世界には、人間が支配できるものがたくさんあります。恰も人間の手に、すべての存在者は委ねられているかのようです。けれども、すべてのすべてがそうではありません。この人間すら、キリストの手に運命を握られています。そのキリストは父なる神のものであるとここでいうのは、どういう意味であるのか、恐らく議論がありましょう。
パウロはキリストと神をどう理解していたのでしょうか。少なくとも、キリストという目に見える形で、私たちに現れた姿を神のひとつのあり方として捉えることで、私たちは福音というものに合点がいくような気がします。そんな貧しい精神の私は、所詮自分の知恵を貫くしかありません。自己の信じるところしか考えられず、それに嘘はつけません。
それでもなお、自己を騙すようなことはしたくないと思っています。ところが、そうすると、どこまでいっても人間の知恵は、人間の知恵でしかありません。そうやって行き詰まるしかないのでしょうか。自己欺瞞とは、いったい何なのでしょうか。「だれも自分を欺いてはなりません」というパウロの言葉と向き合うと、何が見えてくるのでしょうか。
実験的に捉えてみます。自己欺瞞とは、「自分を正しいとすること」ではないか、と。あるいは「自己義認」と言ってもよいでしょう。自分を自分が正しいと見なすこと、そう主張して止まないこと、その態度で他人に迫ること。それはついに、神に対しても向けられかねません。人間の、自分の、この傾向性に気づくことが求められているのではないか。


