まさかの皮肉
チア・シード
コリント一1:18-31
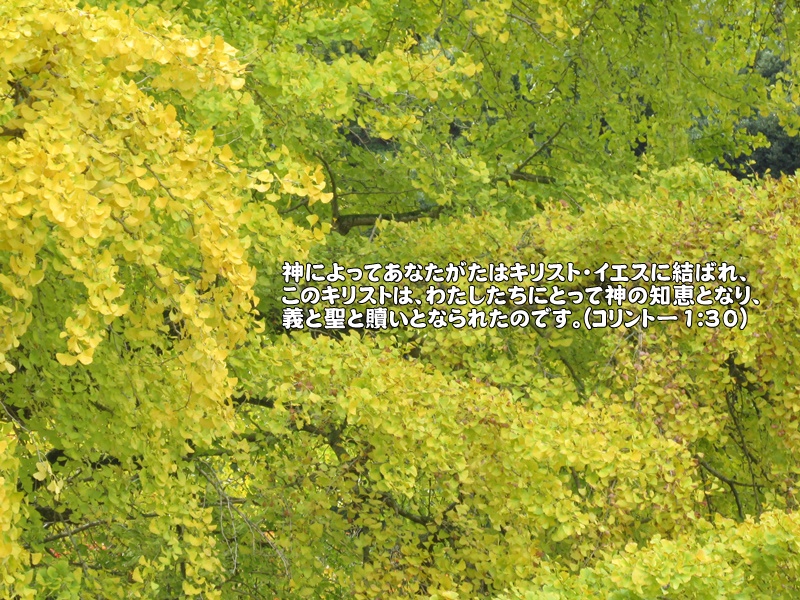
「知恵」という概念は、今の私たちが自然に抱くものと、過去の人々あるいは地域の異なる人々のものとは一致するとは言えないでしょう。しかし細部を度外視するならば、歴史を振り返る特権をもつ私たちの目から見ても、納得のいく分析がここにあります。ユダヤ人とギリシア人の対比を私たちは、ヘブライズムとヘレニズムと呼んでいます。
これらは、西洋文明の2つの源流だと理解されています。もちろん、ケルトやゲルマンなどの文化を無視することはできませんが、これら2つの中心があることについて、異論を差し挟む人はいないでしょう。これらは、それぞれしるしを求めたり、知識論理を求めたりします。パウロがそれを適切に指摘していることは注目に値します。
パウロは同じソフィアというギリシア語を用いていますので、少し紛らわしいのですが、当然違う意味合いで用いている場面があります。いわゆる知識という否定的な側面と、神の知恵という、人格的で総合的なものとを、同じ語で示しているので区分けする必要があります。神の知恵は、知的矛盾をも1つのものとして含み入れてしまうものです。
それは逆説どころではありません。クザーヌスが「反対の一致」と言い、パスカルも「矛盾の統一」と称した考え方です。もしかするとソクラテス以前の哲学においてもあったかもしれません。キリストにおいて、死と生が統一されていきます。世の知恵では片付けられない問題を、神の知恵はいわば止揚してしまうのです。
神の知恵は、むしろ世で誇るもののない弱い者たちの内で輝いているとパウロは見ています。ここで考えてみます。コリントの教会にいた人々は、どういうステイタスであったでしょうか。豊かな都市は、文化水準も高く、それなりに知識も浸透していたことでしょう。でも、文化階級から外れた貧困層の人々もいたことも確かでしょう。
世で軽んじられている者を神が選んだ。これは慰めなのでしょうか。それとも、皮肉なのでしょうか。自分をひとかどの者と考えている人々へ、パウロは痛烈な皮肉を浴びせているという可能性を考えてはいけないでしょうか。誇る者は主を誇れとまでパウロは言っています。キリストの業は、すべての文化対立を超えて、1つにできるのです。


